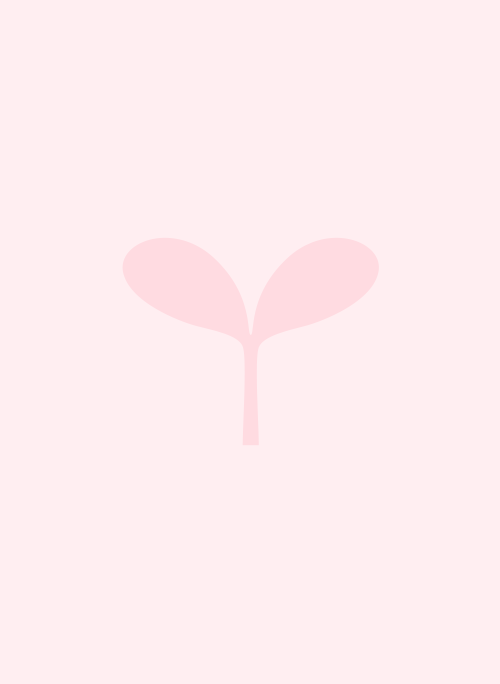生まれて最初に感じたことは、初めて息をする苦しさよりも、「ここはどこだ?」という疑問だった。
後で聞くところによると、俺は異様なほど精神の発達が速いらしく、非常に大人たちに気味悪がられた。
周りの人間だけではない、親さえも俺を遠ざけた。
案の定、俺はある大きな研究施設に身を売られ、労働者として扱われた。足首についた鉄の塊は、ガリガリと俺の皮膚を削っていった。
そんな生活に変化が起きたのは、施設に入って3年経った6歳の頃だ。
急に研究施設の最高責任者が死亡し、新しい者が襲名した。「大神零(おおがみ ぜろ)」という、柔らかい物腰と顔つきをした男だった。
零は俺たちから枷を外し、一人一人に狭いながらも部屋をくれた。毎日3食の食事と、風呂も入らせてくれた。小学校にも通い、普通の生活を送ることができた。
今日は、中学校入学式。
***
満開の桜を眺めながら、俺は新しい学校生活に期待を抱いていた。小学校が同じだったやつもいるだろうから、初めもさして緊張しなくていいだろう。
こうして制服に身を包み歩いていると、ただの子供になれたようで少し嬉しい。
ふと、前を見ると、親子だろう。きっちり制服をきた子供を、安心と喜びを合わせたような目でみる女の姿があった。
女は、少しでも子供の姿が乱れると、すぐに手を出して「大丈夫?大丈夫?」と聞いた。
子供はそんな女を「平気だよ、こんぐらい」と、鬱陶しそうに受け流していた。
俺のとなりには、当たり前のように誰もいない。桜の花びらが、風で竜巻のように舞い上がっているだけだった。
いまさら、寂しいとは思わない。ただ、新鮮なだけだ。
俺は桜から目を離して歩き出した。
*教室*
「大神!また、同じクラスだなっ」
窓際の席で頬杖をついて外を眺めていた俺に話しかけてきたのは「東池裕也(とういけ ゆうや)」、小学校で3年間程同じクラスだった男子だ。
「そうだな、今年もよろしく頼むよ」
小学校の頃からクラスの中心的な人物で、明るく気さくで、俺なんかよりもよっぽど人気者だった。なにもいわなくても寄ってきて、あれやこれやと世話を焼いてくれた。
「ほらっ、座んなさいー」
ガラッと扉が開き、髪の短い女教師が入ってきた。
ガタガタガタっと生徒達が席につき、女教師は教卓に立って話初めた。
「あなた方も今日から中学生です。遊んでばかりおらず、勉強や部活動に励み…」
またつまらない話か…、と俺は聞き流して外を眺めた。
つまらないな、本当に。
***
もうキチンと着た制服もいい感じに乱れ、帰って来た頃にはスクールバックを片手で担ぐという有り様だった。
「ただいま…」
自動ドアの玄関を通ると、永遠と曲がりくねった廊下が続く。この研究施設は国家レベルの研究もしているとかで侵入者が絶えないらしく、研究施設のなかは迷路のようになっている。下手したら一生出られないとか。何年も住んでいるから今一実感はない。
この施設の真ん中には、風呂と食堂がある。食堂では、施設に住む者達が集まり情報を交換したりしている。施設に住む者は、世間を賑わす通り魔やスパイのようなことをしている奴等もいるので、そいつらの武勇伝を聴くのもなかなか面白いのだった。
後で聞くところによると、俺は異様なほど精神の発達が速いらしく、非常に大人たちに気味悪がられた。
周りの人間だけではない、親さえも俺を遠ざけた。
案の定、俺はある大きな研究施設に身を売られ、労働者として扱われた。足首についた鉄の塊は、ガリガリと俺の皮膚を削っていった。
そんな生活に変化が起きたのは、施設に入って3年経った6歳の頃だ。
急に研究施設の最高責任者が死亡し、新しい者が襲名した。「大神零(おおがみ ぜろ)」という、柔らかい物腰と顔つきをした男だった。
零は俺たちから枷を外し、一人一人に狭いながらも部屋をくれた。毎日3食の食事と、風呂も入らせてくれた。小学校にも通い、普通の生活を送ることができた。
今日は、中学校入学式。
***
満開の桜を眺めながら、俺は新しい学校生活に期待を抱いていた。小学校が同じだったやつもいるだろうから、初めもさして緊張しなくていいだろう。
こうして制服に身を包み歩いていると、ただの子供になれたようで少し嬉しい。
ふと、前を見ると、親子だろう。きっちり制服をきた子供を、安心と喜びを合わせたような目でみる女の姿があった。
女は、少しでも子供の姿が乱れると、すぐに手を出して「大丈夫?大丈夫?」と聞いた。
子供はそんな女を「平気だよ、こんぐらい」と、鬱陶しそうに受け流していた。
俺のとなりには、当たり前のように誰もいない。桜の花びらが、風で竜巻のように舞い上がっているだけだった。
いまさら、寂しいとは思わない。ただ、新鮮なだけだ。
俺は桜から目を離して歩き出した。
*教室*
「大神!また、同じクラスだなっ」
窓際の席で頬杖をついて外を眺めていた俺に話しかけてきたのは「東池裕也(とういけ ゆうや)」、小学校で3年間程同じクラスだった男子だ。
「そうだな、今年もよろしく頼むよ」
小学校の頃からクラスの中心的な人物で、明るく気さくで、俺なんかよりもよっぽど人気者だった。なにもいわなくても寄ってきて、あれやこれやと世話を焼いてくれた。
「ほらっ、座んなさいー」
ガラッと扉が開き、髪の短い女教師が入ってきた。
ガタガタガタっと生徒達が席につき、女教師は教卓に立って話初めた。
「あなた方も今日から中学生です。遊んでばかりおらず、勉強や部活動に励み…」
またつまらない話か…、と俺は聞き流して外を眺めた。
つまらないな、本当に。
***
もうキチンと着た制服もいい感じに乱れ、帰って来た頃にはスクールバックを片手で担ぐという有り様だった。
「ただいま…」
自動ドアの玄関を通ると、永遠と曲がりくねった廊下が続く。この研究施設は国家レベルの研究もしているとかで侵入者が絶えないらしく、研究施設のなかは迷路のようになっている。下手したら一生出られないとか。何年も住んでいるから今一実感はない。
この施設の真ん中には、風呂と食堂がある。食堂では、施設に住む者達が集まり情報を交換したりしている。施設に住む者は、世間を賑わす通り魔やスパイのようなことをしている奴等もいるので、そいつらの武勇伝を聴くのもなかなか面白いのだった。