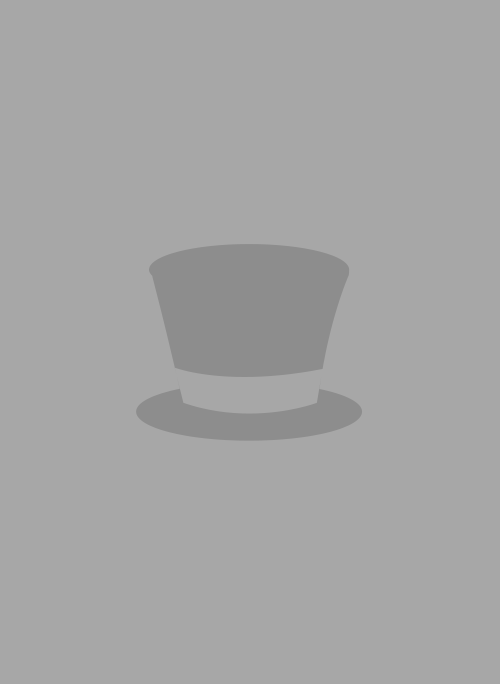海斗のその言葉は、和陽にとっては思いもよらぬものだったのだろう。ビクンと体を震わせている。しかし、そのことで上げ足を取られるわけにはいかないと思っているのだろう。その証拠に、彼はことさら落ち着いた様子で海斗の言葉に応えている。
「そんなことも言ったかもしれないね」
「やっぱり、そうなんだ。じゃあ、おじさんは友梨がどうなったのかっていうことも、ある程度までは分かっているんじゃないんですか?」
今の海斗にとっては入学式よりも友梨の行方の方が気になるのは間違いない。自分の問いかけに肯定的な返事をした和陽に、さらに食い下がっていく。だが、ここであっさりと尻尾を掴まれるほど和陽も与しやすい相手ではない。彼は表情をうかがわせない笑顔を貼り付けると、ことさら穏やかな調子で海斗に語りかけている。
「その返事は、また後にしてもらえるかな? 今は学校に行って、入学式を済ませてくる方が大事なことだと思うからね。ほら、なんといっても、先生に友梨が欠席するってことを連絡してもらわないといけないし」
「え~、俺がですか? でも、それって本来は保護者であるおじさんがするべきことじゃないんですか? ま、やれって言われるんなら、やっちゃいますけど」
和陽の言葉に、海斗はぶぜんとした表情を浮かべて居る。だが、ここで反論しても軽くかわされてしまうということも分かっているのだろう。渋々といった表情ではあるが、和陽の言葉に頷いている。
「やっぱり、海斗君はちゃんと分かってくれるんだね。いや~、助かるよ。そうだね、友梨は体調を崩して休むっていうことにしておいてもらえるかな? 第一、本当のことを言ったとしても、誰も信用してくれないしね」
「そうでしょうかね」
和陽の言葉に、不満げな口調で応えている海斗。だが、そんな彼の頭をポンと軽くたたきながら、和陽は話し続けている。
「そうだよ。海斗君だって、あれを目の前で見たからこそ、そんなことを言うんだろう? 人間って不思議なものでね。信じがたいことを目にした時って、それを真実だとは思わないように感じてしまうものなんだよ。だからこそ、誰がきいても納得する理由にしておいた方が、余計な詮索を受けなくてすむ」
その言葉に含まれているのは剣呑な響き。そのことに気が付いた海斗が何かを口にしようとした瞬間、和陽は彼のl口を押えると、ニッコリと笑っている。
「海斗君、今は学校に行こうね。おじさんも、まさかこんな時間に事が起こるとは思ってもいなかったんだ。確かに、今日は朔の日だから用心はしていたんだけどね……」
どこか悔しさをにじませるような響きが和陽の口からは漏れている。そのことを不思議に思う海斗が口を開く前に、和陽がその背中をグイっと押している。
「さ、早く行った、行った。友梨のことは心配しないように。もっとも、そうはいっても海斗君が友梨のことを心配してしまう気持ちもわかるからね。そうだ、今度の休みの日にでも話をしようか。それまでくらいなら、待てるよね?」
一見、穏やかな口調ではあるが、その言葉の端々からは逆らうことができないような力が感じられる。そのことに気が付いた海斗は、首を縦に振ることしかできない。そして、どこか納得していないというような表情で海斗が立ち去った後。和陽はそれまでとは全く違った真剣な表情で、神木と並んでいる桜の木を睨みつけていた。
「そんなことも言ったかもしれないね」
「やっぱり、そうなんだ。じゃあ、おじさんは友梨がどうなったのかっていうことも、ある程度までは分かっているんじゃないんですか?」
今の海斗にとっては入学式よりも友梨の行方の方が気になるのは間違いない。自分の問いかけに肯定的な返事をした和陽に、さらに食い下がっていく。だが、ここであっさりと尻尾を掴まれるほど和陽も与しやすい相手ではない。彼は表情をうかがわせない笑顔を貼り付けると、ことさら穏やかな調子で海斗に語りかけている。
「その返事は、また後にしてもらえるかな? 今は学校に行って、入学式を済ませてくる方が大事なことだと思うからね。ほら、なんといっても、先生に友梨が欠席するってことを連絡してもらわないといけないし」
「え~、俺がですか? でも、それって本来は保護者であるおじさんがするべきことじゃないんですか? ま、やれって言われるんなら、やっちゃいますけど」
和陽の言葉に、海斗はぶぜんとした表情を浮かべて居る。だが、ここで反論しても軽くかわされてしまうということも分かっているのだろう。渋々といった表情ではあるが、和陽の言葉に頷いている。
「やっぱり、海斗君はちゃんと分かってくれるんだね。いや~、助かるよ。そうだね、友梨は体調を崩して休むっていうことにしておいてもらえるかな? 第一、本当のことを言ったとしても、誰も信用してくれないしね」
「そうでしょうかね」
和陽の言葉に、不満げな口調で応えている海斗。だが、そんな彼の頭をポンと軽くたたきながら、和陽は話し続けている。
「そうだよ。海斗君だって、あれを目の前で見たからこそ、そんなことを言うんだろう? 人間って不思議なものでね。信じがたいことを目にした時って、それを真実だとは思わないように感じてしまうものなんだよ。だからこそ、誰がきいても納得する理由にしておいた方が、余計な詮索を受けなくてすむ」
その言葉に含まれているのは剣呑な響き。そのことに気が付いた海斗が何かを口にしようとした瞬間、和陽は彼のl口を押えると、ニッコリと笑っている。
「海斗君、今は学校に行こうね。おじさんも、まさかこんな時間に事が起こるとは思ってもいなかったんだ。確かに、今日は朔の日だから用心はしていたんだけどね……」
どこか悔しさをにじませるような響きが和陽の口からは漏れている。そのことを不思議に思う海斗が口を開く前に、和陽がその背中をグイっと押している。
「さ、早く行った、行った。友梨のことは心配しないように。もっとも、そうはいっても海斗君が友梨のことを心配してしまう気持ちもわかるからね。そうだ、今度の休みの日にでも話をしようか。それまでくらいなら、待てるよね?」
一見、穏やかな口調ではあるが、その言葉の端々からは逆らうことができないような力が感じられる。そのことに気が付いた海斗は、首を縦に振ることしかできない。そして、どこか納得していないというような表情で海斗が立ち去った後。和陽はそれまでとは全く違った真剣な表情で、神木と並んでいる桜の木を睨みつけていた。