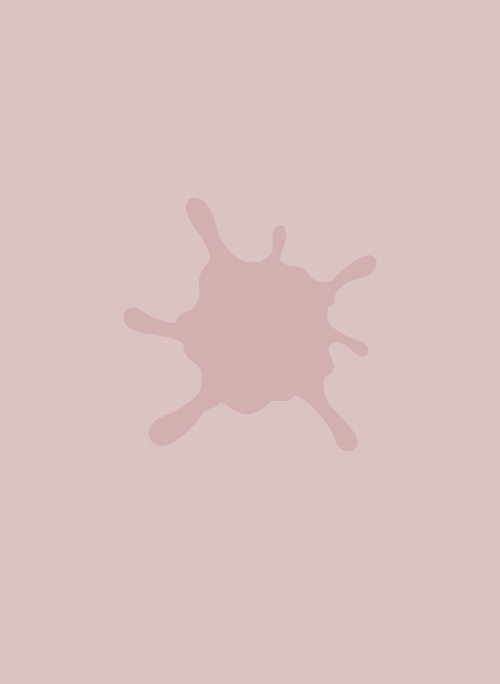「ははっ、そんなに必死にならなくてもいいでしょう」
「いや、それはその……」
さっきからずっと、彼はクスクスと笑い続けている。
……そんなに私の口調は滑稽だったかな。
「笑いすぎですよ、シノノメさん」
「いえ、失礼。可愛いなと思ってしまったもので」
「なっ、可愛いって―――」
「冗談ですよ」
その言葉に声にならない声を上げる。まんまと騙された! 一瞬でも盛り上がってしまった私は単純そのものだ。
「あらま、単純ですね」
「シノノメさんって何気にいじわるなんですね」
「僕ですか。まあ、それなりには」
「それなりにって!!」
それからいろいろな話をした。シノノメさんは料理が得意で、よく自分用のプリンを作ること。彼は近所の子供にいろいろなあだ名をつけられていること。職場の仲間が最近調子を崩したこと。
すべてが私にとって新鮮で、知らなかったシノノメさんが見えてくる。
堅物な人かと思ったけれど、案外そうでもないのかもしれない。特にプリンの話はシノノメさんのイメージと違いすぎて、私はしばらく笑い転げていた。
「……はあ、シノノメさんって面白いんですね」
「また冗談ですか?」
「いえいえ! これは心の底から思ってますよ」
私がそう言うと、
「あれ?」
―――ツー ツー ツー ツー ツー……
なぜだか通話は途絶えた。