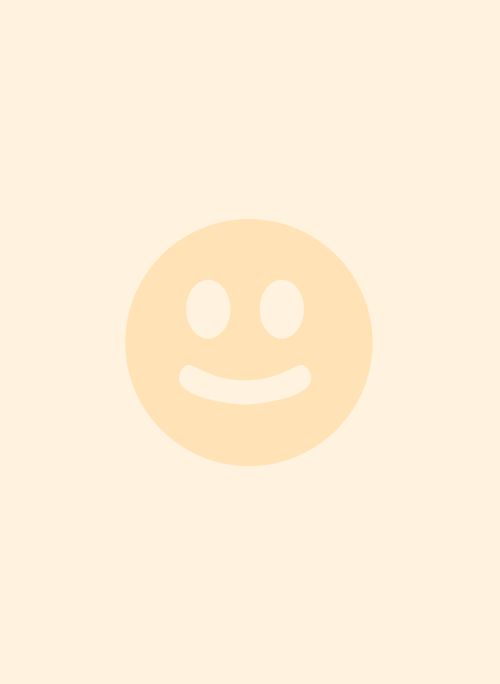星を釣ったあの日から、あたしはジンの仕事を間近で見てきた。恐らく死者だろうという人達が、ジンを拝んだり親しげに話をしたり、判決が気に入らないものだったら罵倒してみたり、その反応は様々だった。
けれど、ジンの反応はすべて同じだった。
「今までよく生きたね。次もきちんと輪廻に還っておいでよ」
そうにこやかに言った後に、決まって「バイバイ」と言いながら手を振る。そんなふうに言われてしまうと、激昂していたはずの死者たちも、何だか拍子抜けしてしまうのか、おとなしく案内係に連れられていった。
こんな感じで、飽きる飽きない以前に、何だか最早どうでもよくなる程の人数の魂魄を死後の世界に案内して、一息吐いてからジンは伸びをする。それから、あたしの方に振り向いて、「疲れちゃった、肩揉んで」等とほざく。
「アンタ凝るような筋肉無いでしょ」
「失礼な。こう見えて実はマッチョなんだよ、私。ショルダーマッチョ」
「どんなマッチョだよ」
こうして間抜けなことを抜かすジンが、神様だなどと思う人は少ないだろうし、実際あたしもコイツが神様で居られることが不思議で仕方がない。案内係のお姉さんにジンに対しては敬語を使うように注意もされたが(変な名前で呼ぶなとも言われたっけ)、現にあたしはコイツに敬語のけの字も使っていない。
「じゃあ、トントンでも良いや。ねぇ、お願ぁ~い」
「伸ばしてんじゃねーよ、気持ちわりィ」
辛辣な言葉を吐きながらも、あたしは仕方なく奴の肩を叩き始める。凝っているというのは強ち嘘ではないかもしれない、少し肩が張っている気がした。
ジンは嬉しそうにニコニコしながら、あたしにされるがままになっていた。
「何ニヤニヤしてんの」
「ん~?」
だから語尾を伸ばすな、とツッコミかけて、奴が口を開こうとしたのでやめた。相変わらずニヤついたジンが笑う。
「孫に肩を叩いてもらうお祖父ちゃんになった気分」
「……やだこんなクソジジイ」
「ヒドッ。……でもさ、すごく嬉しい」
一瞬白目をむいたが、その後ジンは儚ない微笑みを見せた。
「神様だからってずっと一人で世界を見下ろしてきてさ。こういう風景を見ることも勿論あった。優しい表情で孫を見守るお祖父さんと、嫌そうにしながらも楽しそうに肩叩きをする孫。ちょっと憧れてたんだよね」
願いが一つ叶ったよ、なんてジンは嬉しそうに微笑んで、あたしの方に振り向いた。それから、さっきから機械的にジンの肩を叩き続けていたあたしの両手を包み込むように握ると、「交替しよっか」と言いながら立ち上がる。
「叩いたら血管切れるから、入念に揉んで」
「……私、一応神様なんだけど」
げんなりした様子で呟くジンだが、やはり何処か嬉しそうにあたしの肩をほぐしている。
たまにはこんなのも良いでしょ、退屈しのぎだと思ってよ。