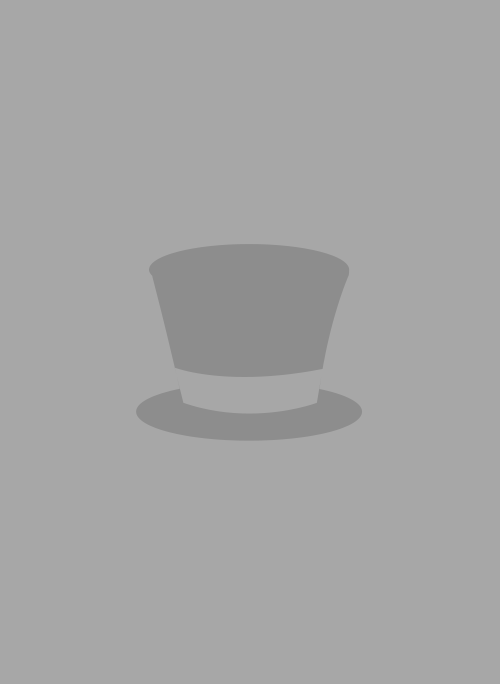どうして安心なのかわからず、最愛はじっと古霜先生を見る。
「少なくとも、名波が好きになる男は今はいないということなら、俺にチャンスはあるってことだろ?」
「ありません」
そんなチャンスはどこにもないことを言っても、彼の耳には届いていない。
「チャンスを無駄にしない。今でなくても好きだと言わせる」
「そんなこと、聞きたくないです・・・・・・」
どこからそんな自信が出てくるのか、最愛には理解できなかった。古霜先生を嫌う人がいないから、いつか心を奪えると言いたいのかもしれない。
ただ単に生徒をからかっているだけ。あの頃の自分はそれだけしか考えていなかった。
「こんな手紙をもらっても・・・・・・」
翌日、図書室で一通の手紙を読んでいた。昼休み、靴を履き替えようとしたときに手紙が挟んであった。人前で読めなかったので、放課後に選んだ。差出人の名前が書いてあったが、知らない人だった。
これはラブレターで相手が待っている時間と場所が書かれていたが、行く気になれず、手紙を鞄に入れた。相手には悪いが、この手紙は後で処分することにした。
鞄のチャックを閉めたときに名前を呼ばれて振り返ると、角重苺果(かどしげいちか)がスライド式のドアを開けた。この先生は美人で男子に人気の先生で、誰もが注目する。
「本を借りに来たの?」
「いいえ、先生は返しに?」
角重先生は本を左手で持って、右手でドアを閉めながら頷いてから、図書委員に本を渡してから、最愛の向かいの席に座った。
「誰かを待っているの?」
「いえ、誰も待っていません」
「少なくとも、名波が好きになる男は今はいないということなら、俺にチャンスはあるってことだろ?」
「ありません」
そんなチャンスはどこにもないことを言っても、彼の耳には届いていない。
「チャンスを無駄にしない。今でなくても好きだと言わせる」
「そんなこと、聞きたくないです・・・・・・」
どこからそんな自信が出てくるのか、最愛には理解できなかった。古霜先生を嫌う人がいないから、いつか心を奪えると言いたいのかもしれない。
ただ単に生徒をからかっているだけ。あの頃の自分はそれだけしか考えていなかった。
「こんな手紙をもらっても・・・・・・」
翌日、図書室で一通の手紙を読んでいた。昼休み、靴を履き替えようとしたときに手紙が挟んであった。人前で読めなかったので、放課後に選んだ。差出人の名前が書いてあったが、知らない人だった。
これはラブレターで相手が待っている時間と場所が書かれていたが、行く気になれず、手紙を鞄に入れた。相手には悪いが、この手紙は後で処分することにした。
鞄のチャックを閉めたときに名前を呼ばれて振り返ると、角重苺果(かどしげいちか)がスライド式のドアを開けた。この先生は美人で男子に人気の先生で、誰もが注目する。
「本を借りに来たの?」
「いいえ、先生は返しに?」
角重先生は本を左手で持って、右手でドアを閉めながら頷いてから、図書委員に本を渡してから、最愛の向かいの席に座った。
「誰かを待っているの?」
「いえ、誰も待っていません」