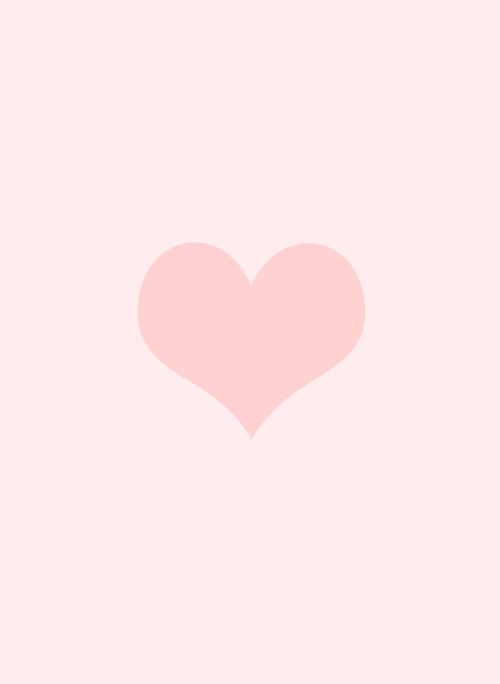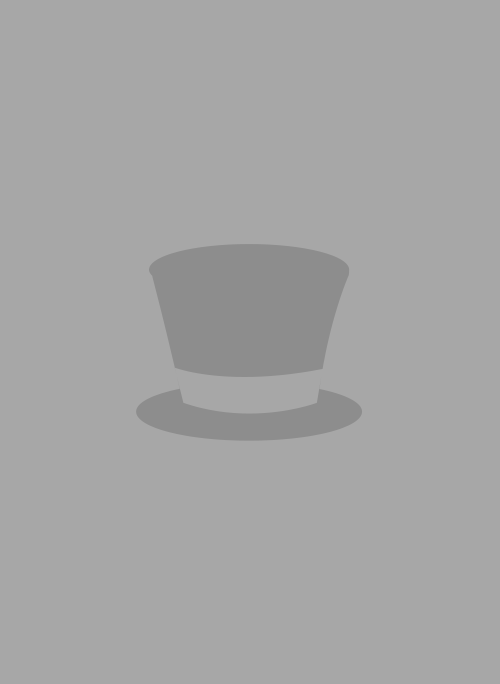国道で見た札所九番の案内板。
『先にあっちに行く?』
と優香は言った。
『いや、やはり順番通りがいいな』
僕はそう言った。
そう言った手前、六番から先に回るのが本筋だ。
そう思いながらも七番への巡礼道を進んでいた。
実は六番札所の卜雲寺は七番の先にある。
其処から八番へと行けるのだ。
それはさっきの交差点にあった、右六番と八番左七番の案内板が証明していた。
もし先に七番へと行かなかったら、同じ道を逆戻りすることになる。
だから此処だけは逆さに回ることにしたのだった。
「おん、まか、きゃろにきゃ、そわか」
七番法長寺の御真言を唱える。
境内に黒光りした牛の像があった。
違う色の像もあった。
村民が牛伏堂と名付けて建立したのだそうだ。
だからこの牛の像が此処にあるのはもっともだったのだ。
元々の牛伏堂があったは生川入口の丁字路を少し進んだ場所だったようだ。
天明二年の火災の後で法長寺へと移されたそうだ。
全ての御参りを済ませて納経所へ行き御朱印をいただいた。
其処のお寺は駐車場もトイレも立派だった。
僕は輪袈裟を外して此処に寄った。
トイレなどの不浄の場所では外すしきたりになっているのだ。
此処だけではない。
実は本堂は秩父三十四番札所の中でも最大なのだそうだ。
そしてその寺を設計したのが、あのエレキテルや土用の丑の日のキャッチコピーで有名な平賀源内だと言うことだ。
「あれっ、バイクなくなったね」
優香が何気なく言った。
次は坂を上った場所にある六番卜雲寺だ。
「おん、あろりきゃ、そわか」
これは聖観音様のご真言だった。
秩父札所では、この観音様を安直しているお寺が多いようだ。
此処へと登った階段の脇にガマズミの木があった。
初夏に白い花を付けて、秋には真っ赤な実になると言う。
それはお寺の象徴として新聞にも載ったようで、納経所の方がその記事を指差してくれた。
そのガマズミの木の向こうには秩父の象徴、武甲山が聳え立っていた。
僕達はベンチで少しだけ休ませてもらうことにした。
八番札所西善寺への道を案内板を頼りに進む。
権現橋を渡り暫く行くと国道の橋架下に出た。
其処を潜り抜け、突き当たりを左に行く。
次の交差点に案内板があった。
その先にあったのは、西武秩父線の橋架だった。
『先にあっちに行く?』
と優香は言った。
『いや、やはり順番通りがいいな』
僕はそう言った。
そう言った手前、六番から先に回るのが本筋だ。
そう思いながらも七番への巡礼道を進んでいた。
実は六番札所の卜雲寺は七番の先にある。
其処から八番へと行けるのだ。
それはさっきの交差点にあった、右六番と八番左七番の案内板が証明していた。
もし先に七番へと行かなかったら、同じ道を逆戻りすることになる。
だから此処だけは逆さに回ることにしたのだった。
「おん、まか、きゃろにきゃ、そわか」
七番法長寺の御真言を唱える。
境内に黒光りした牛の像があった。
違う色の像もあった。
村民が牛伏堂と名付けて建立したのだそうだ。
だからこの牛の像が此処にあるのはもっともだったのだ。
元々の牛伏堂があったは生川入口の丁字路を少し進んだ場所だったようだ。
天明二年の火災の後で法長寺へと移されたそうだ。
全ての御参りを済ませて納経所へ行き御朱印をいただいた。
其処のお寺は駐車場もトイレも立派だった。
僕は輪袈裟を外して此処に寄った。
トイレなどの不浄の場所では外すしきたりになっているのだ。
此処だけではない。
実は本堂は秩父三十四番札所の中でも最大なのだそうだ。
そしてその寺を設計したのが、あのエレキテルや土用の丑の日のキャッチコピーで有名な平賀源内だと言うことだ。
「あれっ、バイクなくなったね」
優香が何気なく言った。
次は坂を上った場所にある六番卜雲寺だ。
「おん、あろりきゃ、そわか」
これは聖観音様のご真言だった。
秩父札所では、この観音様を安直しているお寺が多いようだ。
此処へと登った階段の脇にガマズミの木があった。
初夏に白い花を付けて、秋には真っ赤な実になると言う。
それはお寺の象徴として新聞にも載ったようで、納経所の方がその記事を指差してくれた。
そのガマズミの木の向こうには秩父の象徴、武甲山が聳え立っていた。
僕達はベンチで少しだけ休ませてもらうことにした。
八番札所西善寺への道を案内板を頼りに進む。
権現橋を渡り暫く行くと国道の橋架下に出た。
其処を潜り抜け、突き当たりを左に行く。
次の交差点に案内板があった。
その先にあったのは、西武秩父線の橋架だった。