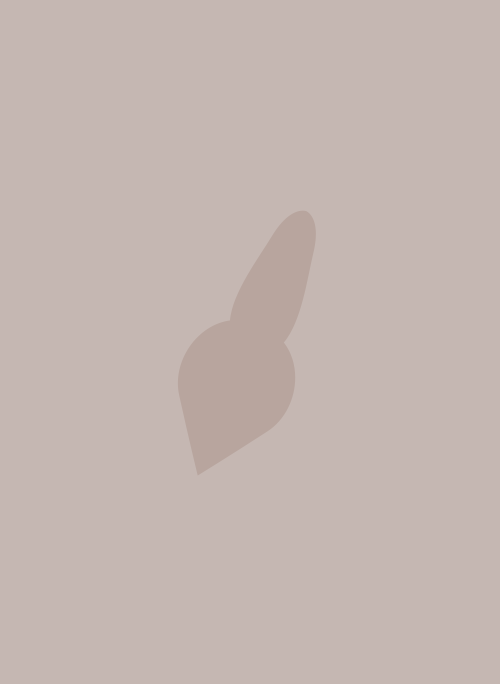熊に食われている途中だった。
右足が無い。太股の付け根から、血で濡れた骨がつきでている。
九島策郎は、あっさりと死を覚悟した。
二十五年間の人生で、自分は数えきれないほどの人間を殺してきた。これくらいの罰は当然なのかもしれない。
策郎自身は、いままで行ってきた殺人に対して罪の意識は無い。女子供といった弱い者を殺すのはださいが自分が殺ってきた相手は、どいつもこいつも、化け物みたいな強者ばかりだった。
彼等に真剣勝負を挑み、そして殺したのだ。
格好いい。
だから、罪の意識は無い。
目だけを動かして、周囲の風景を見渡した。
森の中だ。地面はぬかるんでいて、所々に水溜まりができている。さっきまで雨が降っていたのだ。草に着いた露が日の光を反射して輝いている。
空はうっとうしいくらい晴れていた。残り滓のような小さな雲が、青一面の中にうっすらと漂っている。
唸り声が聞こえたので、熊に視線を戻した。熊は血の染みた口で、策郎の足を乱暴に噛みつぶしている。
クマ公、うまいか?
頭の中でつぶやきながら、小さく笑った。だいぶ血が抜けてきたのか、意識がぼんやりとしてくる。
ああ、おれの人生、これで終わりか。
そう考えてから、ふと眉をひそめた。