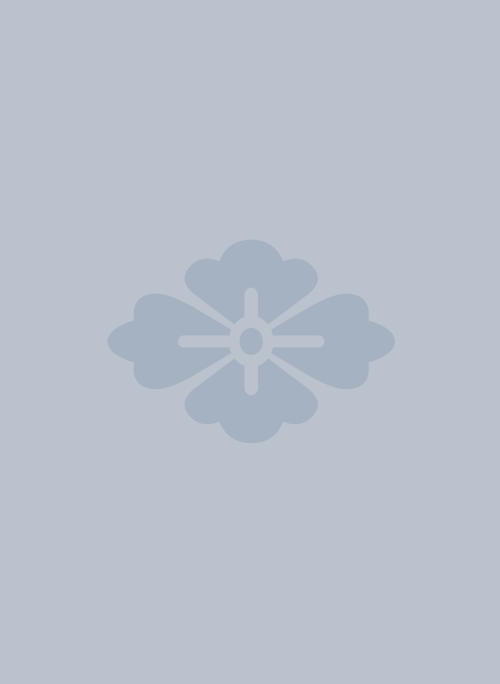俺はゆっくりと右腕の包帯を取ると、幼い頃から見慣れた、黒の刻印が露わになる。
一族から引き継がれる、契約の印。
男の、従者であるという印。
自分に自由がないという、呪いの印。
忌々しいとは感じなかった。
平気だ、見慣れてる。
自由なんて、生まれて一度も感じたことはない。
感じたことがない感覚を求めるほど、自分は子供ではない。
自分には、主である誰かに仕えるというのが、日常なんだから。
普通。
そう、普通なんだ。
だから、この刻印は、
変わることのない、永遠の印なんだ。
「……素晴らしいよ。美しい…」
そう、思ってたんだ。
「……っ」
「諸伏。いいかい?君は一生俺の所有物だ。誰にも渡さない…俺だけが、君を操り、狂わせる」
この男に出会うまでは…。
「ふふ…気に障っちゃった?
その歳で眉間に皺なんて寄せちゃ、可哀想だよ」
吉田の手が、自分の右手首を捉える。
一瞬にして引っ張られると、欄干の柱に、背をしたたかに打ち付けられた。
「大事にしなきゃ…。
君を傷つける奴はたとえ誰であっても、俺は許さないよ」
顎が掴まれる。
強引に引き上げられれば、吉田の不気味なまでに整った顔が目の前にあった。
「相手が、君自身であったとしてもね…」