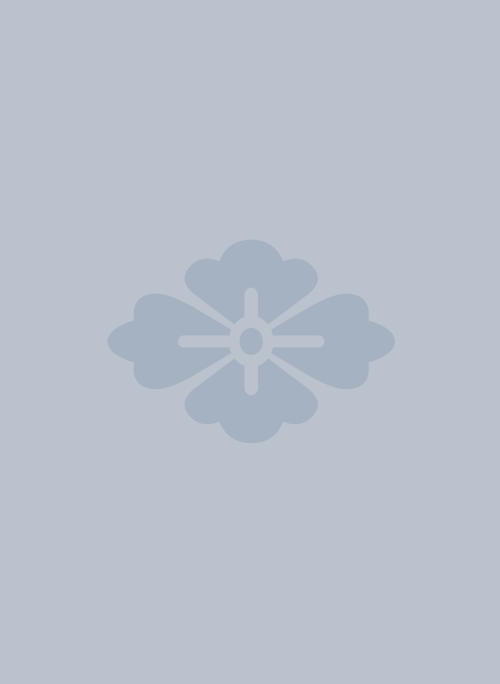一人になりたかった。
今だけは、何も聞きたくない、感じたくない、話したくない、関わりたくない……
そう思っている筈なのに、俺は気が付けば、蘭丸が眠る一室へと足を向けていた。
部屋の前まで来たところで、俺は人知れず自嘲する。
一人になりたいと、沖田先生に無礼な態度をとってまで、あの場を離れたというのに……。
独りきりになるのが嫌で、俺は無意識に蘭丸を求めていた。
俺と蘭丸……二人いて当たり前。
そんな言葉はとっくに色褪せてしまっている。
部屋に入ると、蘭丸は一人眠っていた。
数日前までは額に脂汗を滲ませて、苦しそうに呼吸をしていたが、今はだいぶ落ち着いているらしい。
もっとも、目を覚ますまで油断はできないが。
「……蘭丸」
こうして耳元で蘭丸の名を囁くのも、もう何度目になるかわからない。
片目に痛々しく巻かれた包帯を見る度、何度無力な自分を呪ったかわからない。
俺が強ければなんて、空想や空虚な仮定を立てたところで、どうにもできないと知っているのに。
「……蘭丸」
それでも、俺が一番望んでいるのは……蘭丸が目を覚ますこと。
それだけなんだ。