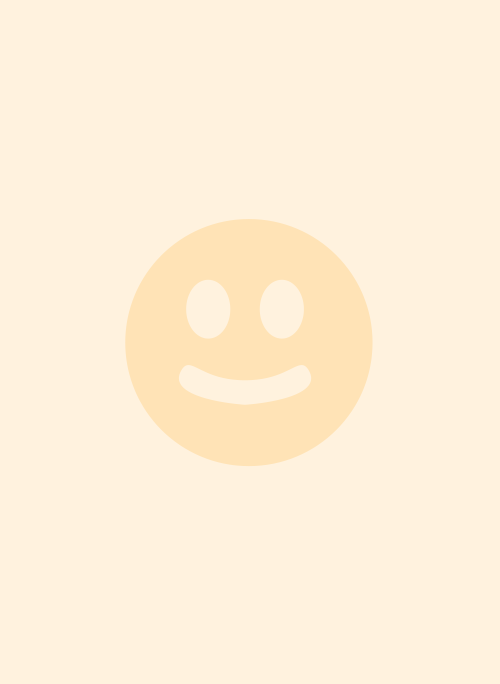すると暫くの間をあけて、正輝の低い声が聞こえた。
「・・・いや、何でも」
何なんだよ、気になるけど追求するのも面倒臭いしな。
うなじの辺りを正輝の指が触れる。私はぼーっとしながらその感触を楽しんでいた。
「・・・はあ~・・・・気持ちいい・・・」
つい、声が漏れる。
大事にされてるペットってのは毎日こんなことされてんだろうか・・・。ならもうこのさい、ペットでもいいっす。そんくらい気持ちよかった。
「・・・終わり」
ドライヤーのスイッチを切って、正輝がぼそっと言った。
私はうーんとそのままで伸びをして、御礼を言う。
「ありがと。本当に上手かった、びっくりー」
振り返ると、微妙な表情の正輝が私を見ていた。
「うん?」
「・・・・いや、何でも」
また同じ返答をして、目を逸らし、ドライヤーをなおしに立ち上がった。
何だ、あいつ。言いたいことがあるなら言えっつーの。私はソファーの上で、気持ち悪さに膨れる。
手持ち無沙汰になったから、テーブルの支度でもしようと動き出したら、ちょうどインターフォンが来客を告げた。
この豪雨の中、立派にピザ屋がご飯を運んできてくれたのだ。素晴らしい。