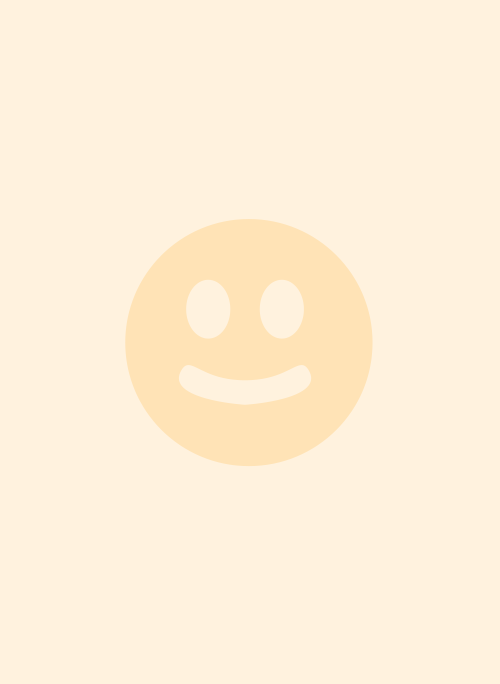「俺、彼女にはふられたばかりなんです。でもそれはいいんだ。でなくて、友達と、ちょっとね」
ビールを飲み干したらしい音。お代わりはとはマスターからは聞かない。正輝はボーっとしているようだった。
「そのお友達は女性ですか?」
マスターが正輝に聞いた。珍しい。バーテンダーが自分から突っ込んだ話を聞くなんて。
私がここにいるからで、マスターはちょっと面白がってるに違いない。
ちょっと!と牽制を込めて、私はマスターの黒いズボンを引っ張った。
「そうです。・・・ここで、いつも一緒に飲む女の人、判りますか?」
正輝の返答。
またマスターがチラリと私を見下ろした。私はぶんぶんと首を大きく横に振る。
「その方なら―――――――痛っ」
声に楽しそうな調子を聞き取って、私はマスターの足を鞄ではたいた。
「いた?」
正輝の声に、マスターは、いえ、何でもないです、と声を小さくした。
「えーっと・・・その方なら、先日お二人で一緒だったときから見てませんね」
なんとか誤魔化した模様だ。
「・・・・女って、難しい・・・」
正輝は挙動不審のマスターに何も思わなかったらしく、そう呟いて、立ち上がった。
「ご馳走様です。すみません、一杯で」
「いえ、またどうぞ。お待ちしております」
ありがとうございました、とマスターの声が聞こえて、見送ったらしく戻ってきた。