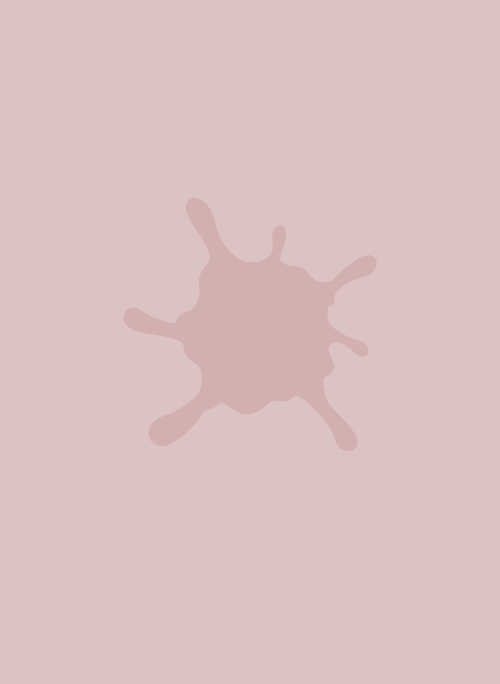プッと口を尖らす仕草も、学年一の美女には当然サマになっていた。
「ブルーフェアリーを信じてるとこ。」
「・・・ブルーフェアリー・・・・」
ブルーフェアリーとは、ピノキオの『人間になりたい』という願いを叶えた妖精の事である。
「・・・確かに・・それは・・信じておきたいような・・カンジです。」
「でしょ?!だったらウソついたら鼻が伸びるってのも『事実』って事の方が、ブルーフェアリーに近づけてるってコトじゃない?!」
小坂の理論は、いつもこうだ。
言葉にした時には既に相手が負けているのだ。
小坂は相手がどう切り替えしてくるか全て計算し尽くして、言葉を投じる。
その後誰が何を言おうと、小坂が言い負かされるコトは無い。
彼の緻密な理論の計算が狂ったコトなど、菜都の知る限りでは一度もなかった。
「はい・・確かに・・・」
菜都は毎回このように、素直に納得するしか道は残されていなかった。
「まぁ、とにかく僕は図書部の部長として、キミの次のレポートに期待するという意味だよ。校内図書新聞の〆切りも迫っているしね。」
「ブルーフェアリーを信じてるとこ。」
「・・・ブルーフェアリー・・・・」
ブルーフェアリーとは、ピノキオの『人間になりたい』という願いを叶えた妖精の事である。
「・・・確かに・・それは・・信じておきたいような・・カンジです。」
「でしょ?!だったらウソついたら鼻が伸びるってのも『事実』って事の方が、ブルーフェアリーに近づけてるってコトじゃない?!」
小坂の理論は、いつもこうだ。
言葉にした時には既に相手が負けているのだ。
小坂は相手がどう切り替えしてくるか全て計算し尽くして、言葉を投じる。
その後誰が何を言おうと、小坂が言い負かされるコトは無い。
彼の緻密な理論の計算が狂ったコトなど、菜都の知る限りでは一度もなかった。
「はい・・確かに・・・」
菜都は毎回このように、素直に納得するしか道は残されていなかった。
「まぁ、とにかく僕は図書部の部長として、キミの次のレポートに期待するという意味だよ。校内図書新聞の〆切りも迫っているしね。」