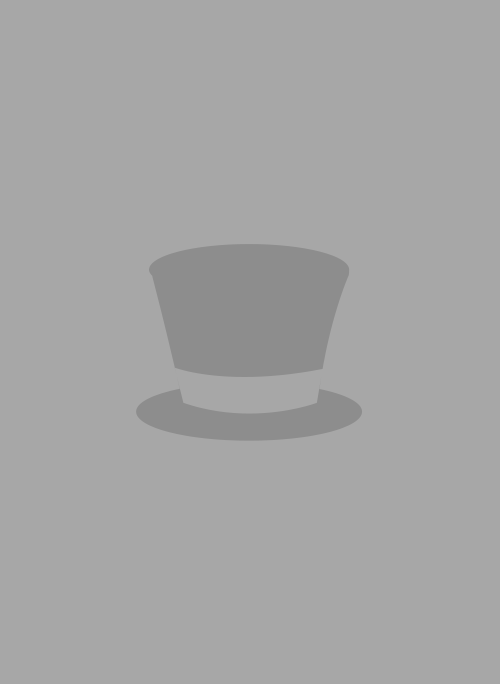「…僕のせいで…?」
「…はい。」
残酷だと分かっていながらも、これ以外に真実は存在しなかった。
「うっ…うぁ…。」
あれほど紳士的で、あれほど平気で取り繕っていた龍馬さんが、初めて涙を見せた。
「…泣いていいですよ。もう強がる必要はないんですから。」
コーヒーのついたハンカチを手渡すと、龍馬さんは何も言わずにお辞儀をすると、それを顔にあてがった。
…これで、よかったんだよね。
自分自身に言い聞かせていないと、またハンカチを濡らしてしまいそうだった。
「ピロピロピロピロ…。」
ポケットの中のケータイが、軽快な音を立てた。
「あ…ちょっとすみません。」
花屋の外に出て、私は電話に出た。
「紗姫?」
相手は、菜月くんだった。
「うん、そうだけど?」
「かなりヤバいことになってる! 早く戻ってきてくれ!」
「いきなりどうしたの? …今仕事中だし…。」
「いいから早…むぐぅっ!?」
「菜月くん!?」
呼びかけたが、すでに時遅し。不通音が左耳にこだました。
「…何かあったんですか?」
まだ目の赤い龍馬さんが、後ろからいつもの優しい声で問いかける。
「分かりません…。けど、会社の方で何かあったみたいで…。」
「…はい。」
残酷だと分かっていながらも、これ以外に真実は存在しなかった。
「うっ…うぁ…。」
あれほど紳士的で、あれほど平気で取り繕っていた龍馬さんが、初めて涙を見せた。
「…泣いていいですよ。もう強がる必要はないんですから。」
コーヒーのついたハンカチを手渡すと、龍馬さんは何も言わずにお辞儀をすると、それを顔にあてがった。
…これで、よかったんだよね。
自分自身に言い聞かせていないと、またハンカチを濡らしてしまいそうだった。
「ピロピロピロピロ…。」
ポケットの中のケータイが、軽快な音を立てた。
「あ…ちょっとすみません。」
花屋の外に出て、私は電話に出た。
「紗姫?」
相手は、菜月くんだった。
「うん、そうだけど?」
「かなりヤバいことになってる! 早く戻ってきてくれ!」
「いきなりどうしたの? …今仕事中だし…。」
「いいから早…むぐぅっ!?」
「菜月くん!?」
呼びかけたが、すでに時遅し。不通音が左耳にこだました。
「…何かあったんですか?」
まだ目の赤い龍馬さんが、後ろからいつもの優しい声で問いかける。
「分かりません…。けど、会社の方で何かあったみたいで…。」