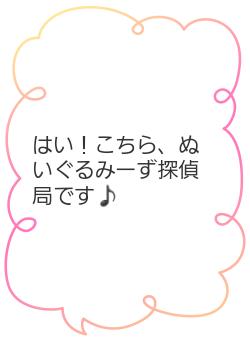「やっぱり…好きだったし。あの優しさは見せかけだったのかと。それを見抜けなかった…見せかけの彼を信じていた自分が情けなかった」
「……」
「悲しいだけじゃなくて腹立たしいやら情けないやらで泣きに泣いた」
「先輩」
「うん?」
「先輩は自分に厳しすぎる」
「涼君」
「その時の先輩って今の俺と同じ高校2年で16、7なわけでしょう。こんなこと言ったら先輩怒るかもしれないけど…まだ俺達大きく分けたら子どもの部類に入るんだし…そんな人生経験浅い俺達に人の本質見抜けなかったって恥ずかしいことじゃないです。 俺達の年で酸いも甘いも分かってたらおかしいです。騙されて悔しかった…なら泣 いたらいいんです。相手を罵ればいい んです。自分を責めることなんてこれっぽっちもありません」
「……」
先輩が俺を見つめて
「フフフ…涼君ありがとう」
「えっ?」
「そうだよね。泣いたって罵ったっていいんだよね」
「はい」
「私ね、テニス部のエースだって中学の時から言われて、家ではピアノを習いに来る子達のお姉さんで…知らず知らずのうちに『 確りしなくちゃいけない。大人にならなくちゃいけない』って自分で枷をはめてたんだと思う。そうだよね、まだ私高校生なんだよね」
「先輩」
「私が素の私『水島凛』でいられるのはもしかしたら千恵の前だけかも」
「……」
「家はまぁ、言ってみれば共稼ぎじゃない。お母さん今でこそ家で教えてるだけだけど去年までは学校で教えてたし」
「えっ?学校の先生ですか」
「うん。音楽の非常勤教師だったから。だから尚更親に甘えちゃいけないって」