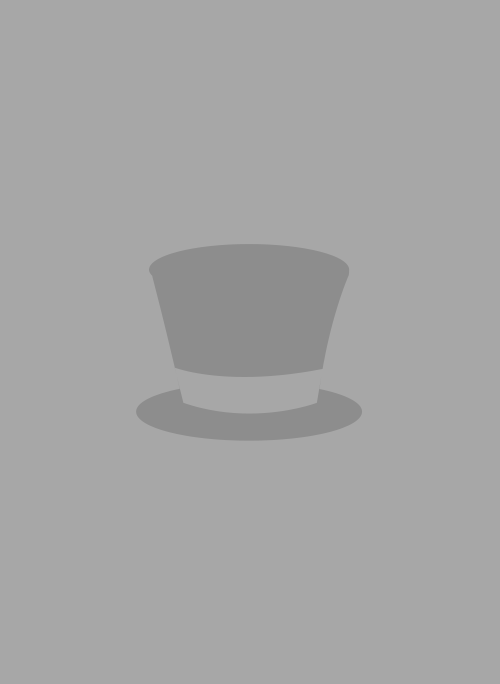「何時から?何時から好きなのー?」
「入学式にたまたま見て一目惚れですよ、僕のタイプだったんです彼女ー」
「以外ね話すの嫌がると思ったのに。」
「別に良いですよどうせ一年だっても進行もない恋ですからね」
僕がポットに紅茶を入れ。コップを戸棚から取り出す。
小さなそのコップはバラ柄のポットと同じ模様であった。
「そうそうふっきーとひざッチじゃ天と地よいや地面の下?」
「ひ、ひどい言われようですね……」
「良いわ協力してあげる!」
大声を出して勘月さんはそう言った。
僕はテーブルに用意した紅茶入りのポットをそっと置く。
「いいですよ別に叶えたくないですから……」
「ほんと?ほんとは叶えたい付き合いたい……違う?」
「そ、そりゃー付き合いたくないと言ったら嘘になりますけど……」
勘月さんは平然とした顔で紅茶をそそいだ。
「でー私も協力してほしいことがあるんだけどー」
また変な要求だろうと僕は嫌になった。
「私の恋にも協力してほしいんだけど」
勘月さんの言葉に僕は耳を疑った。勘月さんが恋?あのわがままでうざったらしい勘月さんが恋?
「勘月さんの美貌ならすぐ落とせるんじゃ……」
「それがさー彼好きな人がいる見たいで、しかも年下」
勘月さんは溜息を吐き紅茶を少し喉に入れた。
「年下?2年ですか?」
「1年……」
「1年ね……」
どうして勘月さんはこうなのかと少し馬鹿らしく思えてもきた。
「で?誰なんですか?僕の好きな相手も知ってるんですから教えてくださいよ」
「いやだー恥ずかしいもん!自分からいうなんてさー」
僕らはどうやら叶わないと思われる恋をしているらしい。
「あ、いたんじゃん勘月と日崎ー」
扉を少しあけ柳がこちらの様子をうかがっていた。
「入学式にたまたま見て一目惚れですよ、僕のタイプだったんです彼女ー」
「以外ね話すの嫌がると思ったのに。」
「別に良いですよどうせ一年だっても進行もない恋ですからね」
僕がポットに紅茶を入れ。コップを戸棚から取り出す。
小さなそのコップはバラ柄のポットと同じ模様であった。
「そうそうふっきーとひざッチじゃ天と地よいや地面の下?」
「ひ、ひどい言われようですね……」
「良いわ協力してあげる!」
大声を出して勘月さんはそう言った。
僕はテーブルに用意した紅茶入りのポットをそっと置く。
「いいですよ別に叶えたくないですから……」
「ほんと?ほんとは叶えたい付き合いたい……違う?」
「そ、そりゃー付き合いたくないと言ったら嘘になりますけど……」
勘月さんは平然とした顔で紅茶をそそいだ。
「でー私も協力してほしいことがあるんだけどー」
また変な要求だろうと僕は嫌になった。
「私の恋にも協力してほしいんだけど」
勘月さんの言葉に僕は耳を疑った。勘月さんが恋?あのわがままでうざったらしい勘月さんが恋?
「勘月さんの美貌ならすぐ落とせるんじゃ……」
「それがさー彼好きな人がいる見たいで、しかも年下」
勘月さんは溜息を吐き紅茶を少し喉に入れた。
「年下?2年ですか?」
「1年……」
「1年ね……」
どうして勘月さんはこうなのかと少し馬鹿らしく思えてもきた。
「で?誰なんですか?僕の好きな相手も知ってるんですから教えてくださいよ」
「いやだー恥ずかしいもん!自分からいうなんてさー」
僕らはどうやら叶わないと思われる恋をしているらしい。
「あ、いたんじゃん勘月と日崎ー」
扉を少しあけ柳がこちらの様子をうかがっていた。