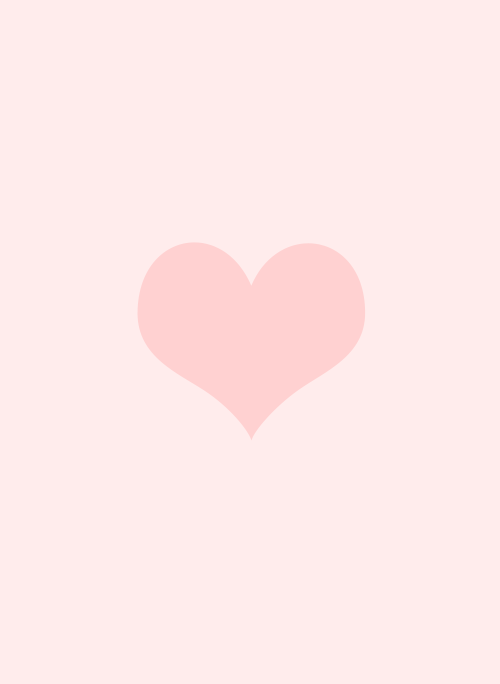そして一斗はしばらく私を歩かせ、近くに合ったビジネスホテルに連れ込んだ。
「ほら美海。水飲んで」
ベッドに寝転がったまま起き上がれない私に、一斗は甲斐甲斐しく看病してくれる。
寝ころんだままグラスを受け取り、痛む喉に水を通した。
ゴクリ、ゴクリ。
ひんやりとした冷たいものが喉に流れ込んできて気持ちがいい。
「………美海、零れてる」
私が寝ているベッドの淵に腰掛けた一斗は、そっと口の端からこぼれた水を手で掬ってくれた。
飲み切ったグラスを一斗は私から取り上げ、ベッドの横にあるサイドテーブルに置いた。
私はただ一斗をぼーっと見るだけ。
頭の中で鳴り響いていた不協和音も、今ではただ余韻のようにぼんやりとしたものへと変化を遂げた。
「……………いちとぉー」
なんで、あなたはそんなに優しいの。
「………説教は酔いが冷めてからな」
「…………いちと」
つーっと、火照っている顔に涙が伝った感覚がした。
「…………美海」
でも一斗は、涙を拭ってはくれない。
「……いちと。わたしじゃぁ……だめだったの?としした、だから……?」
ずっと聞きたかったこと。
もしも私が一斗と同じ年だったなら。
一斗は姉ではなくて私を選んでくれたのだろうか。
「………美海。俺は……」
「みぃーんな。みぃーんな。わたしじゃなくて、おねぇちゃんを選ぶんだもんねぇ。……わたし、どこが欠落してるのかなぁー……」
またポロリ、涙が零れた。
「………美海っ」
「…………………わたしには、一斗だけが希望だったのにー。一斗のばか。ばぁーっか。嫌いだもん。お母さんも、お父さんも。一斗もぉー。私ってただの……おねーちゃんのお飾りだもんねぇーだっ。どぉせ」
「美海、美海」
「私、悲劇のヒロインみたぁーい。誰からも愛されない可哀想なお姫様ぁーっ。おーじ様は、一斗くんじゃないけどー」
「もう、いいから」
「んふふ、自分で悲劇のヒロインって、私いたいなぁ。こころ、痛い」
ゆっくりと瞼を閉じる。
溢れている涙を自分で拭う事はせずに、ただぼんやりとする意識を放置した。
そのあとは、ただ無の世界へ。