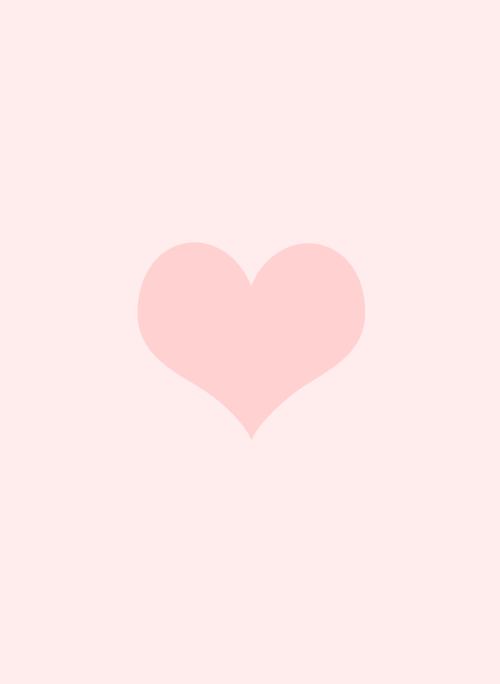その言葉に薫は気恥ずかしくなり、持っていた本をぺらぺらとめくった。
男は東屋の梁に薬玉をかけると袂から煙草とライターを取り出した。
「和服を着てるのに煙管とかは使わないんですね」
「キセルぅ? あんな使い勝手の悪いもん、持って歩けると思うのかい?」
薫は苦笑いする。
先生はこの屋敷と似ているんだな。
チラリと男の横顔を伺う。カチンっとライターの蓋を開けて手馴れたように煙草に火をつける。気持ちよさそうに紫煙を燻らす姿に、薫は煙草はそんなに旨いものなのかと疑問に思う。
以前、先生が書斎を離れた隙に煙草を一本くすねて試したことがあるが、咳き込むだけで美味しいなんて思えなかったからだ。そのことを男は知っているのかいないのか、薫を咎めるようなことはしなかった。
薫はたびたびこの屋敷に足を運んでいる。
何がきっかけだったかは定かではない。学校でも体力のないほうから数えたほうが早いくらい運動はまったく向いていなく、唯一できることといったら散歩くらいだった薫は偶然にこの屋敷を見つけた。
開け放たれた大きな窓から沢山の本を虫干ししている様子を見てたまらなくなってこの屋敷の主に声を掛けたのだ。
いや、もしかしたら声を掛けたのは男のほうだったかもしれない。 以来、薫は本を借りにたびたび通うようになったのだ。
それなのにこの男の素性は知れない。
『先生』と呼んではいるが、事実、先生なのかどうかさえもわからないし、名前も今となっては聞きづらい。何をしてそうやって生活をしてるのかさえ謎だ。
それでもここへ来てしまうのは居心地が良いせいなのかも知れない。
「薫、喉が渇いただろう? 井戸にラムネを冷やしてあるから」
丁度、喉が渇いていた薫は屋敷の傍にある井戸へ行き、つるべを上げてみると網の中にラムネが一本だけ入っていた。
男は東屋の梁に薬玉をかけると袂から煙草とライターを取り出した。
「和服を着てるのに煙管とかは使わないんですね」
「キセルぅ? あんな使い勝手の悪いもん、持って歩けると思うのかい?」
薫は苦笑いする。
先生はこの屋敷と似ているんだな。
チラリと男の横顔を伺う。カチンっとライターの蓋を開けて手馴れたように煙草に火をつける。気持ちよさそうに紫煙を燻らす姿に、薫は煙草はそんなに旨いものなのかと疑問に思う。
以前、先生が書斎を離れた隙に煙草を一本くすねて試したことがあるが、咳き込むだけで美味しいなんて思えなかったからだ。そのことを男は知っているのかいないのか、薫を咎めるようなことはしなかった。
薫はたびたびこの屋敷に足を運んでいる。
何がきっかけだったかは定かではない。学校でも体力のないほうから数えたほうが早いくらい運動はまったく向いていなく、唯一できることといったら散歩くらいだった薫は偶然にこの屋敷を見つけた。
開け放たれた大きな窓から沢山の本を虫干ししている様子を見てたまらなくなってこの屋敷の主に声を掛けたのだ。
いや、もしかしたら声を掛けたのは男のほうだったかもしれない。 以来、薫は本を借りにたびたび通うようになったのだ。
それなのにこの男の素性は知れない。
『先生』と呼んではいるが、事実、先生なのかどうかさえもわからないし、名前も今となっては聞きづらい。何をしてそうやって生活をしてるのかさえ謎だ。
それでもここへ来てしまうのは居心地が良いせいなのかも知れない。
「薫、喉が渇いただろう? 井戸にラムネを冷やしてあるから」
丁度、喉が渇いていた薫は屋敷の傍にある井戸へ行き、つるべを上げてみると網の中にラムネが一本だけ入っていた。