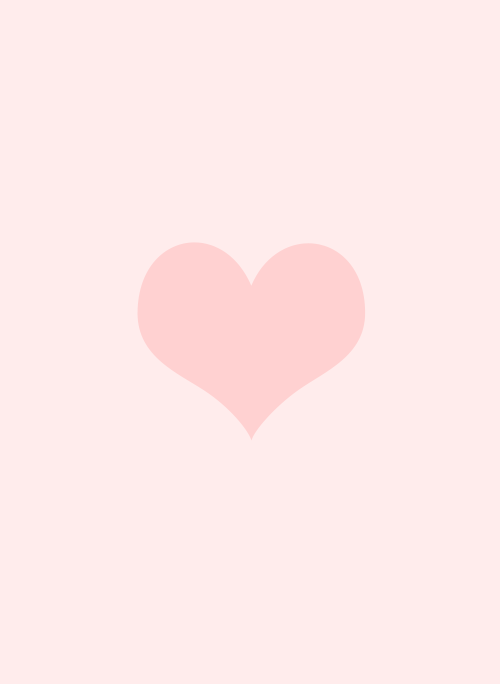泣いても、あいつは戻らない。
わかっていながらも、涙を止めることができない。
さっきまでいたのに、さっきまで触れられる距離にいたのに、いきなり消えてしまうなんて、いくらなんでも唐突過ぎだ。
そうやって、棗はなんでもかんでも俺たちを置いて、先に行ってしまう。
寂しいし、悲しいし、つらいし、ひどい。
喉がしまるような感覚はしばらく続きそうだ。
狼嵐も、綾も紘も、分家の奴らも、棗というかけがえのない奴が消えたことに、ただ涙を流した。
心葉side end
わかっていながらも、涙を止めることができない。
さっきまでいたのに、さっきまで触れられる距離にいたのに、いきなり消えてしまうなんて、いくらなんでも唐突過ぎだ。
そうやって、棗はなんでもかんでも俺たちを置いて、先に行ってしまう。
寂しいし、悲しいし、つらいし、ひどい。
喉がしまるような感覚はしばらく続きそうだ。
狼嵐も、綾も紘も、分家の奴らも、棗というかけがえのない奴が消えたことに、ただ涙を流した。
心葉side end