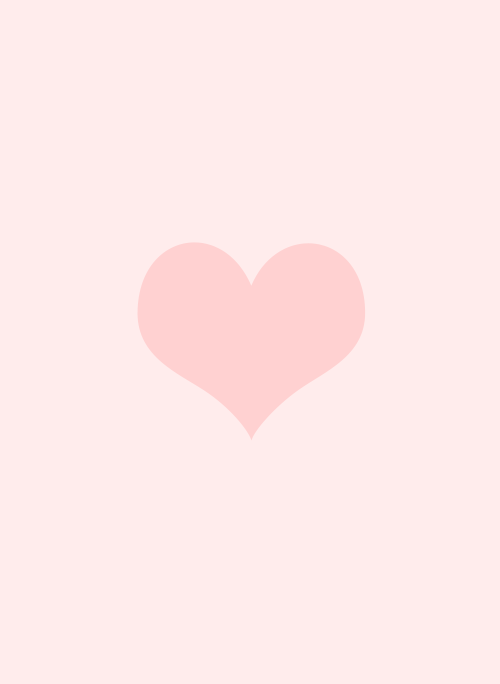「沖田さんお茶をお持ちしました」
「入っていいよ」
気怠げなでもどこか嬉しさを含んだような声に微笑みを浮かべて彼の部屋に入った。
「気分はどうですか?」
「全然大丈夫だよ。なのに君も土方さんも心配しすぎ」
はぁ…とわざとらしくため息をついて沖田さんはお茶を啜った。小さな子どものようにすねた様子の沖田さんが可愛く見えてくすりと笑うと何笑ってるの、と釘をさされてしまった。
「ふふっ…心配されてあげてください。それだけ私も土方さんも沖田さんのこと大切に思ってるってことですよ」
「ふーん…土方さんはともかく君に心配されるってことならいいかもね」
「もう…またそんなこと…」
「…ねぇ、助けてくれたんだよね、君が」
「…覚えてたんですか?その時のこと」
「少しだけね」
沖田さんを助けた時のことを思い出すと正直恥ずかしい。意識が朦朧としていたはずだから覚えていないと思って自然に接するようにしていたのに。そんな私の考えは儚く散ってしまった。
覗き見るように沖田さんをちらりと見れば今まで見てきた彼の表情の中でも見たこともないくらい真剣な顔をしていて、目には熱っぽさが見られた。
「ありがとう」
「いえ、そんな…」
じっと見つめられてそれ以上は何も言えなくなってしまう。
「君は怪我しなかった?」
「えっと…腕を少し、でももう塞がりましたし大丈夫です」
「見せて」
「は、はい…」
袖をまくって沖田さんの近くによると少しきつめに巻かれていたさらしを解かれて傷跡が見えた。
四寸くらいのそれは先ほど言った通りもう塞がっているが跡として残るだろう。それでも別に私はかまわなかった。それで沖田さんを守れたというのなら傷跡なんてかまわない。もう痛みもないし不便を感じることもないのだからそれでいいのだ。
それでも沖田さんはその傷をゆっくりとなぞっては切なげな表情を浮かべた。