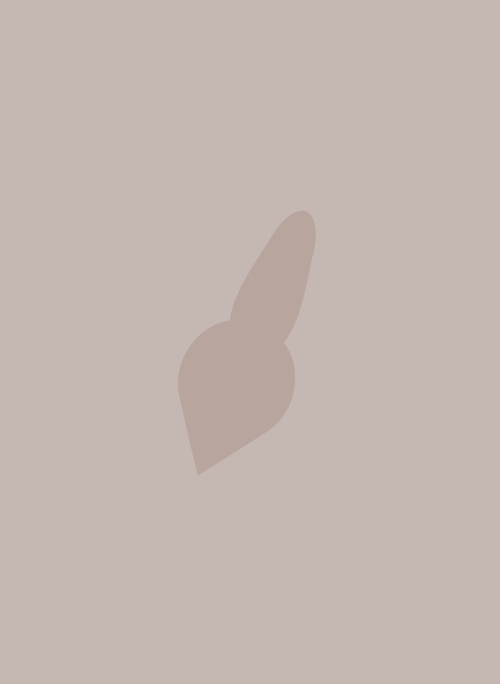「ん…」
私の瞳に最初に映ったのは煌煌と光る電気だった。
不思議な匂いが私の鼻をつく。
私はまだ痛む後頭部を抑えながら上半身を起す。
視界がぐらぐらとゆれる。
どのくらい意識を失っていたのだろうか。
視界のゆれがなくなったことを自分自身で確認してから立ち上がる。
あたりは静まり返っていた。
まるで私しかいないみたいだった。
そう思うと急に不安になりおねえちゃんの部屋に向かってみた。
ギシギシと軋む階段を駆け上がる。
今だけはこの長い階段を憎らしく思えた。
「おねえちゃん!!!!!」
私はおねえちゃんの部屋の扉を勢いよく開けた。
窓から差し込む月の光で部屋の中がほんの少しだけ見えた。
返答は、無かった。
でも誰か居る。
勘、なんかじゃなく本当に居るのだ。
明らかな証拠が二つ。
人影があること
息をする音が聞こえること
「おねえちゃん…?」
相変わらず返答は無い。
ただ息のする音が聞こえる。
私は人影に近寄り、影の主がどこに居るのか手探りで確かめてみる。
ふと、なにかに触れた。
おそらく人の体だった。
「…誰…?」
つぶやく。
しかし返答は無い。
私は人から離れ、電気のスイッチを探す。
それらしきものを探り当て、スイッチを入れた。
それらしきものは本当に電気のスイッチだったようで電気がつく。
そこに居たのはおねえちゃんだった。
頬には赤いナニカがついていた。
私は人がおねえちゃんだとわかると駆け寄り抱きしめる。
「おねえちゃん…!!!」
「…」
おねえちゃんから言葉は返ってこない。