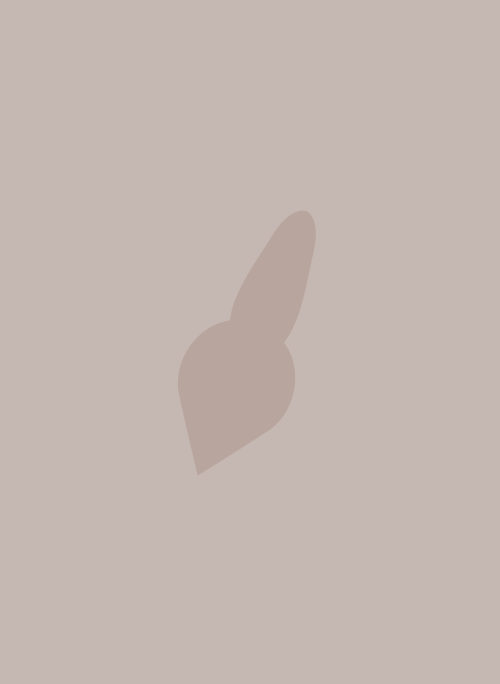あの日の朝、熊は雌熊のうめき声で目をさました。
起きあがって雌熊を見ると、様子がおかしかった。ぐったりと横たわったまま、ぼんやりと洞穴の天井を見つめているのだ。その目には生気がなかった。
死にかけている、とすぐにわかった。飢えがとうとう極限に達したのだ。
火事の日以来、二匹共ろくに食事をとっていなかった。冬ごもり前のこの時期に、この状況は危険だった。
熊は毎日必死で獲物を探した。森を出て、人里から食べ物を盗み、人間に撃ち殺されかけた。そこまでしてでも、得られた食べものはわずかだった。
「しっかりしろ。すぐに何か食べものを持ってきてやるからな」
そう叫んで、熊は洞穴を飛びだした。しかし、どこへ向かえばいいのかわからなかった。早く何か食わせないと、雌熊の命が危ない。でも、食べものを手に入れる方法が見つからない。
迷ったすえに、狩人の家へむかうことにした。狩人に相談して、何かよい助言をもらえないかと思ったのだ。考えることに関しては、自分よりも、人間のほうがすぐれているだろうから。わらにもすがる気持ちだった。不安で泣きそうになるのをこらえながら、熊は川沿いを駆けおりた。
狩人の家に着くと、熊は前足で窓を軽くたたいた。しばらくしてから、窓がひらいて狩人の妹が顔を出した。その顔はなぜか少し青ざめていた。妹はゆっくりと頭をさげた。
「おはようございます。兄に御用ですか?」
「ああ」
「すみません。兄はいま出かけているのです」
「そうなのか」
熊はため息をついてうなだれた。悩みつかれて頭が痛い。自分も飢えが極限まで達しているのだ。ここに来ただけでも、ものすごく疲労している。空腹による胃痛がひどくなって小さくうめいた。
ふと妹を見おろした。
今年で十五歳になる彼女の全身は、女らしくふっくらと成長していた。
うまそうだな、と思った。
そして考えた。人間は雑食の生きもので、いろんなものを食うらしい。だから人間の体には、さまざまな栄養がつまっているそうだ。もしかしたら、これを食わせれば、雌熊は回復するかもしれない。
熊の中で何かが切れた。
前足で妹の頭を殴った。頭蓋骨が砕けた。首の骨が折れた。窓に頭をつっこんで、死体を口にくわえた。血の味が舌の上に広がった。思う存分租借して、呑みこみたくなる衝動を必死でおさえた。
すぐにその場から去った。これで雌熊を助けられるかも、と期待しながら、川沿いを歩いた。
そして、そこで雌熊の死体をひきずる狩人に会った。