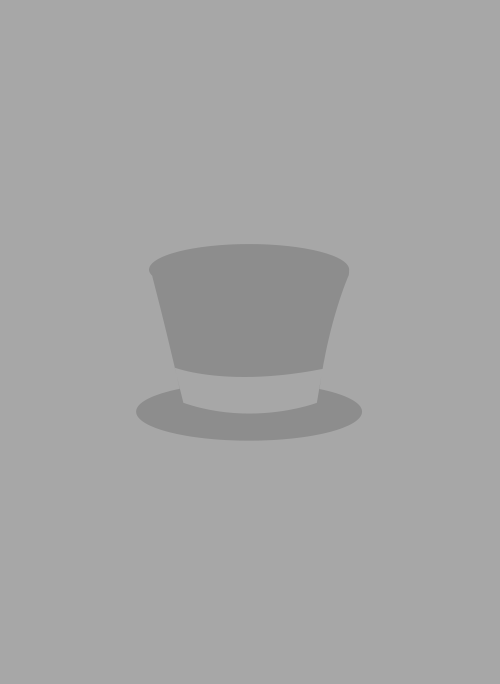そんな態度を取られたら、いくらひなでも分かってしまう。
梓がいつも言っていた『転けちゃった』は嘘なのだと。
それでも、
「まだよく転ける…とか?」
そうひなが訊くのは梓の嘘を信じたく無かったからだ。
でも亮介は、うん。とは言わずに眉尻を下げる。
「ちげーよ。あの傷や痣は、……親父さんに殴られて出来たもんなんだよ」
「えっ、……梓のお父さん…に?」
「そう。DVってやつだよ」
転けたというのが嘘なら誰かに殴られたというのは安易に想像出来た。
それでも、それが実の父親からという事は思いもしなかった。
ひなはそんな事を思い付かない様な家庭で育ってきたから余計だ。
「……りょ……すけは…、いつから知ってたの?」
「小6の時に、親父さんに殴られてる現場を目撃して…からだな」
「……………そう」
ひなが震える声で紡ぐ事が出来るのはそれだけ。
そっとひなの肩に亮介の手が乗る。
そしてぽんぽんと優しく何度も叩いてくれるのは、ひなの心情を気遣ってだ。
少しすると、ひなは震える唇を一度グッと噛み締めた後、ポツリポツリといっぱいいっぱいな気持ちが溢れ出た。
「私、……梓の事親友とか言ってた癖に。……何も知らなかった」
「知られない様にしてたのは梓だよ」
「でも!」
「ほら、時間無いから次行くぞ!」
ひなにそれ以上は言わせないと言わんばかりに、ひなの手をギュッと強く握って歩き出した亮介。
そんな亮介にもう何かを言える筈がなく、梓への思いをグッと呑み込んで、
「…………うん」
と返事をする。