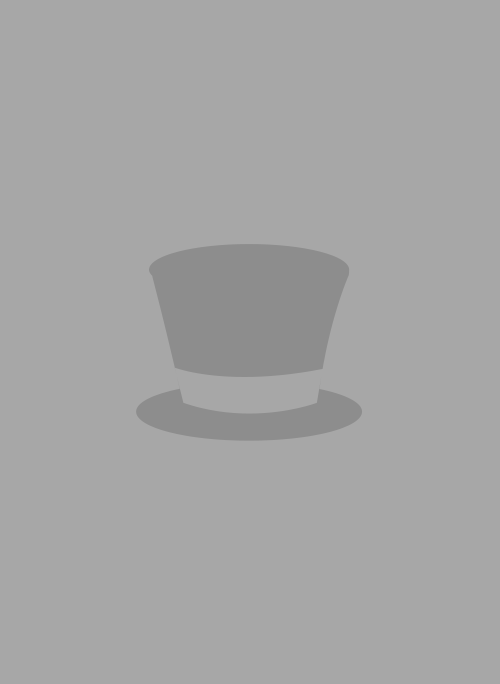「そっ。私ね、このせいで幸せ一杯っていう顔してるやつが大嫌いになったんだよね。特に、私の家族は仲が良いの!なんて言うやつに虫ずが走る」
「梓……」
亮介がポツリと梓の名前を口にしていたが、ひなの頭の中はそれどころではない。
梓の言葉が頭から離れない。
「だからね、蔑む目も大嫌い。じゃあね、亮介」
フッと鼻で笑って去っていく梓からひなは目が離せない。
もう、動くことすら出来ない。
梓の姿が全く見えなくなった時、ようやくひなが恐る恐る口を開いた。
「亮介。梓のあの左腕って……。この事って……、何?」
その質問に亮介が少し驚いた顔をする。
「ひなは気付いてなかったのか?」
気付いているだろうと思われていたその口調に、思わず肩が揺れる。
「な、…何に?」
普通なら気付く様な事。
それに私は、……気付いてない?
そんな不安に苛まれて亮介を見つめるひなに、亮介があー、あのさ…と言いにくそうにしながら話し出した。
「小学校の時から、梓はよく怪我や痣が出来てたの覚えてねぇか?」
確かに梓は腕や足に怪我や痣が多かった。
でも、それは……。
「あれは、梓がよく転けるからって……」
ケラケラ笑いながら梓が、また転けちゃった。といつも言っていたのを覚えている。
「信じてたのか?」
「そりゃ、信じるよ!」
「そっか」
ひなの答えを聞いて、視線をひなから背けた亮介。
その仕草が余りにも不自然で、ひなの背中に冷たいものが伝う。