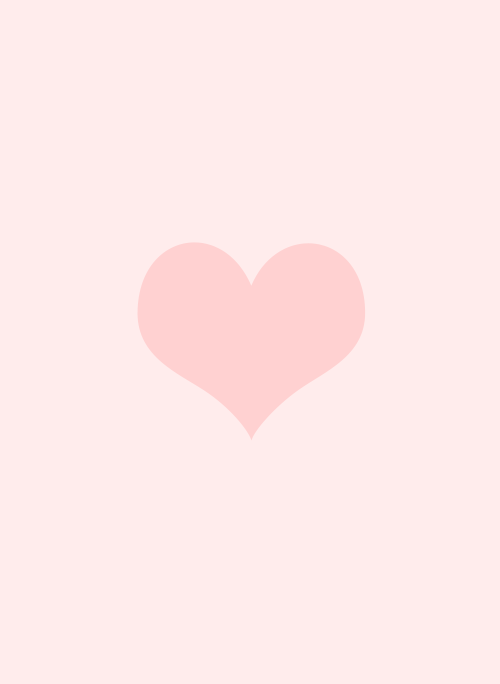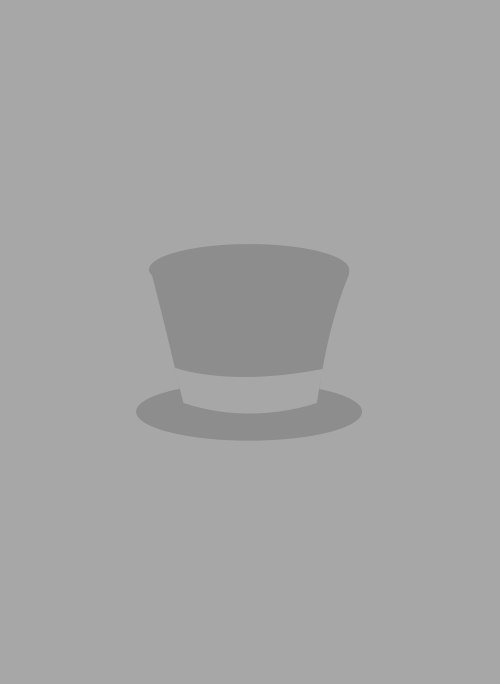「ハァハァ…捕まえた。」
と青年の手をとって起こそうとした。直哉はちょっとした違和感を感じた。
すると
「離せや。」
と振りほどかれた。そしてまた逃げようとした。直哉は、それを阻止しようとうでを掴んだ。
「何故、逃げるんだ?」
「離せ。離しって言いゆうやろうがっ!」
青年は、興奮状態だった。揉み合っていると直哉の指がネックレスに引っ掛かり切れてしまった。直哉が、ネックレスに気を取られた空きに腕からすり抜けネックレスを拾って逃げて行った。
直哉が、肩を落とし一ノ瀬のところへ戻ろうとしたときふと道端に目を向けた。そこには青年が落とした財布があった。急いで拾い上げ中を確認した。直哉は、自分の感じた違和感の正体を認識した。
財布を持ち一ノ瀬のもとに戻った。一ノ瀬は、車のところにはいなかった。正面のワイパーにメモが置かれていた。
“うえはら美容整形クリニックの斜め向かいのファミリーレストランにいます。”
直哉が、向かうと上原と一ノ瀬が向かい合わせで話合っていた。一ノ瀬が、直哉に気づき手を挙げて知らせた。話は佳境へ入っていた。
「こちら付き添いの水柿です。話を戻しましょう。蘇芳茜という女性についての情報を少しでいいんです。教えて頂けませんか?」
「だからさっきから言っているように個人情報をお教えすることは出来ません。」
双方の話は、平行線をたどっていた。直哉は、ふと上原の指先に目線を向けた。右手の人差し指の付け根にたこがあった。左手をみてみると親指以外の指先に皮膚が厚くなったあとがあった。
直哉が、ふと言葉を発した。
「バイオリン、習われていたんですか?」
「え?」
「いえ、両手両指のたこです。右手の付け根にあるたこ。なかなかそんな所にタコは出来ませんから。まあ、ペンダコという可能性もありますがなら左手の指先の皮膚の厚み。これが説明がつかない。だからバイオリンかなと。」
「よく分かったわね。確かにバイオリン習ってた。幼少期から高校までね。私は、バイオリニストになりたかったんだけと親がね。一生食べていける保証は無いんだから諦めなさいって。まあね、言い返せ無かった私も悪いのよ。でも後悔だけが残っちゃった。」
上原は、遠くを見つめながら言った。直哉は、
「まだ、蘇芳茜さんは23歳なんです。まだ叶えられるだろう夢や希望がたくさんあるんです。そんな彼女が今、忽然と失踪してしまってるんです。あなたは何とも思わないんですか?」
とまくし立てた。すると上原の様子に変化が現れ始めた。忙しなく脚を組み換えたり、手を組んだり離したりした。
「でも個人情報流出なんてことになったら…」
「二度目の裁判が怖いですか?」
一ノ瀬が横から一言そえた。直哉は、話を続けた。
「僕たちは、決して情報を流出させたりしません。じゃあ、僕は高校生なので高校の生徒手帳のコピーをあなたに渡してもいい。」
そういって直哉が席を立とうとすると上原が止めた。
「分かった。そこまでしなくていいわ。…あなたは信じても良さそうだから。」
上原は、立ち上がり
「付いてきて。」
と歩きだした。
3人は、クリニックへ入って行った。看護師たちは全員帰ってしまい中は真っ暗だった。上原は、どんどん奥へ入って行く。やがて院長室に着いた。明かりを点け
「座って待っていて下さい。カルテ等を持ってきます。」
上原は、院長室を出て行った。
間もなくして上原は帰ってきた。カルテともうひとつ書類を持ってきた。
「これで全部です。コピーをしました。だからもう帰って下さい。」
「確認させて頂きます。」
中を見ると“蘇芳茜”の文字があった。読み進めると住所が書いてあった。だが鳩羽から聞いていたあの部屋の住所のものではなかった。
「ありがとうございます。決して口外致しません。約束します。」
直哉は、上原に頭を下げた。一ノ瀬も一緒に頭をさげた。
上原と別れたあと直哉たちは、車に乗り家路を急いだ。時間が10時半を回っていた。
一ノ瀬は、直哉を家に送ると言った。直哉は、断ったが親御さんに謝るからと聞かなかった。
直哉の家に着いた。チャイムを鳴らすと中から母が飛んで出てきた。
「直くん…心配したんだから。」
母は、脚の力が抜けたようにその場にしゃがみこんだ。母親は泣いていた。あの大喧嘩以来の涙だった。直哉は、少し以外に感じていた。母から“心配”の二文字がでるとは思っていなかった。自分に興味なんてないと思っていたから。
「…ごめん。連絡しなくて。」
「申し訳ありませんでした。私の管理が至りませんでした。反省致します。」
一ノ瀬も頭を下げた。
「…あの、どちら様ですか?」
母は濡れた目で一ノ瀬を見た。
「申し訳ありません。紹介が遅れました。私、直哉さんの高校で保健室の校医をしています。一ノ瀬真赭と申します。直哉さんは高校の文化祭委員に参加していまして。遅くまで私の手伝いをしてくれていて。私もその好意に甘えてしまって。親御さんにはお話が言っているとばかり…。本当に申し訳ありません。」
一ノ瀬の迫力に押される形で母親は納得した。これからは、遅くても10時までには帰って来ることと約束した。
一ノ瀬は、最後に深々と頭を下げ去って行った。一ノ瀬のお陰で余り咎められることはなかった。だがその晩は二人の間で会話が行われることは無かった。
と青年の手をとって起こそうとした。直哉はちょっとした違和感を感じた。
すると
「離せや。」
と振りほどかれた。そしてまた逃げようとした。直哉は、それを阻止しようとうでを掴んだ。
「何故、逃げるんだ?」
「離せ。離しって言いゆうやろうがっ!」
青年は、興奮状態だった。揉み合っていると直哉の指がネックレスに引っ掛かり切れてしまった。直哉が、ネックレスに気を取られた空きに腕からすり抜けネックレスを拾って逃げて行った。
直哉が、肩を落とし一ノ瀬のところへ戻ろうとしたときふと道端に目を向けた。そこには青年が落とした財布があった。急いで拾い上げ中を確認した。直哉は、自分の感じた違和感の正体を認識した。
財布を持ち一ノ瀬のもとに戻った。一ノ瀬は、車のところにはいなかった。正面のワイパーにメモが置かれていた。
“うえはら美容整形クリニックの斜め向かいのファミリーレストランにいます。”
直哉が、向かうと上原と一ノ瀬が向かい合わせで話合っていた。一ノ瀬が、直哉に気づき手を挙げて知らせた。話は佳境へ入っていた。
「こちら付き添いの水柿です。話を戻しましょう。蘇芳茜という女性についての情報を少しでいいんです。教えて頂けませんか?」
「だからさっきから言っているように個人情報をお教えすることは出来ません。」
双方の話は、平行線をたどっていた。直哉は、ふと上原の指先に目線を向けた。右手の人差し指の付け根にたこがあった。左手をみてみると親指以外の指先に皮膚が厚くなったあとがあった。
直哉が、ふと言葉を発した。
「バイオリン、習われていたんですか?」
「え?」
「いえ、両手両指のたこです。右手の付け根にあるたこ。なかなかそんな所にタコは出来ませんから。まあ、ペンダコという可能性もありますがなら左手の指先の皮膚の厚み。これが説明がつかない。だからバイオリンかなと。」
「よく分かったわね。確かにバイオリン習ってた。幼少期から高校までね。私は、バイオリニストになりたかったんだけと親がね。一生食べていける保証は無いんだから諦めなさいって。まあね、言い返せ無かった私も悪いのよ。でも後悔だけが残っちゃった。」
上原は、遠くを見つめながら言った。直哉は、
「まだ、蘇芳茜さんは23歳なんです。まだ叶えられるだろう夢や希望がたくさんあるんです。そんな彼女が今、忽然と失踪してしまってるんです。あなたは何とも思わないんですか?」
とまくし立てた。すると上原の様子に変化が現れ始めた。忙しなく脚を組み換えたり、手を組んだり離したりした。
「でも個人情報流出なんてことになったら…」
「二度目の裁判が怖いですか?」
一ノ瀬が横から一言そえた。直哉は、話を続けた。
「僕たちは、決して情報を流出させたりしません。じゃあ、僕は高校生なので高校の生徒手帳のコピーをあなたに渡してもいい。」
そういって直哉が席を立とうとすると上原が止めた。
「分かった。そこまでしなくていいわ。…あなたは信じても良さそうだから。」
上原は、立ち上がり
「付いてきて。」
と歩きだした。
3人は、クリニックへ入って行った。看護師たちは全員帰ってしまい中は真っ暗だった。上原は、どんどん奥へ入って行く。やがて院長室に着いた。明かりを点け
「座って待っていて下さい。カルテ等を持ってきます。」
上原は、院長室を出て行った。
間もなくして上原は帰ってきた。カルテともうひとつ書類を持ってきた。
「これで全部です。コピーをしました。だからもう帰って下さい。」
「確認させて頂きます。」
中を見ると“蘇芳茜”の文字があった。読み進めると住所が書いてあった。だが鳩羽から聞いていたあの部屋の住所のものではなかった。
「ありがとうございます。決して口外致しません。約束します。」
直哉は、上原に頭を下げた。一ノ瀬も一緒に頭をさげた。
上原と別れたあと直哉たちは、車に乗り家路を急いだ。時間が10時半を回っていた。
一ノ瀬は、直哉を家に送ると言った。直哉は、断ったが親御さんに謝るからと聞かなかった。
直哉の家に着いた。チャイムを鳴らすと中から母が飛んで出てきた。
「直くん…心配したんだから。」
母は、脚の力が抜けたようにその場にしゃがみこんだ。母親は泣いていた。あの大喧嘩以来の涙だった。直哉は、少し以外に感じていた。母から“心配”の二文字がでるとは思っていなかった。自分に興味なんてないと思っていたから。
「…ごめん。連絡しなくて。」
「申し訳ありませんでした。私の管理が至りませんでした。反省致します。」
一ノ瀬も頭を下げた。
「…あの、どちら様ですか?」
母は濡れた目で一ノ瀬を見た。
「申し訳ありません。紹介が遅れました。私、直哉さんの高校で保健室の校医をしています。一ノ瀬真赭と申します。直哉さんは高校の文化祭委員に参加していまして。遅くまで私の手伝いをしてくれていて。私もその好意に甘えてしまって。親御さんにはお話が言っているとばかり…。本当に申し訳ありません。」
一ノ瀬の迫力に押される形で母親は納得した。これからは、遅くても10時までには帰って来ることと約束した。
一ノ瀬は、最後に深々と頭を下げ去って行った。一ノ瀬のお陰で余り咎められることはなかった。だがその晩は二人の間で会話が行われることは無かった。