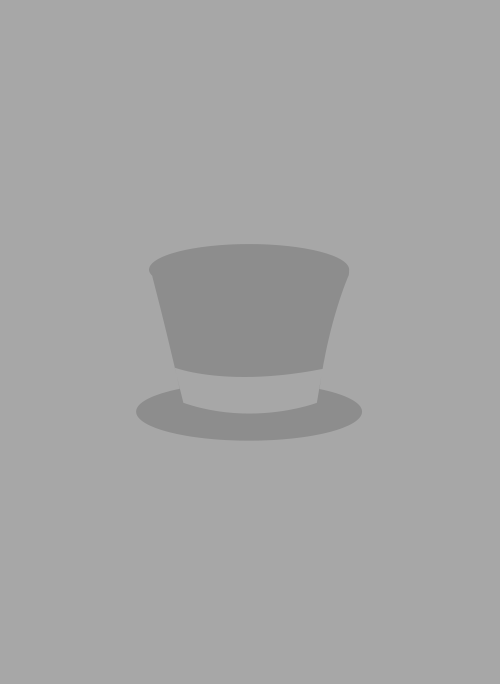1ヶ月前のあの日は、朝から雨が降っていた。母は、父方の祖父母の家に行き来客の準備の手伝いをしに行っていた。祖父は公務員でエリート官僚、祖母は、主婦をやっていたが二人とも国立大学トップ二校の出身であった。
「舞子さん、直哉はどこの大学に行くの?」
「ええ、まだ本人も決めかねているみたいで…。」
「長男の慎二を普通は国立大に行かせるべきなのよ。それが、駄目だった以上直哉には必ず行ってもらはないと。」
「はい。申し訳ありません。」
「本当に、しっかりしてちょうだい。」
「はい。申し訳ありません。」
その夜、母は少し疲れた表情で帰ってきた。
「あっ、直くん。ごめんね。お腹減ったでしょ?今、ご飯をつくるから。」
「大丈夫。もう食べた。」
「…そう。ならお風呂…」
「もう、いいよ。無理して俺に気を使うなよ。ばばあがまた小言言ったんだろ?そんなの無視し…」
「あなたにお母さんの何がわかるのよ!!頼りたい時に誰も周りに居なくて。言いたいことも言えない。あなたは、お父さんに似てはっきりものが言えるの…でもお母さんは、出来ない…出来ないの。」
崩れ落ちるように玄関にうずくまり泣き出した。何かの糸が切れた。
直哉は、その場に留まることが出来なかった。息苦しさを感じ2階の自室に駆け上がったのだった。
食べ終わった食器を流し台に運び洗った。皿をふき食器棚に戻す。いつも家事洗濯は母が全て行う。だが目の前にあるのは自分の分だけだった。
今回ぐらい自分でやらないとな…。
直哉は、皿を洗い食器棚に戻した。最後に箸を棚の引き出しに終おうと引き出しを開けた。すると家族四人の箸の横に幼児用の箸が出てきた。
“水柿直哉”
その箸には、名前入りのキャラクターシールが貼られていた。
「いつまで持ってんだよ…。」
そう吐き捨て引き出しを閉めようとした。
…あぁ…
直哉の頭の中で走馬灯の様に過去の記憶が蘇った。
家族四人での団欒の風景だった。まだ箸が持てない自分に父親が、当時直哉が好きだった戦隊ものの箸を買ってきてくれたのだ。
「お母さん!お父さんがね、ゴウケンジャーのお箸買ってきてくれたぁ―!!」
「良かったね!直くん。いっぱいお箸の練習しないとね!」
…どこで間違ったんだ。あんなに仲が良かったのに。どこで…。
そっと引き出しを閉めた。それと共に幸福だった過去の思い出にも暗く重い南京錠が掛かろうとしていた。
「舞子さん、直哉はどこの大学に行くの?」
「ええ、まだ本人も決めかねているみたいで…。」
「長男の慎二を普通は国立大に行かせるべきなのよ。それが、駄目だった以上直哉には必ず行ってもらはないと。」
「はい。申し訳ありません。」
「本当に、しっかりしてちょうだい。」
「はい。申し訳ありません。」
その夜、母は少し疲れた表情で帰ってきた。
「あっ、直くん。ごめんね。お腹減ったでしょ?今、ご飯をつくるから。」
「大丈夫。もう食べた。」
「…そう。ならお風呂…」
「もう、いいよ。無理して俺に気を使うなよ。ばばあがまた小言言ったんだろ?そんなの無視し…」
「あなたにお母さんの何がわかるのよ!!頼りたい時に誰も周りに居なくて。言いたいことも言えない。あなたは、お父さんに似てはっきりものが言えるの…でもお母さんは、出来ない…出来ないの。」
崩れ落ちるように玄関にうずくまり泣き出した。何かの糸が切れた。
直哉は、その場に留まることが出来なかった。息苦しさを感じ2階の自室に駆け上がったのだった。
食べ終わった食器を流し台に運び洗った。皿をふき食器棚に戻す。いつも家事洗濯は母が全て行う。だが目の前にあるのは自分の分だけだった。
今回ぐらい自分でやらないとな…。
直哉は、皿を洗い食器棚に戻した。最後に箸を棚の引き出しに終おうと引き出しを開けた。すると家族四人の箸の横に幼児用の箸が出てきた。
“水柿直哉”
その箸には、名前入りのキャラクターシールが貼られていた。
「いつまで持ってんだよ…。」
そう吐き捨て引き出しを閉めようとした。
…あぁ…
直哉の頭の中で走馬灯の様に過去の記憶が蘇った。
家族四人での団欒の風景だった。まだ箸が持てない自分に父親が、当時直哉が好きだった戦隊ものの箸を買ってきてくれたのだ。
「お母さん!お父さんがね、ゴウケンジャーのお箸買ってきてくれたぁ―!!」
「良かったね!直くん。いっぱいお箸の練習しないとね!」
…どこで間違ったんだ。あんなに仲が良かったのに。どこで…。
そっと引き出しを閉めた。それと共に幸福だった過去の思い出にも暗く重い南京錠が掛かろうとしていた。