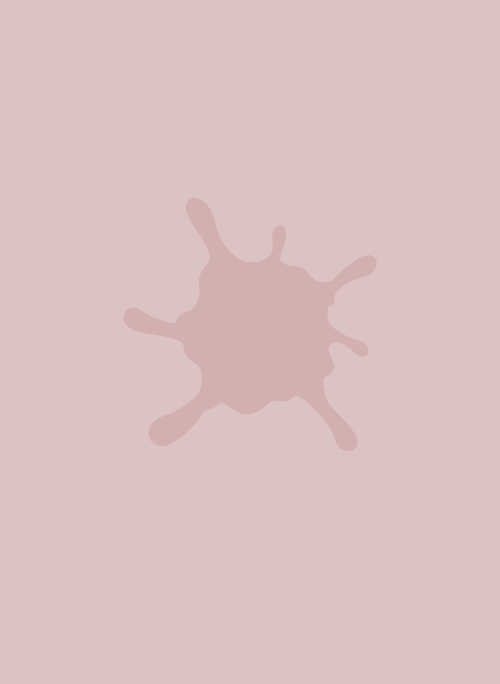第26話(side story 21)
海賊王に俺はなる!みたいなノリを真顔で言ってのけた昼下がりの弥だったが、その学習能力の高さは尋常ではなく一度見たものは確実に記憶している。一緒に見た再放送の刑事ドラマでも、犯人の特徴から部屋の小さな小物の配置まで覚えていた。もし百科事典を手渡せば一日で読破し、内容を正確にインプットするに違いない。
料理の手際も良く、生まれて初めて作った言う料理の味も本格的で、ある意味料理の鉄人とも言える。ただし瞳の色に関しては本人もよく覚えていないと言い、勇利自身さして大きな問題とも思えず軽く流す。
弥の人間離れした特技に関心していた勇利だったが、我に返り本題を全く話していなかったと思い直す。テレビの画面を消すと心を落ち着かせ弥に向き合う。
「弥さんに大事な話があるんだけど、いいかな?」
「勿論です。なんですか?」
「実は、僕には過去とても愛している女性がいました。その女性は人間性が素晴らしく魅力溢れる人だった。誰からも好かれ誰からも愛される太陽のような人。だけど、僕のせいで亡くなりました。それ以降、僕は全ての女性を避けて生きてきたんです。もう誰も好きにならない、自分は誰かを好きになるような資格すらないって思ったから。でも、貴女と出会ってそれが急変したんです。今言った亡くなった女性と貴女が瓜二つだったから」
真剣な表情で語る勇利に弥もじっと耳を傾ける。
「だから初めて弥さんを見たとき、亡くなった彼女が生まれ変わって現れたように感じたんです。極端な話、もし容姿が似てなかったらこうして向き合っていなかったと思う。それくらい貴女との出会いは衝撃的だったんです。そこで弥さんに聞きたい。この出会いは偶然だったのか、果たして仕組まれたものだったのか。そして、貴女は何者なのか。答えてくれませんか?」
出会ってからずっと抱えていた想いをぶつける勇利に、弥は戸惑うことなく即座に答える。
「勇利さんと私が出会ったのは偶然です。私も貴方の過去は知らなかったし、何より自分の名前すら無かったのだから。それと、私が何者かという問いには一つしか言いようがない。私は君島弥。勇利さんが付けてくれた君島弥という名前が全て。そう、亡くしてしまった勇利さんの大切な人と同じ名前と顔を持つ君島弥です」
会話の中から自分が亡くなった弥の名前を付けられたのだと理解し、悟ったように言い切る。亡くなった想い人の名を付けたことがバレ、申し訳ない気持ちが勇利の中に広がる。その反面、どういう存在であるかという問いについては上手くはぐらかされた感があり腑に落ちない。
人間離れした高い能力を見ても普通の人間じゃないのは理解できるものの、何故弥に似ているのかは解明されてない。本人が言いたくないのか、それとも本当に以前の記憶がないのか、二つの解釈ができるが答えを導くための情報が少なすぎ、問題に対しては保留を選択する。
「僕を軽蔑しますか? 亡くなった恋人の名前を付けるようなこの僕を」
「いいえ。勇利さんは私の命の恩人です。感謝はしても軽蔑なんて感情、微塵も感じませんよ。むしろ、何も知らない身元不明の私なんかが君島弥と称して勇利さんの側に居て良いのかが不安です。本当に私はここに居て良い存在ですか?」
「居てダメな存在なら連れて帰ってませんよ。それに、伴侶にしてくれって最初に言ったのは弥さんですよ? どういう意図で言ったんですか?」
「伴侶? 私、そんなこと言ったんですか?」
「えっ? 覚えてないんですか?」
「ごめんなさい。実は昨日の記憶がところどころないんです。どうやって怪我したのかすら覚えてなくって。山で勇利さんと出会って病院行って自宅に来た大まかな流れは覚えているんですけど……」
申し訳なさそうにそう言う弥を見ていると、よりいっそう弥という存在がどいうものか分からなくなっていく。さっき見せた記憶力の良さとは裏腹に昨日のことはほとんど覚えていない。こうなってくると山で出会ったときも記憶喪失であり、これからの生活も危く不安な面がもたげてくる。最初に少し考えていたことだが、どこかの施設から逃げ出した患者という線もあり得る。不安な気持ちが沸き起こり勇利は思い切って聞く。
「ちなみに一番古い記憶ってどんなことですか?」
「一番古い記憶は、山で勇利さんと会った瞬間。なぜあの山に居たのかも、今までどこで何をしていたのかも分からない。私自身、自分が何者かは判断がつかないんです。可笑しいですよね」
苦笑いする弥を見て勇利も対応に困る。弥に似ているというだけの理由で連れて来たものの、事件事故に巻き込まれてしまうのは教師になるという夢に向かってはマイナス要因としかならない。かと言ってあのまま怪我をした弥を見過ごせる訳もなく、現状がなるべくしくなったものだとも思う。
ただ、下山中にポツリと言った『澄み渡った綺麗な青空。私はこれを見るために生まれてきたのかもしれない』というセリフが勇利の中で引っかかっていた。同じようなセリフを過去に聞いており、本人と符合する点としても大きい。亡くなった弥とは違うと頭で分かっていても、同じ容姿で似たようなセリフを言われると心は揺れ動される。
二カ月後、楽しげに振る舞う弥を引き連れ近所のショッピングセンターへと足を運ぶ。釈然としない部分があるものの、関わった以上放り投げる訳にもいかず気持ちを切り替え日常生活を送っていた。
弥のことをつぶさに観察して分かったきたことだが、当初発揮していた学習能力や記憶力は影を潜めており、発言自体も世間並みの内容に完全シフトしている。山で出会った当初の発言から察すると人間以上の存在と思えていたが、今となるとそれもただの演技だったのかと首をひねる。今の弥と出会った当初の弥、どちらが本当の姿であるのか判断がつかないまま勇利は弥との第二の恋愛をスタートさせていた。
それと同時に、同じ屋根の下に住み毎日顔を合わす日々に幸せを感じる傍ら、未来への漠然とした不安も抱える。先々の話になるが世間的に死んでしまっている相手との婚姻関係など結べる訳もなく、病院のケースと異なり法的な手続きとなると面倒なことが多くなることが予想される。さらに言うと、子供が出来た場合を考えると簡単に手も出せない。実際一緒に住み始めて今日に至るまで、キスすら出来ておらず悶々とした日々を送っている。
初経験となる恋愛期間ゼロでスタートした同棲生活で、自身がどう対応してよいのか迷っている面もあるが、弥自身が勇利をどう想っているのかもよく分らずただいたずらに日数だけが過ぎた。ウインドウショッピングを楽しむ弥を見守りながら、勇利はそろそろ互いの想いを確認しなければならないと覚悟を決めている。
「弥さん、ちょっとお茶にしませんか?」
洋服を片手に悩んでいる弥に勇利は声をかける。勿論向き合う気持ちをもってのことだ。
「あ、ごめんなさい勇利さん。服選びに熱中し過ぎてました。喉渇きましたよね?」
「いえ、ちょっとお話をしたいなと思って」
「お話ですか。どんな話ですか?」
「それは秘密です」
「勇利さんが秘密って言うときは、たいてい良い話が多いですよね」
「あはは、バレてるし」
苦笑いする勇利を見て弥は満面の笑顔を見せる。その笑顔に勇利は心底癒されていることを実感する。愛を失ってからの苦い数年、亡くなった現場の凄惨な光景、その全てがこの笑顔によってかき消されて行く。この出会いが奇跡と言うのならば、それは神様のくれたやり直すチャンスだとしか思えない。
勇利は弥との未来を前向きに捉え一緒に歩いて行くことを決意していた。しかし、そんな決意を吹っ飛ばすが如く思いもよらない出来事が降って湧いてくるのが人生だったりもする。ショッピングセンター内のカフェに入ろうとした瞬間、逆に店から出てきた一人の女性客と目が会う。互いが互いの存在を認識したと同時に、勇利は心の中で衝撃的とも言える焦りを感じるが時既に遅く、女性こと園山真希は驚嘆の声を上げた。
「あら空条君……、えっ!? 君島先生!」
海賊王に俺はなる!みたいなノリを真顔で言ってのけた昼下がりの弥だったが、その学習能力の高さは尋常ではなく一度見たものは確実に記憶している。一緒に見た再放送の刑事ドラマでも、犯人の特徴から部屋の小さな小物の配置まで覚えていた。もし百科事典を手渡せば一日で読破し、内容を正確にインプットするに違いない。
料理の手際も良く、生まれて初めて作った言う料理の味も本格的で、ある意味料理の鉄人とも言える。ただし瞳の色に関しては本人もよく覚えていないと言い、勇利自身さして大きな問題とも思えず軽く流す。
弥の人間離れした特技に関心していた勇利だったが、我に返り本題を全く話していなかったと思い直す。テレビの画面を消すと心を落ち着かせ弥に向き合う。
「弥さんに大事な話があるんだけど、いいかな?」
「勿論です。なんですか?」
「実は、僕には過去とても愛している女性がいました。その女性は人間性が素晴らしく魅力溢れる人だった。誰からも好かれ誰からも愛される太陽のような人。だけど、僕のせいで亡くなりました。それ以降、僕は全ての女性を避けて生きてきたんです。もう誰も好きにならない、自分は誰かを好きになるような資格すらないって思ったから。でも、貴女と出会ってそれが急変したんです。今言った亡くなった女性と貴女が瓜二つだったから」
真剣な表情で語る勇利に弥もじっと耳を傾ける。
「だから初めて弥さんを見たとき、亡くなった彼女が生まれ変わって現れたように感じたんです。極端な話、もし容姿が似てなかったらこうして向き合っていなかったと思う。それくらい貴女との出会いは衝撃的だったんです。そこで弥さんに聞きたい。この出会いは偶然だったのか、果たして仕組まれたものだったのか。そして、貴女は何者なのか。答えてくれませんか?」
出会ってからずっと抱えていた想いをぶつける勇利に、弥は戸惑うことなく即座に答える。
「勇利さんと私が出会ったのは偶然です。私も貴方の過去は知らなかったし、何より自分の名前すら無かったのだから。それと、私が何者かという問いには一つしか言いようがない。私は君島弥。勇利さんが付けてくれた君島弥という名前が全て。そう、亡くしてしまった勇利さんの大切な人と同じ名前と顔を持つ君島弥です」
会話の中から自分が亡くなった弥の名前を付けられたのだと理解し、悟ったように言い切る。亡くなった想い人の名を付けたことがバレ、申し訳ない気持ちが勇利の中に広がる。その反面、どういう存在であるかという問いについては上手くはぐらかされた感があり腑に落ちない。
人間離れした高い能力を見ても普通の人間じゃないのは理解できるものの、何故弥に似ているのかは解明されてない。本人が言いたくないのか、それとも本当に以前の記憶がないのか、二つの解釈ができるが答えを導くための情報が少なすぎ、問題に対しては保留を選択する。
「僕を軽蔑しますか? 亡くなった恋人の名前を付けるようなこの僕を」
「いいえ。勇利さんは私の命の恩人です。感謝はしても軽蔑なんて感情、微塵も感じませんよ。むしろ、何も知らない身元不明の私なんかが君島弥と称して勇利さんの側に居て良いのかが不安です。本当に私はここに居て良い存在ですか?」
「居てダメな存在なら連れて帰ってませんよ。それに、伴侶にしてくれって最初に言ったのは弥さんですよ? どういう意図で言ったんですか?」
「伴侶? 私、そんなこと言ったんですか?」
「えっ? 覚えてないんですか?」
「ごめんなさい。実は昨日の記憶がところどころないんです。どうやって怪我したのかすら覚えてなくって。山で勇利さんと出会って病院行って自宅に来た大まかな流れは覚えているんですけど……」
申し訳なさそうにそう言う弥を見ていると、よりいっそう弥という存在がどいうものか分からなくなっていく。さっき見せた記憶力の良さとは裏腹に昨日のことはほとんど覚えていない。こうなってくると山で出会ったときも記憶喪失であり、これからの生活も危く不安な面がもたげてくる。最初に少し考えていたことだが、どこかの施設から逃げ出した患者という線もあり得る。不安な気持ちが沸き起こり勇利は思い切って聞く。
「ちなみに一番古い記憶ってどんなことですか?」
「一番古い記憶は、山で勇利さんと会った瞬間。なぜあの山に居たのかも、今までどこで何をしていたのかも分からない。私自身、自分が何者かは判断がつかないんです。可笑しいですよね」
苦笑いする弥を見て勇利も対応に困る。弥に似ているというだけの理由で連れて来たものの、事件事故に巻き込まれてしまうのは教師になるという夢に向かってはマイナス要因としかならない。かと言ってあのまま怪我をした弥を見過ごせる訳もなく、現状がなるべくしくなったものだとも思う。
ただ、下山中にポツリと言った『澄み渡った綺麗な青空。私はこれを見るために生まれてきたのかもしれない』というセリフが勇利の中で引っかかっていた。同じようなセリフを過去に聞いており、本人と符合する点としても大きい。亡くなった弥とは違うと頭で分かっていても、同じ容姿で似たようなセリフを言われると心は揺れ動される。
二カ月後、楽しげに振る舞う弥を引き連れ近所のショッピングセンターへと足を運ぶ。釈然としない部分があるものの、関わった以上放り投げる訳にもいかず気持ちを切り替え日常生活を送っていた。
弥のことをつぶさに観察して分かったきたことだが、当初発揮していた学習能力や記憶力は影を潜めており、発言自体も世間並みの内容に完全シフトしている。山で出会った当初の発言から察すると人間以上の存在と思えていたが、今となるとそれもただの演技だったのかと首をひねる。今の弥と出会った当初の弥、どちらが本当の姿であるのか判断がつかないまま勇利は弥との第二の恋愛をスタートさせていた。
それと同時に、同じ屋根の下に住み毎日顔を合わす日々に幸せを感じる傍ら、未来への漠然とした不安も抱える。先々の話になるが世間的に死んでしまっている相手との婚姻関係など結べる訳もなく、病院のケースと異なり法的な手続きとなると面倒なことが多くなることが予想される。さらに言うと、子供が出来た場合を考えると簡単に手も出せない。実際一緒に住み始めて今日に至るまで、キスすら出来ておらず悶々とした日々を送っている。
初経験となる恋愛期間ゼロでスタートした同棲生活で、自身がどう対応してよいのか迷っている面もあるが、弥自身が勇利をどう想っているのかもよく分らずただいたずらに日数だけが過ぎた。ウインドウショッピングを楽しむ弥を見守りながら、勇利はそろそろ互いの想いを確認しなければならないと覚悟を決めている。
「弥さん、ちょっとお茶にしませんか?」
洋服を片手に悩んでいる弥に勇利は声をかける。勿論向き合う気持ちをもってのことだ。
「あ、ごめんなさい勇利さん。服選びに熱中し過ぎてました。喉渇きましたよね?」
「いえ、ちょっとお話をしたいなと思って」
「お話ですか。どんな話ですか?」
「それは秘密です」
「勇利さんが秘密って言うときは、たいてい良い話が多いですよね」
「あはは、バレてるし」
苦笑いする勇利を見て弥は満面の笑顔を見せる。その笑顔に勇利は心底癒されていることを実感する。愛を失ってからの苦い数年、亡くなった現場の凄惨な光景、その全てがこの笑顔によってかき消されて行く。この出会いが奇跡と言うのならば、それは神様のくれたやり直すチャンスだとしか思えない。
勇利は弥との未来を前向きに捉え一緒に歩いて行くことを決意していた。しかし、そんな決意を吹っ飛ばすが如く思いもよらない出来事が降って湧いてくるのが人生だったりもする。ショッピングセンター内のカフェに入ろうとした瞬間、逆に店から出てきた一人の女性客と目が会う。互いが互いの存在を認識したと同時に、勇利は心の中で衝撃的とも言える焦りを感じるが時既に遅く、女性こと園山真希は驚嘆の声を上げた。
「あら空条君……、えっ!? 君島先生!」