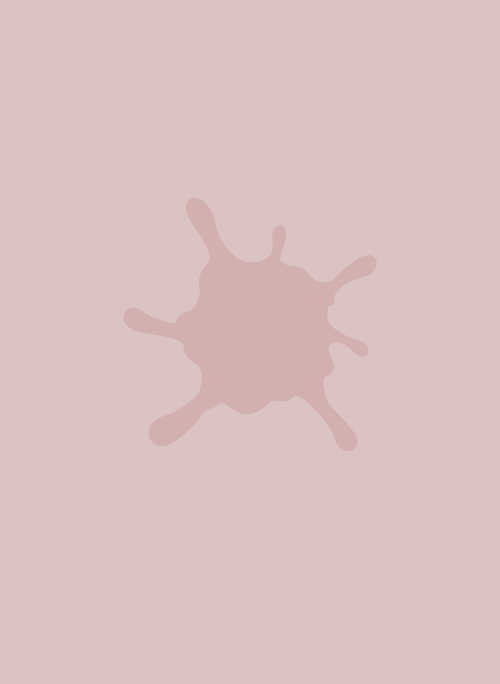第14話(side story 11)
凄惨な事件も風化しつつあった半年後、新宿駅の改札を抜け職場である歌舞伎町に向かって歩いていると、勇利はすれ違った女性に呼び止められる。
「あの、もしかして、空条君?」
無言で振り向いた先に居る、明らかにキャバ嬢っぽい服装の女性に勇利は首を傾げる。勇利の本名を知ってるのは歌舞伎町でも店のオーナーしかいない。訝しがりながら警戒し睨んでいると女性は笑顔を見せる。
「お久しぶり、もう忘れてるかな? 私よ、園山真紀」
歌舞伎町という特異な場所での邂逅を驚くよりも、優等生であった真紀の変貌ぶりに勇利は目を見張る。自己紹介を受けなければ真紀とは絶対に分からないくらい派手な化粧をしており、夜の蝶としての匂いが漂っている。挨拶もそこそこに場を離れようとするものの、大事な話があると懇願されてしぶしぶ頷く。通りの見下ろせるカフェに入り、向かい合って座ると同時に真紀は深々と頭を下げる。
「ごめんなさい。空条君にはいくら謝っても謝りきれないことをしてしまった」
「あ? 何のことだよ?」
「君島先生のこと……」
「その名前を出すな!」
店内でいきなり大声を出す勇利に、周りの客は驚きビクッとしている。
「今度その名前を言ったら殺す」
本気で言っていることが伝わる程の殺意を目つきから感じ真紀は心底怯える。今の勇利にとって弥という単語は怒りと後悔の混じった激情のトリガーでしかない。仕事に没頭することで忘れようとしていた過去なだけに、名前を聞いた瞬間押し込めていた感情が爆発する。
「話がそれなら俺はもう行くぞ」
「ま、待って。私もずっと苦しんでるの」
「はあ? オマエが苦しいとか俺の人生に関係あるのか? 知るか」
「奈々絵さん、自殺したわ。知ってる?」
奈々絵という名前でコーポでの惨殺シーンが甦る。いつものように学校から直でコーポに向かい玄関の扉を開いた瞬間、目に飛び込んできたのは真っ赤な光景だった。玄関に隣接するキッチンの床に倒れている弥と、その横で包丁を片手にニヤニヤしていた血塗れの奈々絵は、勇利の心を一瞬にして粉々にした。
「知らねえし、どうでもいい。道ですれ違っても、もう俺に話し掛けてくるなよ」
席を立つと、店員に迷惑料と告げ一万円札を一枚渡し店を後にする。真紀は微動だにできず、その背中を見送ることしかできなかった。
クラブ聖夜では連日イベントが開催され、異様に賑わっていた。入店半年ながら指名ナンバー3まで人気急上昇していた勇利も忙しく店内を行き来する。女性の扱いは言うまでもなく、もともと酒に強いこともあって、この仕事は天職だと実感する。ただし、ナンバー2の琥珀(こはく)とナンバー1の蓮夜(れんや)は別格で全く勝てる気がしない。新規の客を適当にあしらいながら飲んでいると、ヘルプの陸斗(りくと)がサッと側に座る。
「優星(ゆうせい)さん、純子(じゅんこ)さん来ました!」
「分かった、すぐ行く」
女の子に断りを入れフロアの入り口に立つと、勇利は純子を迎え入れる態勢を整える。純子は勇利にとって言わば上客であり、ここまで出世できたのも彼女の支援あってのことだと理解していた。紫のドレス姿で現れたスタイル抜群の純子は、勇利を見ると微笑み話し掛けてくる。
「こんばんは、優星」
「いらっしゃいませ、純子様。こちらへどうぞ」
笑顔でエスコートすると、勇利と純子はVIPルームへと向かう。席に着くと何も言うことなく、フルーツの盛り合わせと年代物のロマネコンティが出される。かなりの額を毎回落としてくれる純子だが、年齢から職業まで一切が不明で、外見から四十代という推測くらいしかできない。通り一遍な挨拶を交わしていると、純子が話を切り出す。
「ねえ、優星。ここで私と知り合ったのがいつかは覚えてる?」
「勿論です。2月14日のバレンタインイベントのときですよね」
「そう、だからそろそろ三カ月になるわ」
純子の言葉で同伴デート等を想像するが、予想外な言葉が飛び出る。
「私、そろそろホスト遊びを卒業しようと思ってるのよ」
「え、それはまた急なお話ですね。僕に何か至らないところでもありましたか?」
「ううん、優星は悪くないし無関係。単純に私的な理由ね」
「私的な理由。何かにお悩みでしたら、微力ながらこの僕が……」
大幅な売上減となるかもしれない出来事に、勇利は内心焦る。
「理由は、そうね。とても重たいテーマになるわ。例えばだけど、もし、自分の命が後一年と告げられたらどうする?」
「えっ!? 純子さん、ご病気なんですか?」
「いやね~、私はいたって健康よ。だから、例えばの話よ。優星ならどんな行動を取るかしら?」
「僕が一年の命なら……」
真剣に考える勇利の横顔を純子はグラスを傾けながら見つめる。あの事件以来、勇利にとって命はどうでもいい分類にカテゴリされている。生きてても死んでても何の意味も持たない人生。心から愛するものを失った絶望感は何ものにも代え難く、誰にも理解できない。
「正直に言うと、分からないです。いざ、そういう状態にならないと分からないかもしれません」
「そう、それも一理あるわね。でも、私の望む回答ではないわ」
純子は回答を聞き不満げにグラスの液体を飲み干す。
「純子さん?」
「今月、そう、後二回お店に来るから、違う回答を考えておいて。もし私の望む回答を導き出すことができたら、卒業を撤回してあげる」
挑戦的な眼差しを向ける純子を見て、勇利は息を呑んでいた。
凄惨な事件も風化しつつあった半年後、新宿駅の改札を抜け職場である歌舞伎町に向かって歩いていると、勇利はすれ違った女性に呼び止められる。
「あの、もしかして、空条君?」
無言で振り向いた先に居る、明らかにキャバ嬢っぽい服装の女性に勇利は首を傾げる。勇利の本名を知ってるのは歌舞伎町でも店のオーナーしかいない。訝しがりながら警戒し睨んでいると女性は笑顔を見せる。
「お久しぶり、もう忘れてるかな? 私よ、園山真紀」
歌舞伎町という特異な場所での邂逅を驚くよりも、優等生であった真紀の変貌ぶりに勇利は目を見張る。自己紹介を受けなければ真紀とは絶対に分からないくらい派手な化粧をしており、夜の蝶としての匂いが漂っている。挨拶もそこそこに場を離れようとするものの、大事な話があると懇願されてしぶしぶ頷く。通りの見下ろせるカフェに入り、向かい合って座ると同時に真紀は深々と頭を下げる。
「ごめんなさい。空条君にはいくら謝っても謝りきれないことをしてしまった」
「あ? 何のことだよ?」
「君島先生のこと……」
「その名前を出すな!」
店内でいきなり大声を出す勇利に、周りの客は驚きビクッとしている。
「今度その名前を言ったら殺す」
本気で言っていることが伝わる程の殺意を目つきから感じ真紀は心底怯える。今の勇利にとって弥という単語は怒りと後悔の混じった激情のトリガーでしかない。仕事に没頭することで忘れようとしていた過去なだけに、名前を聞いた瞬間押し込めていた感情が爆発する。
「話がそれなら俺はもう行くぞ」
「ま、待って。私もずっと苦しんでるの」
「はあ? オマエが苦しいとか俺の人生に関係あるのか? 知るか」
「奈々絵さん、自殺したわ。知ってる?」
奈々絵という名前でコーポでの惨殺シーンが甦る。いつものように学校から直でコーポに向かい玄関の扉を開いた瞬間、目に飛び込んできたのは真っ赤な光景だった。玄関に隣接するキッチンの床に倒れている弥と、その横で包丁を片手にニヤニヤしていた血塗れの奈々絵は、勇利の心を一瞬にして粉々にした。
「知らねえし、どうでもいい。道ですれ違っても、もう俺に話し掛けてくるなよ」
席を立つと、店員に迷惑料と告げ一万円札を一枚渡し店を後にする。真紀は微動だにできず、その背中を見送ることしかできなかった。
クラブ聖夜では連日イベントが開催され、異様に賑わっていた。入店半年ながら指名ナンバー3まで人気急上昇していた勇利も忙しく店内を行き来する。女性の扱いは言うまでもなく、もともと酒に強いこともあって、この仕事は天職だと実感する。ただし、ナンバー2の琥珀(こはく)とナンバー1の蓮夜(れんや)は別格で全く勝てる気がしない。新規の客を適当にあしらいながら飲んでいると、ヘルプの陸斗(りくと)がサッと側に座る。
「優星(ゆうせい)さん、純子(じゅんこ)さん来ました!」
「分かった、すぐ行く」
女の子に断りを入れフロアの入り口に立つと、勇利は純子を迎え入れる態勢を整える。純子は勇利にとって言わば上客であり、ここまで出世できたのも彼女の支援あってのことだと理解していた。紫のドレス姿で現れたスタイル抜群の純子は、勇利を見ると微笑み話し掛けてくる。
「こんばんは、優星」
「いらっしゃいませ、純子様。こちらへどうぞ」
笑顔でエスコートすると、勇利と純子はVIPルームへと向かう。席に着くと何も言うことなく、フルーツの盛り合わせと年代物のロマネコンティが出される。かなりの額を毎回落としてくれる純子だが、年齢から職業まで一切が不明で、外見から四十代という推測くらいしかできない。通り一遍な挨拶を交わしていると、純子が話を切り出す。
「ねえ、優星。ここで私と知り合ったのがいつかは覚えてる?」
「勿論です。2月14日のバレンタインイベントのときですよね」
「そう、だからそろそろ三カ月になるわ」
純子の言葉で同伴デート等を想像するが、予想外な言葉が飛び出る。
「私、そろそろホスト遊びを卒業しようと思ってるのよ」
「え、それはまた急なお話ですね。僕に何か至らないところでもありましたか?」
「ううん、優星は悪くないし無関係。単純に私的な理由ね」
「私的な理由。何かにお悩みでしたら、微力ながらこの僕が……」
大幅な売上減となるかもしれない出来事に、勇利は内心焦る。
「理由は、そうね。とても重たいテーマになるわ。例えばだけど、もし、自分の命が後一年と告げられたらどうする?」
「えっ!? 純子さん、ご病気なんですか?」
「いやね~、私はいたって健康よ。だから、例えばの話よ。優星ならどんな行動を取るかしら?」
「僕が一年の命なら……」
真剣に考える勇利の横顔を純子はグラスを傾けながら見つめる。あの事件以来、勇利にとって命はどうでもいい分類にカテゴリされている。生きてても死んでても何の意味も持たない人生。心から愛するものを失った絶望感は何ものにも代え難く、誰にも理解できない。
「正直に言うと、分からないです。いざ、そういう状態にならないと分からないかもしれません」
「そう、それも一理あるわね。でも、私の望む回答ではないわ」
純子は回答を聞き不満げにグラスの液体を飲み干す。
「純子さん?」
「今月、そう、後二回お店に来るから、違う回答を考えておいて。もし私の望む回答を導き出すことができたら、卒業を撤回してあげる」
挑戦的な眼差しを向ける純子を見て、勇利は息を呑んでいた。