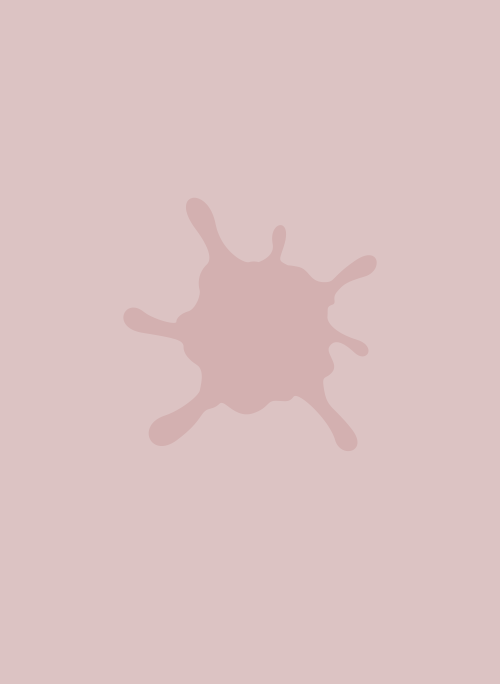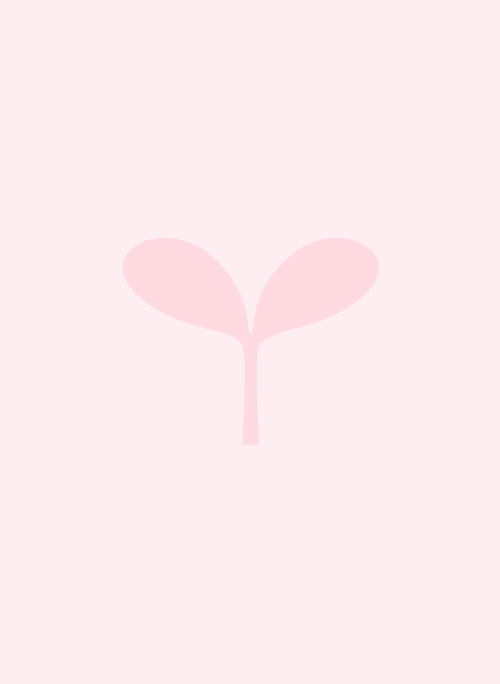電話機を彼女は取った。
そして、すっかり乾ききった上下の唇をおもむろに引きはがして、言った。
「......もう、終わりに」
この部屋の中、その無感情で、うつ状態の様な小さな呟き声は、静かに響きわたった......。
しかし、それは、丸で夢だったかのように彼女は、自分自身を取り戻した。
笑顔も、汚れた様な目的なんかで笑う顔ではなくなった。
心して、純粋に笑う姿を取り戻していた。
............意を決して、正解だった──と、彼女は思う。
「おかえり」
「ただいま」
こういう、何気ないヘリオスとの会話すら、笑みを浮かべていた。
「あの曲はもう弾かないの?」
「あの曲って?」
ヘリオスは、首をひねらせた。
「太陽ノ光」
色気を感じさせる笑みを浮かべながら、ヘリオスの茶色い目を見詰めた。
「あの曲は、ヴィーナス様の誕生日会に使われる曲なんだよ」
「......でも、私は弾いて欲しい」
そう言って、ジュノはおもむろな瞳をヘリオスに向けた。
何気ない会話をする上で、このベッドの居心地は温かで落ち着けた。
そして、すっかり乾ききった上下の唇をおもむろに引きはがして、言った。
「......もう、終わりに」
この部屋の中、その無感情で、うつ状態の様な小さな呟き声は、静かに響きわたった......。
しかし、それは、丸で夢だったかのように彼女は、自分自身を取り戻した。
笑顔も、汚れた様な目的なんかで笑う顔ではなくなった。
心して、純粋に笑う姿を取り戻していた。
............意を決して、正解だった──と、彼女は思う。
「おかえり」
「ただいま」
こういう、何気ないヘリオスとの会話すら、笑みを浮かべていた。
「あの曲はもう弾かないの?」
「あの曲って?」
ヘリオスは、首をひねらせた。
「太陽ノ光」
色気を感じさせる笑みを浮かべながら、ヘリオスの茶色い目を見詰めた。
「あの曲は、ヴィーナス様の誕生日会に使われる曲なんだよ」
「......でも、私は弾いて欲しい」
そう言って、ジュノはおもむろな瞳をヘリオスに向けた。
何気ない会話をする上で、このベッドの居心地は温かで落ち着けた。