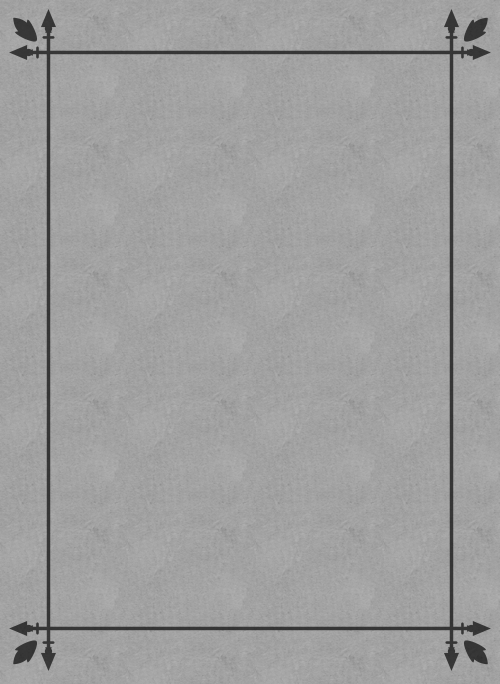すると彼女は、首を左右に振る。
「ぶつかったんです」
ぶつかって転んだんだ。
だけど、そのまま返したりしない。
「あのミケ猫と?」
「……は?…ミケ猫?」
きょとん、と聞き返してくる彼女。
「っ…」
手を動かして傷口を消毒すれば、
やっぱり滲みたのか顔を歪ませた。
ごめんね、痛いよね。
できるだけ痛くないようにしてるんだけど…。
思わず手を止めてしまい、続きを話す。
「だから、ミケ猫とケンカしてたんじゃないんですか?」
ぽかんとしたままの彼女に笑顔を向ける。
僕では、
君と同じ高校の教師としての僕では、
君を助けてあげることができない。
君もきっと、僕と同じ高校だと思い出せば拒絶するだろう。何も知らない、君のことが分からないとしていた方が、君も少しは僕を頼ってくれるんじゃないかな。