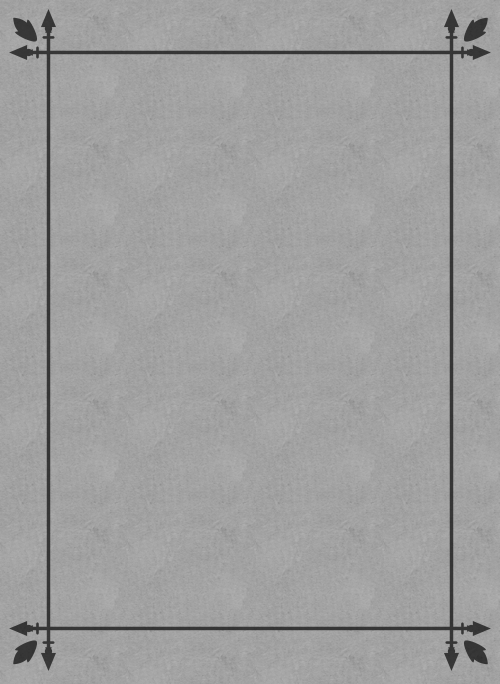そしてやっぱり、どうすればいいのかとそのままその先を見ていて。僕はそんな彼女を通り越して先に進む。
「適当に座ってて」
そう彼女に告げれば、僕を見た後ゆっくりとカーペットの上に腰を下ろした。
手当て手当て…
居心地が悪そうに小さく座って視線を彷徨わせる彼女を確認しながら、手当ての為に動き回る。
さっきは薄暗くてはっきりとは分からなかったけれど、
明るい部屋の中では彼女の傷がしっかりと見える。
転んで擦りむいたところは砂が少しついていて、濡れタオルを持って彼女の横に座った。
「はい、手出して」
僕の言葉に彼女は黙って言われた通りに手を差し出してくれて。
近くで見れば見るほど痛々しくて自分まで痛い気がしてくる。
最近はこんなケガ、したことない。
最後にケガしたのはいつだったけな…。傷が残らなければいいけれど…。
なるべく傷に触らないようにタオルでふき取っていく。
よし、こんなもんかな。
消毒液を手に取り、彼女に話しかける。
「ケンカでもしたの?」
僕は君を猫だと勘違いしてる、そういう設定だから、転んだの?とは聞かずにそう聞いた。