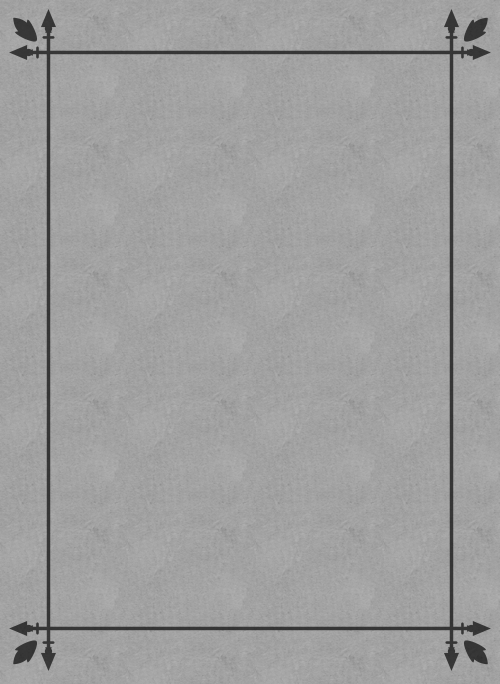そのあと
英語科へ足を運ぶことは全くなくて。
たまに、
本当にたまに、
見かけた時に見る彼女は、いつも友達と楽しそうに笑ってる姿だった。
あの子の言葉に僕は助けられた、という気持ちはずっとあったけど
あの子の存在自体はいつの間にか記憶から薄れて消えつつあって。
その名前を久しぶりに聞いたのは、教師になって2年目の夏休みが明けてすぐだった。
「――松岡さん、どうですか?」
職員室で英語科を担当している河西先生と話していれば、養護教諭の江藤先生が声をかけてきた。
松岡さん…?
あぁ、松岡月菜さんか。
ふっと、忘れかけていた彼女が頭の中に思い浮かぶ。
「あぁ、」と眉根を下げる河西先生。
何かあったのだろうか。
「松岡さん…どうかされたんですか?」
河西先生と江藤先生に聞けば、二人とも同じような顔をする。
「先日、お母さんが倒れられたらしくて…」
「えっ?」
「原因はストレスや疲労らしいんですけど、未だに目を覚ましてないらしいです。それで、松岡さんずっと学校休んでいるんですよね?」