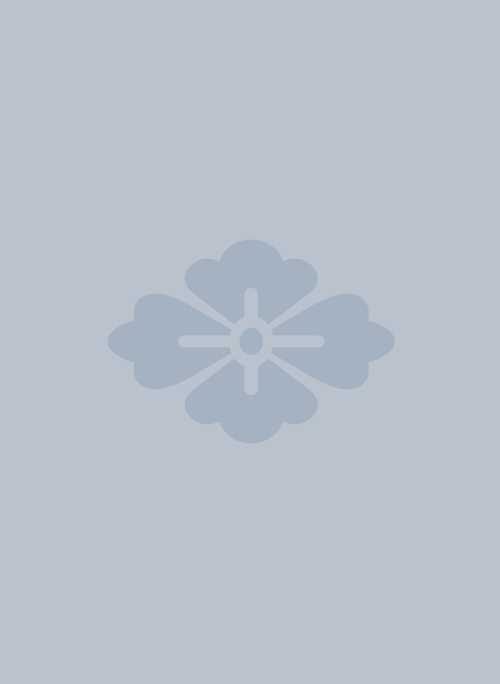私も、指示通りに料理して行く。
そんな匂いに当てられながらも、必死に料理を作り上げて行った。
「ああ〜!終わった、終わった」
布団の敷いてある和室の中、綾が布団に倒れこむ。
私も同じように倒れこんだ。
布団、ふかふかだ……。
「綾!秋羽!じゃあ、私も」
椿も倒れこむ。
右を見れば、綾、椿が隣で寝っ転がっていた。
「もう、今日も疲れちゃったよ〜」
椿が仰向けになって大口を開けた。
「私もだ」
「あたしも〜」
私達は、顔を見合わせると体を互いに近づけて、団子のようにくっつく。
そして、部屋の灯りを消して、静かに話し始めた。
「でも、秋羽が来てくれて嬉しいよ。私」
「あたしも。人手足りなかったし、楽しいしさ」
椿……、綾。
なんか、嬉しいな。
「秋羽が来てもう一ヶ月前経つけどさ、なんて言うか……すごいよね」
「綾、どういうことなのだ?」
「料理、すごく上手だし、よくわかんない接客法?それ取り入れたら、どんどん人気になって常連客増えて行くしさ」
椿まで……。
別に、そこまで上手くはないが、店では私の“秋羽特製お膳”という料理までメニューとしてある。
接客法というのは、大したことでない。
料理を最初から注文性にしたり、季節のオススメメニューを紹介したりするという、未来では普通なことをしたまでだ。
「食後のお饅頭には驚いちゃったけどさ」
「私も」