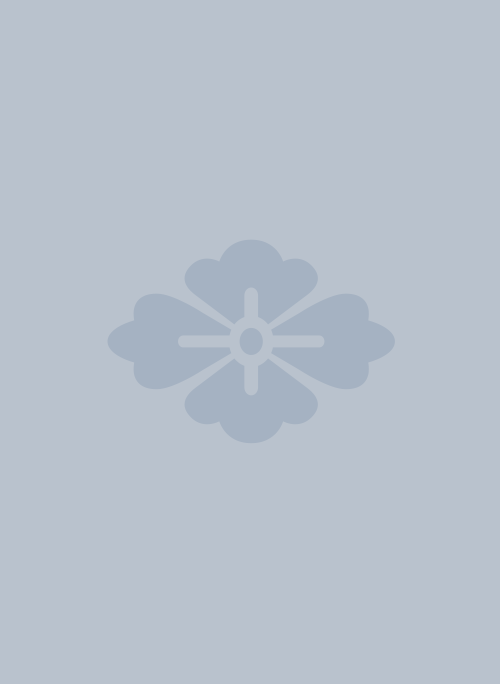肝が据わるとまりあは早い。
渡された食糧を手早く包むと、ゴスロリ姿のまま包囲線から銀行の夜間金庫の入り口に立ち、
「約束通り、食糧を渡しに来ました」
と鉄の扉にあるインターホンに呼ばわった。
犯人は姿を見たらしく、
「扉の前に置いて立ち去れ」
とインターホン越しに指示を出した。
まりあは指示に従って戻って来ると、
「…アクセントが変な若い女です」
とのみ言った。
「あれは関西弁でも東京のアクセントでもない」
たどたどしいから外国人ではないか、というような旨のことを言った。
「外国人、か…」
進藤は呟いた。
「手荒なことをする可能性がありますね」
集中力があったからか、穆は冷静さを忘れてはいなかった。
「こうなったら、昏睡作戦しかないでしょ」
まりあがボソッと言った。
「昏睡作戦?」
進藤が訊いた。
「食糧を要求したってことは、飲み物を要求してくる可能性があるってことですよね、穆さん」
「それは」
前にそういう話は、聞いたことがある。
「でもあれは物語の話で…だいいち睡眠薬をどう入手するんや」
「それは医師を呼べば何とかなります」
進藤が応じた。
「こういった事件では救護班がいます。警察の指示で医師が処方をすれば法律的には問題ありません」
「なるほど」
「まりあちゃんの作戦、使わせてもらいますよ」
そうやって。
進藤は弁当を手配しようとした。
が。
苦味が隠れない。
「うーん」
「…オレンジジュースなら気持ち苦くても、分からんはずや」
穆のひらめきで、オレンジジュースに微量の睡眠薬が混ぜられた。
一口舐めてみると、
「これなら分からないですね」
進藤の評価が出た。
「要求が来てから出す」
という手はずを整え、それが来るのを待った。