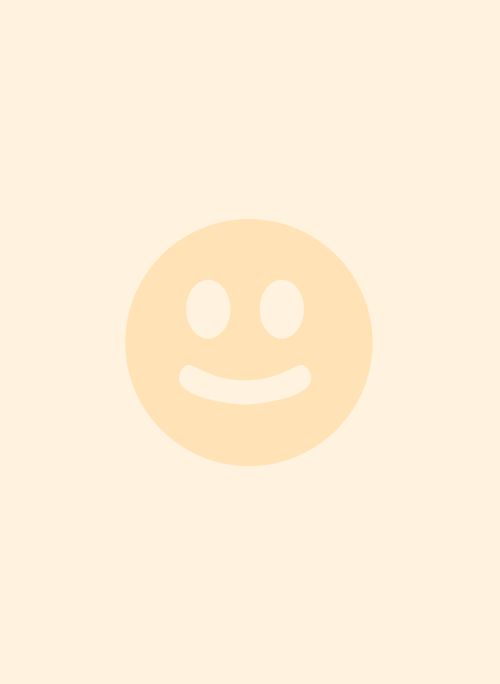それから、走って家まで帰った。疲れたら歩くけれど、一度も止まらない。
息をきらして家にとびこんでいくと、ばあちゃんは今の机の上ではっさくの皮をむいていた。
柑橘とい草の香りの中で牧村さんのことを話すと、ばあちゃんは目を丸くした。
「ようやく、会えたんやねえ。ほんまにあの人は、あんたのことをずっと気にしとったから」
「うん、今日会えてよかった」
返事をして自分の部屋へ駆け上がる。
机に上に置いていた箱を抱えて階段をおり、もう一度声をかける。
「だから、行ってくる」
持っているものを見て、ばあちゃんはうなずいた。
「行ってきい」
何から、どんな風に伝えよう。何日間か部屋で悩み続けていた。
でも1人で悩んでいるぐらいなら、順序立っていなくてもばらばらのままでも、悩みその中のものを一刻も早く共有していればよかったのだ。
ばあちゃんは、2人で選べることは幸せなことなのだと教えてくれた。
まだ遅くはないはずだ。
急激に湧きあがってきた焦燥感と共に、岬への道を急いだ。
息をきらして家にとびこんでいくと、ばあちゃんは今の机の上ではっさくの皮をむいていた。
柑橘とい草の香りの中で牧村さんのことを話すと、ばあちゃんは目を丸くした。
「ようやく、会えたんやねえ。ほんまにあの人は、あんたのことをずっと気にしとったから」
「うん、今日会えてよかった」
返事をして自分の部屋へ駆け上がる。
机に上に置いていた箱を抱えて階段をおり、もう一度声をかける。
「だから、行ってくる」
持っているものを見て、ばあちゃんはうなずいた。
「行ってきい」
何から、どんな風に伝えよう。何日間か部屋で悩み続けていた。
でも1人で悩んでいるぐらいなら、順序立っていなくてもばらばらのままでも、悩みその中のものを一刻も早く共有していればよかったのだ。
ばあちゃんは、2人で選べることは幸せなことなのだと教えてくれた。
まだ遅くはないはずだ。
急激に湧きあがってきた焦燥感と共に、岬への道を急いだ。