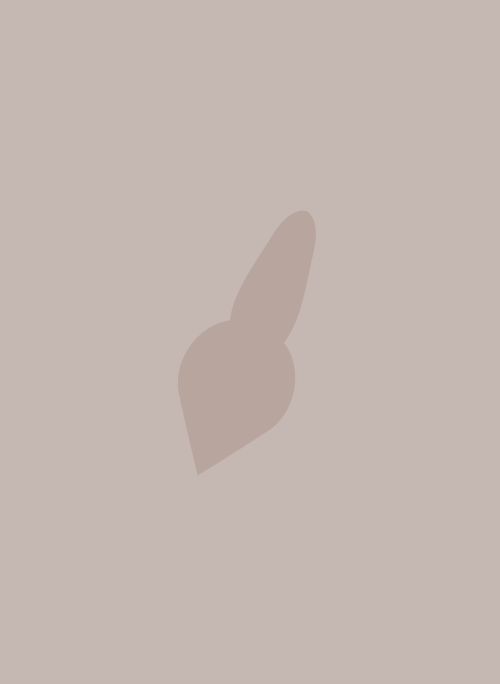空に月が登り、今日もまた夜を迎えた。
村の人々は今頃、あたたかいご飯でも食べているのだろうか。
私は1人岩と鉄格子に囲まれた檻の中で、ふと、そんなことを考えていた。
人柱となる私には、いつも冷えきったお米でつくられたおにぎりしか与えられない。
そして、人と会うのもそのときだけだった。
「今日もあの人は来てくれるかしら。」
小さな声でそっと呟く。
私は、毎晩私にその一度きりのご飯を運んできてるれる三つ年上の男の人に恋をしていた。決して叶うことのない恋を...。
そして、今日もやってきたその青年に私は話しかけることもできないまま、また一日が過ぎてゆくのだ。
「飯を届けに来た。」
(あ...。)
鉄格子を挟んで、その人がいつの間にか目の前に立っていた。
「......。」
私は何も言わずに、檻の中から手を伸ばしておにぎりを掴んだ。
(...あれ?)
それはいつもと違い、少しあたたかかった。
「...あ...たたか...い。」
それが嬉しくて、私はふと微笑んだ。
「やっと笑った。」
「え?」
びっくりした、声をかけられるなんて思っていなかったから。しかも、そんな優しそうな顔で。
「ずっと、見てみたかったんだ。」
(ずっと...?)
「やっぱり、綺麗だね。」
「...綺麗...?」
「うん。」
そう言われて顔を上げると、そこには月の光を背に浴びて少し陰って見える青年の顔があった。
こうしてきちんと見ると、とても整った顔立ちをしている。
「名前は?」
「え?」
「君の名前。」
そう言って、青年はニッコリと笑った。
村の人々は今頃、あたたかいご飯でも食べているのだろうか。
私は1人岩と鉄格子に囲まれた檻の中で、ふと、そんなことを考えていた。
人柱となる私には、いつも冷えきったお米でつくられたおにぎりしか与えられない。
そして、人と会うのもそのときだけだった。
「今日もあの人は来てくれるかしら。」
小さな声でそっと呟く。
私は、毎晩私にその一度きりのご飯を運んできてるれる三つ年上の男の人に恋をしていた。決して叶うことのない恋を...。
そして、今日もやってきたその青年に私は話しかけることもできないまま、また一日が過ぎてゆくのだ。
「飯を届けに来た。」
(あ...。)
鉄格子を挟んで、その人がいつの間にか目の前に立っていた。
「......。」
私は何も言わずに、檻の中から手を伸ばしておにぎりを掴んだ。
(...あれ?)
それはいつもと違い、少しあたたかかった。
「...あ...たたか...い。」
それが嬉しくて、私はふと微笑んだ。
「やっと笑った。」
「え?」
びっくりした、声をかけられるなんて思っていなかったから。しかも、そんな優しそうな顔で。
「ずっと、見てみたかったんだ。」
(ずっと...?)
「やっぱり、綺麗だね。」
「...綺麗...?」
「うん。」
そう言われて顔を上げると、そこには月の光を背に浴びて少し陰って見える青年の顔があった。
こうしてきちんと見ると、とても整った顔立ちをしている。
「名前は?」
「え?」
「君の名前。」
そう言って、青年はニッコリと笑った。