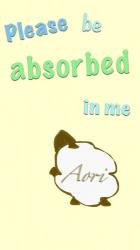部室のドアを後ろ手で閉めて、ドアに背中を預けたままずるずると座り込んだ。
滲んだ涙を袖で拭ってゆっくりと息をつく。
体育館を締めるのはやっておくよ、と同級生を先に帰らせたのは正解だった。
部室にはもう誰もいなくて、私がどんな表情をしていようと「どうしたの?」と声をかける人はいない。
泣くのを堪えたせいで喉が干上がったような感覚がして、鞄から水筒を取り出して喉に通す。
「は…」
言葉にできない感情が胸を占め、しばらく天井を見つめたままその場から動けずにいたのだった。
***
ふいに着信の音が聞こえて携帯電話を見ると、時刻はすでに二時半を過ぎていた。
メールはどこかのサイトからだった。
(…帰らなきゃ)
私はのそのそと立ち上がり、鞄に荷物を放り込んで部室をあとにした。