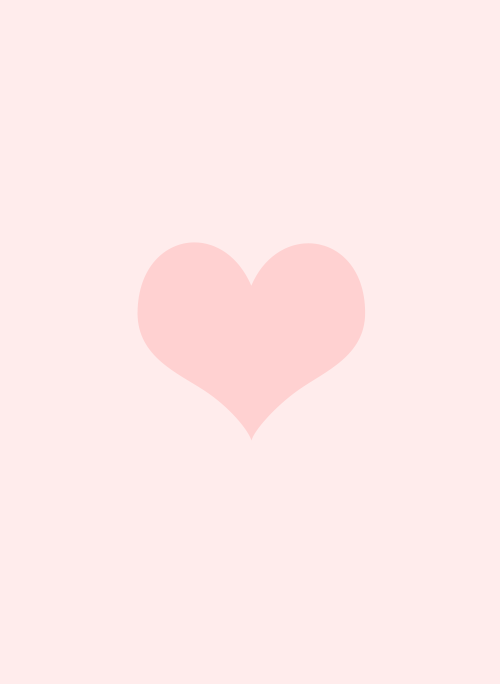まさかこれほど酷いとは――
再認識したミシェルという人物の性格に、三人は様々な意味でミシェルに恐怖心を感じるのだった。
◇◆◇◆◇◆
城に戻ると同時に、ルークは傷の手当てを受けていた。彼の手当てをしているのは、五十代前半の医師。その医師の見立てはエイルと同じで、数センチずれていたら失明していたというもの。
医師の言葉に、ルークの顔が歪む。片方の目の光が失われても生活に支障を来たすことはないが、現在の仕事に差し支える。剣が振るえないということはないが、距離感が上手く掴めない。
そうなると、お払い箱だろう。あの我儘ミシェルのもとから離れることができるという点では喜ばしいが、ルークは今の地位を捨てることができない理由もあった。だから、失明を免れたのは幸運だった。
治療を終えた医師はルークに化膿止めの飲み薬を手渡すと、道具を片付け部屋から出て行ってしまう。
医師の素っ気無い態度に、ルークは苦笑していた。しかし医師の態度は、わからなくもない。
相手は、クローディアの人間。エルバードのルークに冷たい態度を取るが、医師としての使命は別物と考えているので、このように傷の手当てをしてくれた。勿論、手抜きもしていない。
ルークは椅子から腰を上げ鏡の前に立つと、自分の姿を映す。ミシェルによって石を投げ付けられた箇所は、包帯が巻かれている。また、シードの剣によって斬られた箇所も、丁寧に手当てされている。
このように、怪我をしたのは本当に久し振りだった。シードが最強と呼ばれているように、ルークもまた最強の地位にいる。その腕前をかわれ、ルークはミシェルの守護者となった。
公子の守護者。
当初、その地位を喜んだ。
これで大金が稼げ、年老いた両親の面倒を見ることができると考えた。だが、現実は無常そのもの。
ミシェルの性格はあのようなもので、多くの側近を困らせていた。ミシェルはこのようなものと我慢をしていたが、正直疲れたというのが本音といっていい。だからシードに、自分が負けたいと願った。その結果、自分は敗者となったが、このように傷を負ってしまう。