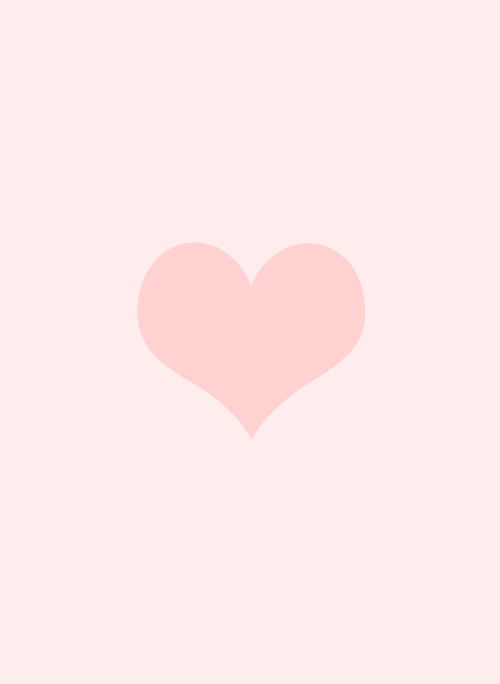息を吐くのさえ、ためらわれてしまう状況。姫野さんと私の顔を交互に見て、笠子主任は意を決したように目を閉じた。
「橘君は、茜口駅前のホテルグループの御子息だ」
一呼吸置いたあと、ぽつりと吐き出された言葉。できるだけ落ち着きを保った声なのに、全身が凍りつくような感覚に思考が停止しそうになる。
姫野さんが身を乗り出した。
「どういうことですか? 彼が今年一月入社の駅員ではなかったということですか?」
驚きとともに僅かな怒りの感じられる姫野さんの声に、停まりかけていた思考が引っ張られる。
本当なの?
ぽんっと頭の中に浮かんだのは、橘さんの笑顔。笑顔から彼のすべてが、するすると引き寄せられてくる。
偽りないと言った彼に、直接尋ねたい。
彼の口から、真実を聞かせてほしい。
「いや、我が社の社員には違いない。彼はプロジェクトに加わってもらうために入社した」
「それで、中途採用を募集していない時期の入社というわけですか?」
「そうだ、彼の帰国後に合わせた」
笠子主任と姫野さん会話を聞きながら、私は考えていた。
彼と初めて出会った日のことを。