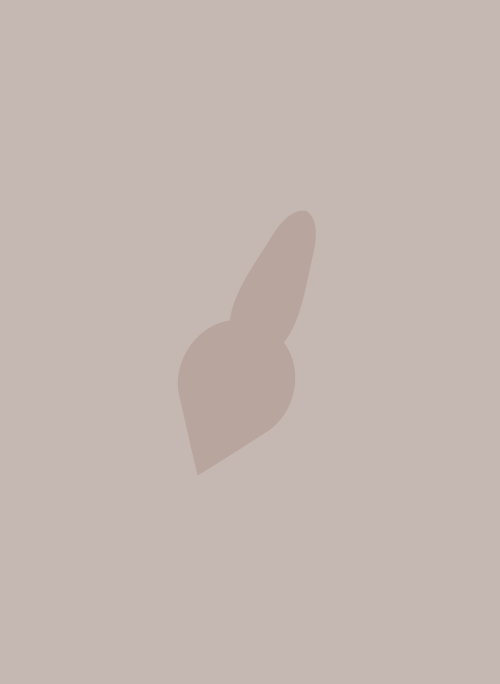「急に呼び出しちゃってごめんね」
廊下に出た佐伯はキョトンとした顔で自分を呼び出した相手を見ていた。
てっきり男の先輩だとばかり思っていたのに、相手は女の先輩だったのだ。
しかも、全く見覚えの無い、まるっきり面識のない相手。
「あ、いえ、大丈夫ですけど……」
「ちょっと、一緒に来てもらえる?」
「?」
誘われるがまま、佐伯は先輩の後をついて行く。
見慣れぬ上級生の女子と歩いていると目立つらしく、廊下にいる生徒たちが興味深そうに二人のことを目で追っていた。
その視線をいたたまれない気持ちで受けながら、
気にしないように視線を前へと見据えたまま廊下を歩く佐伯。
廊下を進み終わると、次は階段をのぼる。
2年の階を過ぎ、3年の階も過ぎ、
いったいどこまで行くのかと不思議に思っていた佐伯に、それまで無言で歩いていた先輩が声をかけた。
「こんなところまで連れ出しちゃってごめんね。
でも、やっぱり人がいないところがよかったから」
たどり着いたのは、屋上だった。
そこは普段なら生徒たちが何人かいる場所だが、
ただでさえ冬で肌寒いというのに今日は天気が悪いので
生徒は一人も来ていなかった。
まったく面識のない女の先輩に屋上に連れて来られて、多少の不審さを感じ始めた佐伯。
いったい何の用なのかとこちらから切り出そうとしたが、先に相手の方が口を開いた。
「急にこんなこと言うの、引かれちゃうかもしれないんだけど、
佐伯くんって、今、彼女とかいる?」
「いえ、いませんけど?」
「……そっか。
あの、あのね、私ずっと佐伯くんのこと気になってて、
いつも部活してるのとか、試合してるの見てて……。
全然話したことはなかったんだけど、
好き……になっちゃったんだ。
もし良かったら、付き合ってもらえないかな?」
「え?」
耳を疑った。
人から告白されるのは、生まれて初めてだった。
しかも学校が同じだとは言え、名前も知らない相手から。
普通、告白をされたら嬉しいものなのかもしれないけれど、
佐伯はただ驚きと戸惑いしか感じることができなかった。
「えっと、あの、それって、ホントにオレですか?」
思わず意味のわからないことを言ってしまった。
すると相手は一瞬キョトンと驚いた顔をしたが、すぐに優しくクスっと笑い、
「そうだよ。
佐伯くんが、好き。」
そう答えた。
頬を赤くしてはにかむ相手。
佐伯はどこか落ち着いた心境でその人のことを見つめた。
何もしなくてもモテそうな、可愛い顔。
風に揺れる長い茶色の髪。
綺麗な二重の目から伸びる長い睫。
薄ピンクの唇。
白い肌。
短いスカートからのびる、スラっとした形の良い細い足。
それは紛れも無く、思春期の少年なら憧れて手を伸ばしたくなる――女の子――だった。
少しも興味をそそられないわけではない。
こんなに可愛い人が、自分を好きだと言っている。
不快な気持ちになるわけではない。
なのに、
(なんでだろ……。全然ドキドキしない。)
鼓動は少しも反応しなかった。
心も、吸い寄せられることはない。
宮田になら、あんなに無防備に翻弄される鼓動と心。
なのに、今目の前にいる相手には少しも、何も、感じない。
痛感してしまう。
自分の心は、ひたすらに彼だけを追っていると。
無言で立ち尽くす佐伯に、先輩が躊躇いがちに話しかける。
「あの、返事聞かせてもらえるかな」
「あっ、すみません」
報われない相手にいつまでも想いを寄せていても、しかたない。
どんなに想ってもけして結ばれない。
そんな相手に執着していないで、こうして自分を好きだと言ってくれる人に逃げてもいいかもしれない。
最初は好きじゃなくても、一緒にいればいつか好きになれるかもしれないし。
付き合ってもいいのかもしれない。
付き合ったほうが、いいのかも。
そうすれば忘れられるかもしれないじゃないか。
この人が、忘れさせてくれるかもしれないじゃないか。
そう思う佐伯の脳裏に、よぎる笑顔。
“佐伯”
眩しく、真っ直ぐに自分に笑いかける宮田の笑顔。
けして薄れずに、消えずに、鮮やかに浮かぶ大好きな彼の笑顔。
佐伯は拳を握り、あまりに痛々しい震える声で答えた。
それは今にも泣き出してしまいそうな佐伯の心の叫びだった。
「すみません。
オレ、
好きな奴がいるんです」
その顔は泣き顔に変わりそうな笑顔。
様々な思いが詰まった、悲しい笑顔だった。
それを見た相手は自分がこれ以上何を言っても、その“好きな奴”には敵わないのだど悟った。
少し眉を下げながらも、佐伯に笑って見せる。。
「わかった。それなら仕方ないなぁ」
耳に髪をかけながら笑うその先輩は、佐伯にはとても大人っぽく見えた。
申し訳ない気持ちで「すみません」と謝る佐伯に、先輩は「いいよいいよ」と笑う。
そして次に、躊躇しながら ゆっくりと言葉を紡ぎ出してきた。
何か言いにくそうに、視線を揺らしながら……。
「あの、変なこと聞いてもいいかな。
もし違ってたら、ごめんね。
佐伯くんって、もしかして……その、あの子と付き合ってる……の?
同じサッカー部の、名前は――えっと、確か」
屋上の強い風が 佐伯を吹きつけた。
「ミヤタくん?だっけ……」
――ドクンッ――
(なんで――っ)
急に出てきた名前。
前触れ無く当たられてしまった自分の想い人。
佐伯はその瞬間、全身の毛が逆立つ気がした。
血が燃えるような感覚と、心臓を何かで絞め殺されるような衝撃。
誰にも気づかれていないと思っていたのに、どうして……。
「ご、ごめんね変なこと言って。
でも私、ホントにいつも佐伯くんのこと見てたから、
なんか、佐伯くん部活の時とかも宮田くんと一緒にいる時多いし、
それに、なんか雰囲気が友達って感じがしなくて……」
見られていた。
この人は、佐伯が密かに友情以上の眼で宮田を見ていた姿を、
見ていたのだ。
佐伯のことを想うが故に彼女は見つけてしまった。
佐伯の瞳に宿る友情以上のものを。
どんなに誰にも気づかれないようにと最善を尽くしても、強い想いで見つめてくる相手には通用しない。
佐伯もまさか誰かが自分のことをそんなに強い想いで見つめているとは思わなかった。微塵も思っていなかった。
少しの油断が、自らを危機に追い込んでしまった。
ドクドクと心臓が鳴る。握った拳に汗がジワリと滲むのがわかる。
動揺に揺れそうな声を必死に制御して、なんとか佐伯は言葉を返す。
「やだなぁ先輩。何言ってるんですか?
オレもあいつも“男”ですよ?」
――だから、付き合えるわけがない。
「人のことホモみたいに言わないでくださいよ~」
――オレは、“そう”かもしれないけど、
あいつは違う。
あいつは男を好きになったりしない。
だから、ここで笑い飛ばしてやらないと……
「男が男を好きになるなんて、」
――あいつのために、笑い飛ばしてやらないと、
あいつまで変な誤解をされてしまう。
「キモチワルイじゃないですか」
とてもおかしそうな顔と声で、笑った。
笑い飛ばした。
男が男を好きなる ということを。
キモチワルイと言ってやった。
純粋に宮田へ惹かれている自分をキモチワルイと笑い飛ばしてやった。
その胸がどれほどひどい音を立てて軋んだのか。どれほどの痛みを抱きながら、笑ったのか。それは佐伯以外、誰にもわからない。
自分だけしか知らない、誰にもわかってもらえない、孤独な痛みだった――。
「そ、そうだよね。
やだなー、私、なんか恥ずかしい。
ホントごめんね!」
「いえ、気にしないでください」
クスクスと笑っていた先輩が、フと綺麗に微笑みを浮かべながら優しく言う。
「……佐伯くん」
「はい?」
「好きな子と、うまくいくといいね」
その微笑に、同じような笑みで答える。
「ありがとうございます」
うまくいくはずがない と、心でうつむきながら……。