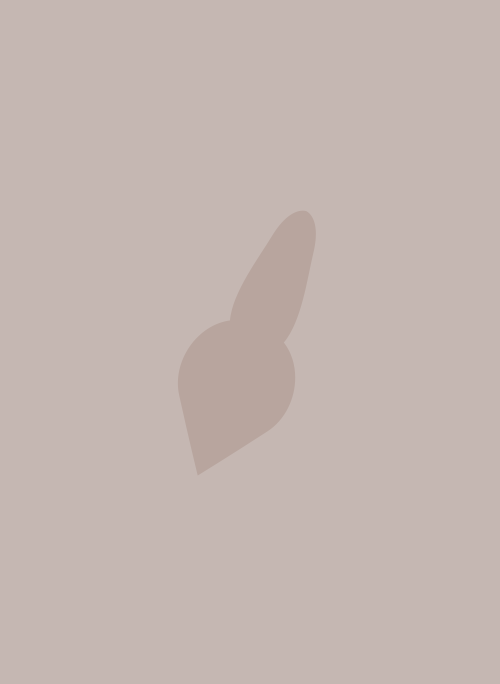――7年前――
「おーい佐伯~」
4限目終了のチャイムが鳴って1分後。
教室の扉を勢い良く開けて、佐伯の席に走りよって来たのは、
「宮田?どうしたの?」
佐伯とは違うクラスの宮田だった。
宮田はニコニコしながら片手に持っている何かをヒラヒラと小さく揺らして見せる。
それは青色の弁当箱だった。
「昼飯、オレも一緒に食っていい?」
その突然の頼みに、佐伯の体が僅かにびくつく。
宮田はいつも同じクラスの足立や村田と一緒に昼の時間を過ごしている。
二人と喧嘩でもしたのだろうかと心配になった佐伯は不思議そうな顔で聞いた。
「いいけど、あいつらはどうしたの?いつも一緒に食ってたよね?」
「それがさー、なんか二人とも部活のことで職員室行かなくちゃいけねーとか言ってさ。
“先に食ってろ”って言われたんだけど、教室で一人で弁当食うなんて寂しいじゃん!?
だから」
「あぁ、だからオレんとこに来たのか」
「そうそう」
言いながら、宮田は近くにある生徒のいなくなった椅子を拝借して佐伯の机にくっつけた。
ガタンっと音を立てて、宮田は佐伯の正面に座る。
周りの生徒たちも各自昼食の支度を始めているので、教室はガヤガヤと騒がしかった。
「やっぱ昼休みは友達と一緒にいたいもんなー。」
弁当を広げながらそう言った宮田。
その言葉に、佐伯の顔が一瞬曇る。
“友達”
宮田がなんとなしに放ったその言葉。
二人の関係を表す適切な言葉。
そう、宮田にとってはそれが適切な表現。
しかし、佐伯にとっては、
その表現は苦いものだった。
(ともだち…なんだよな、やっぱ。
宮田にとってオレはともだち。
それが当たり前なのに、
何でオレは、)
「そうだね。一人でいるより友達といた方が楽しいもんね」
(宮田を、ともだちと思えない……)
自分で自分を苦しめるようなことを言いながら、佐伯はにこりと笑った。
その胸に広がる痛みと、罪悪感を隠すかのように。
「あれ?そういえば高山は?」
あたりを見回し、いつも佐伯と一緒に昼食をとっている高山の姿を探す宮田。
「あぁ、4時間目の途中で具合悪くなっちゃって保健室行ったんだよ」
「マジで? 高山が具合悪くなるなんて珍しくね?」
「うん。
心配だからあとで見に行ってみるけど、宮田も一緒に来る?」
「あ、行く行く」
二人きりの昼休み。
男二人が向かい合って弁当を食べる。
昼休みの教室ならこんな光景はどこにでもあるもの。
しかし、それは佐伯にとってはとても貴重なもので。
日常生活からかけ離れた夢のような光景に見えた。
こうして二人で他愛の無い話をしながら、同じ時間をすごす。
目の前にいる相手が、自分だけを見て、自分だけに笑いかける。
それだけで胸が高鳴って、
たまらなく 苦しくなる。
募っていく想いと、それを冷たく見据える現実。
心と現実とが反比例して、うまく思考のバランスをとれない。
今にも溢れてしまいそうな想い。
手に、頬に、唇に、
触れたいと、触れてほしいと
熱を帯びていく感情。
しかしそれはけして許されない。
けしてしてはいけない。
――現実――
それがいつも背中を冷たくさせていく。
もしも、この想いを告げてしまったら、
もしも、この想いに気づかれてしまったら、
きっと二度と彼は自分に笑いかけてはくれない。
話しかけてはくれない。
こうして、共に時間を共有することなど
できなくなってしまう…。
そうなってしまうくらいなら、このまま彼が言う“友達”のまま痛みに耐えて笑っていた方が……いい……。
失うくらいなら、
これ以上の何かを求めたりはしたくない。
「おーい」
自分の思考に入り込み弁当につけていた箸の手を止めていた佐伯に宮田が首を傾げながら声をかける。
その声にハッとして佐伯は急いで笑顔を作った。
「え? なに?」
すると宮田は怪訝そうな顔をして答える。
「なに?じゃないよ。
俺が話してたこと、聞いてなかったっしょ?
弁当見つめたまんまボーっとして……、
なんか考え事でもしてたの?
……ていうか、何か悩んでるでしょ、佐伯」
核心をつくその言葉に、佐伯の瞳が動揺に揺れる。
しかしそれを笑顔で誤魔化して明るい口調で跳ね除ける。
「あはは。
そんなんじゃないって。弁当のおかず食う順番考えてただけだから。
話し聞いてなくてごめんな。
悪いけど、もう一回言って?」
そう言った顔は、完璧な笑顔だった。
なんの戸惑いも、切なさも感じさせない、完璧な笑み。
それなのに、宮田はハァっとため息を吐いて持っていた箸を置いてしまった。
その動作に佐伯の肩がビクつく。
(やば。感じ悪かったかな……)
相手の機嫌を損ねてしまったかと焦り、何か弁解の言葉を言おうとした時――
「佐伯ってさ、そうやって笑って誤魔化すとこあるよね」
いつもの宮田からは想像できないほどの真剣な眼差しを向けられた。
それはまるで佐伯の心を見抜こうとしているような眼。
佐伯は思わず息をのみ、必死にその視線から心を守ろうとした。
「何言ってんの? そんなこと言うなんて、宮田らしくな――」
「オレには話せないこと?」
「え」
珍しく言葉を遮られた。
遮られたというよりは、逃げるための言葉を無視されたような感覚。
逃げることは許さない、と言われているような気がした。
「佐伯が悩んでることは、オレには話せないことなの?」
宮田のゆっくりとした言葉と冷静な声が、心を追い詰めていく。
――何て言葉を返したらいい。
こういう時、どんな言葉を返せばいい。
まさかその悩みの種がお前なのだと言えるわけもない。
だからと言って、お前には話せることじゃないなんて冷たいことも言えない。
「……」
――だめだ。
早く、何か言わなくちゃ。
不審に思われる。
なんでもいいから、とにかくこの状況を抜け出せる上手い言葉を。
言え。
言え、早く。
加速していく鼓動に翻弄されながら、佐伯が口を開きかけた 瞬間――
「もしかして、
好きな子でもできた…とか?」
宮田が小さな声でそう言った。
――ドクッ
その言葉は、まさに佐伯の格そのものだった。
「え……?」
汗が滲む。
シャツが背中に張り付いて、気持ちが悪い……。
教室のざわめきが遠のいていく。
うろたえを隠すように浮かべられた佐伯の苦笑。
その顔を見て、宮田は確信したように言った。
「図星だろ~。
その女子、他に付き合ってる奴がいるとかなの?」
「……あ、いや、そういう、わけじゃ」
――ちがう 女子なんかじゃない。
「じゃあ好きな奴がいるとか?」
「わかんない……もしかしたら、いるかもしれないけど……」
「そっか~。その子とは結構仲良くなってんの?」
「……。」
「佐伯?」
「向こうも、オレのこと……ともだち、くらいには思ってくれてる」
“友達”
それは、さきほど宮田が言った言葉。
佐伯と宮田の関係を表す 残酷な言葉。
「じゃあ上手くいく可能性あんじゃん。
まずは友達からスタートして、そのうち恋人になれっかも――」
「はは……笑わせないでよ」
佐伯の口から、まるで宮田を馬鹿にするかのような嘲笑いが漏れる。
鼻で笑い、皮肉の笑みを浮かべて……。
「恋人? そんなの、無理に決まってんじゃん」
見たことの無い佐伯の顔に、宮田は一瞬眼を見開いて息をのんだ。
冷たく見放すような佐伯の嘲笑。
それは、佐伯が自分自身に向けて浮かべたものだった。
“無理に決まっている”
そう自分自身へ言う。
自虐の笑みで自分を嘲笑う。
自分の想いを、嘲笑う。
こんな想いは無駄で愚かなもの。
現実の前では脆く簡単に壊れてしまうもの。
それなのに……それでも……
消えてはくれない、想い。
「バカだよな……オレって」
そう零した佐伯の笑顔に悲しみが隠れているような気がして、宮田は「なんでそんな顔すんの?」と聞こうと口を開いたが、
「佐伯~」
突然横から誰かに声を挟まれてしまった。
それまで二人だけの緊迫した空気に身をおいていた二人は、一気に現実の和やかな昼休みの教室へと引き戻される。
声のした方を見ると、ドアに一番近い席に座っている生徒が手招きをしている。
「? なに?」
席を立ってその生徒の方へ歩み寄る佐伯。
するとその生徒は廊下の方を指差して「なんか先輩が呼んでるぜ」と言った。
「先輩?
オレ上級生に知り合いなんていないけど」
「でもオレにお前のこと呼んでくれって言ってきたんだよ。
なんか用があんだろ。行ってやれよ。」
「うん。誰だろ」
不思議そうに首を傾げながら、佐伯は廊下に出て行った。
宮田はその後姿を眼で追ったが、そこからは廊下にいる人物を見ることはできなかった。
「……さっき、なんであんな顔したんだろ」
一人になった席で、佐伯の全く手のつけられていない弁当を見つめながら独り言を零す。
頬杖をついて先ほど交わした会話を頭で回想させる。
何かを隠す時に見せる笑顔。
うろたえた顔。
嘲笑うかのような、自虐のような 冷たい顔。
悲しそうな笑顔。
宮田は思い出せば出すほど、佐伯の心を理解することができなかった。
好きな子ができたら もっと顔を赤くしたり、嬉しそうな顔したりするはずなのに。
いくら片思いだとは言え、人を好きになれたらそれだけで楽しくて幸せな気持ちになるはずなのに。
なぜ彼はあんな顔で 無理に決まっている と言ったのだろう。
“バカだよな…オレって”
そう言ったあの笑顔は、まるで死んだ相手に恋をしているかのようだった。
どんなに想っても、けして届くことはない、報われることはない。
そんな恋をしているかのようだった……。
「佐伯の好きな子って、どんな子なんだろ」