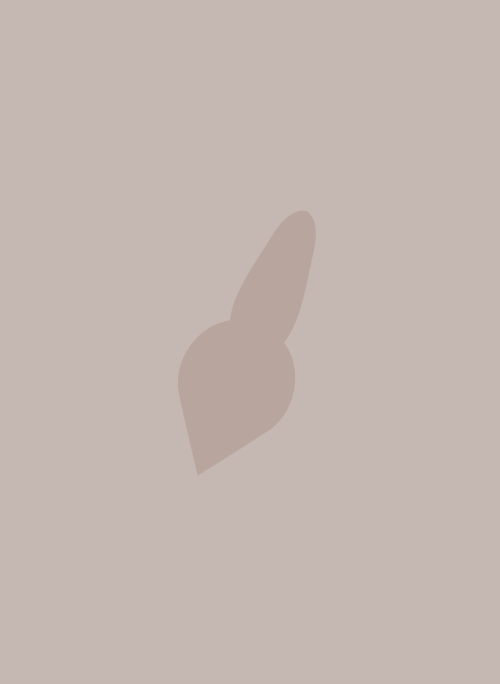そう、呼んだのはほとんど無意識だったけれど。
次の行動に移る時にはこうすべきだったのだ、という確信らしきものがわいてきていた。
「どうしたの?・・あっ!ダメ! 」
ミユウはアキの首元に手を伸ばす。
「っ・・」
触れた瞬間、指先に焼けるような痛みが走った。
ふたりに悟られないよう、咄嗟に左手を背中に隠す。
利き手を使わなくて、良かった。なんて、悠長なことを考える合間にも手はじんじんと痛みを訴えていた。
「ミユウ、何てことを!」
アキは呆然としてその場で動けないでいる。
「手を、見せなさい。」
お兄ちゃんもいつになく厳しい声色だが、今は痛みをこらえるので精一杯だ。
アキとは別の理由で動けないミユウだが、それでも懸命にどうやって傷を隠すか頭を働かせていた。