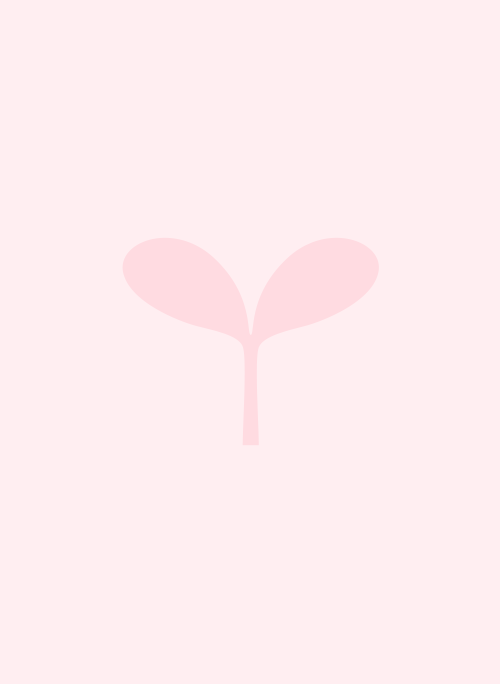部屋にいた数人があたしを見る。興味ありませんとばかりに前を向いたままの人や、うつむいたままの人もいるが、そんな事は気にしていられない。
あたしはこの館の情報を集めるため、そしてここにいる人たちの詳細を知るために、一人一人に話し掛ける事にした。
最初に声をかけようと思ったのは、髪を結ぶ大きなリボンとダブルブレストのジャケットがよく似合う女の子。どこかで見たような気がするが、思い出せない。
近くまで行き、声をかけようとすると、向こうから声をかけられた。
「はじめまして。私はサクラ=ドゥッルです。よろしくね」
「……サクラ…って、もしかして人気アイドルの?」
「うん、そう言われてるみたい。私としてはまだまだって感じなんだけど」
名前を言われて思い出した。目の前にいるこの少女は、今をときめく人気アイドルだ。相手が大御所だろうが政治家だろうが、思った事はハッキリと言う性格で男女問わずファンが多い。
「名前、教えてもらっていいかな?長い付き合いになりそうだし」
「長い付き合い?」
「うん、何となくね。そんな気がする」
サクラはあたしの目を見つめて、少し険しい表情でそう言った。
「…あたし、熱炉夏。気軽に呼んでね」
「じゃあ、夏ちゃんって呼ぶね。私もサクラでいいから」
あたしはサクラと握手を交わし、次の相手の元へと向かった。
次に話し掛けたのはすらっとした女の人と、いかにも危なそうな感じの男の人。女の人は楽しそうに男の人に話し掛けているが、男の人は応えるどころか頷きもしていない。
「ちょっといいかな?良かったら自己紹介を………」
「いいわよ、どうぞ」
あたしの呼び掛けに応えたのは、もちろん女の人。男の人は、こちらを向こうともせずに腕組みをして目を閉じている。
「熱炉夏です。夏って呼んでね」
「うん、夏ちゃんね。私はイリーナ=セシナです。知ってる?」
「うーん、すっごく綺麗だけど、もしかして女優さん?」
もしかしてサクラと同じ芸能人なのだろうか、と思い答えてみたが、残念そうに眉をひそめているのを見る辺り、外れているようだ。
「新体操とか興味ある?フィギアスケートとかは?」
「新体操に関係あるんだ?もしかしてオリンピック選手だったりして」
「ええ、ロシア代表の。思い出した?」
冗談のつもりで言ったのだが本当らしい。それなら世間では有名なのだろうが、あたしは新体操などのスポーツは興味が無いし、オリンピックも見たことがない。
「ごめん、やっぱり知らないや」
「そっか。じゃあ、これから知っていってもらおうかな。よろしくね」
イリーナはにこりと笑った。全てが浄化されるような、そんな笑顔だった。
宝石のような青い瞳に白い肌、絹糸より美しいウェーブのかかったプラチナブロンドと、かなり整った容姿をしている。
こんな女性が笑顔を見せれば、それこそ何だって浄化されるだろう。それほどまでに綺麗な人だった。
「せっかくだし、彼にも自己紹介したらどうかしら」
イリーナは、先程まで話していた男の人をあたしの前に引っ張り出してきた。男の人はウンザリといった感じで、あたしの前に立っている。
「……デニスだ」
横一文字に結ばれていた唇が少しだけ開いた。やる気が無いのか、無愛想なのか。どちらにしろフレンドリーな人ではない。
「熱炉夏です…」
相手のやる気無さに応えるように、自己紹介を手短に済ませた。このデニスという彼が、どういう人物なのか知る気にはなれないし、こちらが聞いても答えてくれないような気がする。
あたしは二人の元を去り、次の相手の元へ向かった。
四人目はピアスを大量に付け、前髪を赤や青で染めている派手な男の子。頻繁に周囲の人に声をかけては適当にあしらわれている。
話しかけるのに忙しさそうだし、後回しにしようかと思っていたら、その男の子は物凄い勢いであたしの方に走ってきた。
「え、えっと、なにかな?」
「ここはどこっすか?俺、なんも悪いことしてないのに……」
よく見ると男の子の目には涙が滲んでいた。おそらく、あたしと同じで目が覚めたらここにいて、訳もわからずパニックになっているのだろう。
「落ち着いて、一人よりマシだって。他にも同じ状況の人、周りにいるでしょ」
「もしかして君も?目覚めたらパイプベッドの上っすか?」
「そういうこと」
男の子は自分と同じ状況の人がいたことで、少しは安心したのか安堵の表情を見せたため、あたしは本題に入った。
「はじめまして。あたし、熱炉夏。名前教えてくれるかな?」
「あ、そうっすね。名前言わないと。俺はエドヴァルド=セダール=ゲーテっす」
「ヨーロッパ人なの?」
いかにもヨーロッパといった感じの名前だったので、なんとなく聞いてみたのだが、彼は少し困った様子で周囲を確認し始めた。そして、あたしに耳を貸すよう言う。
「日本人っす。本当は六万冠一浪って言うんすけど、これ内緒っす」
「じゃあ何でエドヴァルドなのさ」
「ペンネームにだけ使うつもりだったんすけど、気に入っちゃって。普段の名前としても使う事にしたっす」
「ペンネーム?」
漫画でも書いているのだろうか。装飾品が多く、派手な見た目からは想像もつかない。どちらかといえば、バンドでボーカルでもやっていそうなものだが。
「はい、これでも自分、詩人っすから」
「詩人?」
まだ、漫画を描いていると言われた方が驚かなかった。あろうことか、この目の前にいる派手な少年は詩人だと言うのだ。
「こないだ詩集仕上げたっす。もう忙しくって」
本人は何でもない事のように語っているが、あたしはいまだに驚きを隠せない。
「詩人って感じ、しないね。何で詩人になろうと思ったの?」
あたしは浮かんだ疑問を素直にぶつけた。しかし、エドヴァルドは何も話そうとはしない。何か事情があるのだろうかと思い、あたしは発言を撤回した。
「やっぱりいいや。あたし、行くね」
「あ、はい。さよならっす」
ばつの悪さを忘れようと、素早くエドヴァルドの元を去った。