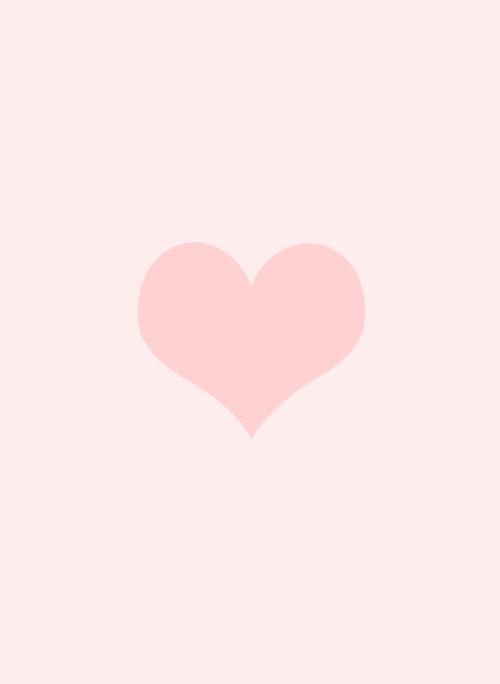「宿題がやっと全部終わったのでどこか遊びにでも行きませんか」
八月に入ってわずか数日を迎えただけの高校生にしては、少々異様なお言葉だった。
私は、若干の波乱とともに高校生初めての一学期を終えたものの、思いのほか学校という枷を抜け出したことにより早く立ち直ってしまった。
それで、夏休みの最初の一週間を主に惰眠とネットサーフィンで構成していた。
母親に嫌がられながら昼前に布団から這い出し、ブランチにそうめんをすすり、一家一台のパソコンを午後中独占する。母親の機嫌を調整するために夕食の準備を手伝い、その後は風呂洗い。
家事手伝いによって突入した真面目モードを利用して少々宿題などに手を付けるも、やっぱりやる気が出ないので、すぐに携帯をいじりだすか布団に潜り込む。
完全にダメ人間のそれである。
そんな矢先に、渡部さんから携帯に電話がかかってきて冒頭のお言葉をいただいたのだった。
実のところ、これまで渡部さんと遊びに行ったことなどなかったので私は電話越しに二つ返事で頷いた。
私も終わってないけど遊びたい。
渡部さんは、私の宿題の進行状況を聞くと一瞬電話口で沈黙したが、遊ぶのをやめるという判断はしなかった。足立くんと佐伯くんも誘うようだ。
「三人以上だと連絡を行き渡らせるのも面倒なので、実里くんの家に一度集まりましょう」
「うん、分かったーーー毎度思うけどさ、あの家すごく使い勝手いいよね」
「実里くんのところ、共働きですからね。親がいないと気楽ですよね。家自体もまあまあ広いし、親戚の方がある程度集まるときはだいたいあの家になるらしいですよ」
「そういえば私、足立くんの伯父さんたちの分のケーキ3回ぐらい食べてるな」
「くだんの伯父さま達は二つ隣の県民らしいので、微妙にアクセスしやすいそうです」
じゃあ、伯父さん達は足立くん一家が好きなのかもな。
兄妹のなかで一番穏やかな好己さんですら「嫌」と称するその親戚のことが、ふとした時に気になる。
「そういえば浅野さん、実里くんとは一日で仲直りしていたようですね」
「え、まあ・・・どうにかなった」
「実里くん、なんだかあの日学校をかけずり回っていたのか知りませんが上履きを信じられないぐらい汚して、亨くんに豚を見るような目で見られたって」
あら、あの弟も潔癖な遺伝子持ちだったか。
それにしてもその日のことを言われるとなんだか気恥ずかしいものだ。
そうか、足立くんに会うのも少し久しぶりである。
八月に入ってわずか数日を迎えただけの高校生にしては、少々異様なお言葉だった。
私は、若干の波乱とともに高校生初めての一学期を終えたものの、思いのほか学校という枷を抜け出したことにより早く立ち直ってしまった。
それで、夏休みの最初の一週間を主に惰眠とネットサーフィンで構成していた。
母親に嫌がられながら昼前に布団から這い出し、ブランチにそうめんをすすり、一家一台のパソコンを午後中独占する。母親の機嫌を調整するために夕食の準備を手伝い、その後は風呂洗い。
家事手伝いによって突入した真面目モードを利用して少々宿題などに手を付けるも、やっぱりやる気が出ないので、すぐに携帯をいじりだすか布団に潜り込む。
完全にダメ人間のそれである。
そんな矢先に、渡部さんから携帯に電話がかかってきて冒頭のお言葉をいただいたのだった。
実のところ、これまで渡部さんと遊びに行ったことなどなかったので私は電話越しに二つ返事で頷いた。
私も終わってないけど遊びたい。
渡部さんは、私の宿題の進行状況を聞くと一瞬電話口で沈黙したが、遊ぶのをやめるという判断はしなかった。足立くんと佐伯くんも誘うようだ。
「三人以上だと連絡を行き渡らせるのも面倒なので、実里くんの家に一度集まりましょう」
「うん、分かったーーー毎度思うけどさ、あの家すごく使い勝手いいよね」
「実里くんのところ、共働きですからね。親がいないと気楽ですよね。家自体もまあまあ広いし、親戚の方がある程度集まるときはだいたいあの家になるらしいですよ」
「そういえば私、足立くんの伯父さんたちの分のケーキ3回ぐらい食べてるな」
「くだんの伯父さま達は二つ隣の県民らしいので、微妙にアクセスしやすいそうです」
じゃあ、伯父さん達は足立くん一家が好きなのかもな。
兄妹のなかで一番穏やかな好己さんですら「嫌」と称するその親戚のことが、ふとした時に気になる。
「そういえば浅野さん、実里くんとは一日で仲直りしていたようですね」
「え、まあ・・・どうにかなった」
「実里くん、なんだかあの日学校をかけずり回っていたのか知りませんが上履きを信じられないぐらい汚して、亨くんに豚を見るような目で見られたって」
あら、あの弟も潔癖な遺伝子持ちだったか。
それにしてもその日のことを言われるとなんだか気恥ずかしいものだ。
そうか、足立くんに会うのも少し久しぶりである。