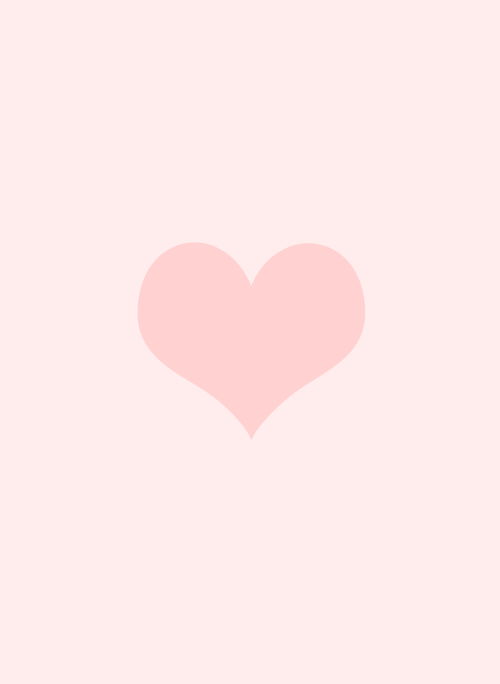「あははははははっ、しょうもなさすぎる!」
「・・・・・」
「さぞかし重大な事件かと思ったらそれ!?足立くんってちょっとバカなんじゃない!?」
「バカ言うな。なに笑ってんだおまえ。人がせっかくーーー」
「やめてよね、それ打ち明け話って程度になってないから!」
「くっそ、なんでこうなるんだ・・・」
足立くんは悔しそうに手元の本を睨みつける。
その光景すらおかしくてしょうがない。
「真に受ける渡部さんも渡部さんだよね!相談相手変えなよー!」
「なんでみんな笑うんだ。十分深刻な話題だろ、これ」
「みんな・・・?」
「中学生くらいの頃、由美のとこのおばさんに『あの子実里くん以外に友達いないみたいなのよね』とか言ってきたから、さっきの話して頭下げたことある。見た事もないくらい笑われた」
「もう、その話がきついわ」
想像したのが間違いだった。
私は、今度こそ笑いが止まらなくなる。
「帰って好己に言ったら手を叩きながら死ぬほど笑われた」
「うわ、手叩いちゃうんだ好己さん」
腹を抱えて笑う私を、足立くんは睨みつけたが、どことなく恥じらいが伴われていた。
ぜんっぜん怖くない。
怖くないのだが、足立くんが恥じらいに任せて図書室の大切な蔵書を私に向かって振り上げてくる。
なので、やっとのことでこらえた。
「足立くんは、気にしなくていいと思うよ、そのこと」
「いや、でも・・・」
「渡部さんだってきっと気にしてないよ」
「友達ができなかった事は気にしてると思うぞ」
「でも、十数年足立くんは見捨てずについててくれたんでしょ。けっこう頼りになってるんじゃないかな」
足立くんの話を咀嚼してみると、その点では確かに尊敬できるかも。
相談だって、自分なりにちゃんと考えてこたえてたんだしね。
まあ、ボケとしか思えないけど。
「私、今の渡部さん好きだよ。面白いし。友達になれてよかった」
「・・・そっか」
私の言葉に、足立くんはようやく安心したように、笑みを漏らした。
初めて見るその表情に、少しだけ私にも安心したような温かさが伝わった。
「・・・・・」
「さぞかし重大な事件かと思ったらそれ!?足立くんってちょっとバカなんじゃない!?」
「バカ言うな。なに笑ってんだおまえ。人がせっかくーーー」
「やめてよね、それ打ち明け話って程度になってないから!」
「くっそ、なんでこうなるんだ・・・」
足立くんは悔しそうに手元の本を睨みつける。
その光景すらおかしくてしょうがない。
「真に受ける渡部さんも渡部さんだよね!相談相手変えなよー!」
「なんでみんな笑うんだ。十分深刻な話題だろ、これ」
「みんな・・・?」
「中学生くらいの頃、由美のとこのおばさんに『あの子実里くん以外に友達いないみたいなのよね』とか言ってきたから、さっきの話して頭下げたことある。見た事もないくらい笑われた」
「もう、その話がきついわ」
想像したのが間違いだった。
私は、今度こそ笑いが止まらなくなる。
「帰って好己に言ったら手を叩きながら死ぬほど笑われた」
「うわ、手叩いちゃうんだ好己さん」
腹を抱えて笑う私を、足立くんは睨みつけたが、どことなく恥じらいが伴われていた。
ぜんっぜん怖くない。
怖くないのだが、足立くんが恥じらいに任せて図書室の大切な蔵書を私に向かって振り上げてくる。
なので、やっとのことでこらえた。
「足立くんは、気にしなくていいと思うよ、そのこと」
「いや、でも・・・」
「渡部さんだってきっと気にしてないよ」
「友達ができなかった事は気にしてると思うぞ」
「でも、十数年足立くんは見捨てずについててくれたんでしょ。けっこう頼りになってるんじゃないかな」
足立くんの話を咀嚼してみると、その点では確かに尊敬できるかも。
相談だって、自分なりにちゃんと考えてこたえてたんだしね。
まあ、ボケとしか思えないけど。
「私、今の渡部さん好きだよ。面白いし。友達になれてよかった」
「・・・そっか」
私の言葉に、足立くんはようやく安心したように、笑みを漏らした。
初めて見るその表情に、少しだけ私にも安心したような温かさが伝わった。