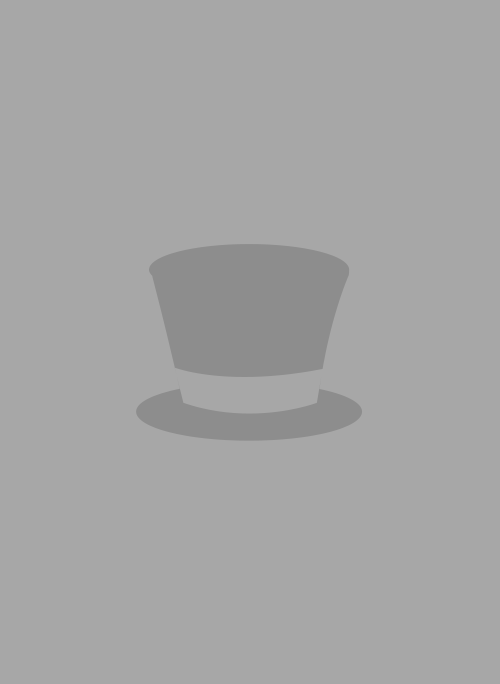「そう」と彼の口から紡がれるその何ともない言葉にドキドキと心拍数が加速する。
ど、とうしたんだ、私!
何か分からないけど、梶木君の匂いに惑わされ過ぎてる気がする。
心拍数が加速する一方で、頬が火照ってくるのもそのせいだ。
「あっ、梶木君が運んでくれたんだよね!保健室まで」
今、思い出した風にそう口にするのは、自分の火照っている頬を梶木君に見られたくないから。
真っ赤になった顔を彼が馬鹿にするのなんて目に見えている。
と言っても、お礼が言いたかったってのも本音。
「それが?」
「ありがとう、梶木君」
どうでもよさそうな彼に向かってお礼を言えば、プイッと私から視線を逸らす梶木君。
な、何故に逸らされた!?
そんな疑問は直ぐに梶木君の口から出た言葉によって解消する。
「森山さん。今の顔、……他の人には見せないでね」
「えっ!何で!?」
「不細工過ぎるからに決まってるでしょ」
納得する理由だけど、納得したくない。
仮にも女子高校生に向かってその言葉は酷過ぎる。
「酷っ!」
「煩いよ、森山さん」
声を大にして突っ込めば、冷静にいなされる。
梶木君の中での私の位置は一生上がる事は無いのかもしれない。
ぼけっとそんな事を考えながらその場に突っ立っていると、
「はい」
という台詞と共に、私へと差し出される私の鞄。
やる気のなさそうな感じなのに、梶木君が私の鞄を持ってきて差し出してくれたらしい。