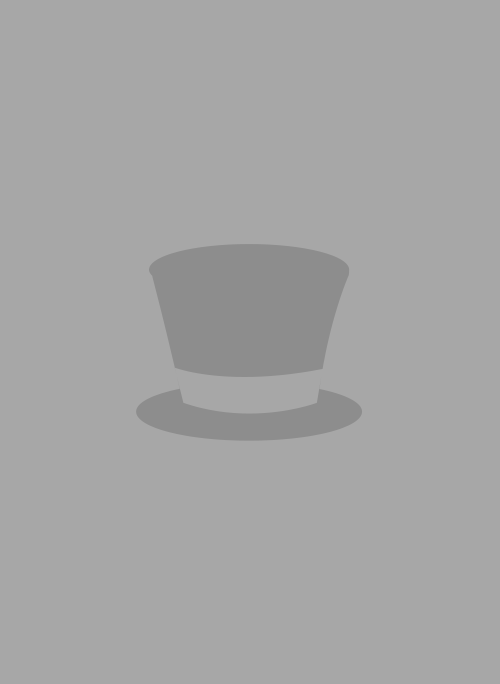口を少し開ければ、口へと流れ込んでくるしょっぱい味。
「わ、…私がこんな大切な事聞いて…良かったの…かな……」
おばあちゃんに聞いている様で、自分に問い掛けているその言葉が頭の中を占めていく。
ここに来たのは梶木君の事を聞きに来たから。
でも、こんなに皆が悩んでいて大切な事を、明らかに無関係の私が聞いても良かったんだろうか。
私は……、梶木君が好きで。
私は、梶木君のおばあちゃんも好きで。
それでも、端から見たら梶木君の家族とは無関係なんだ。
そんな私なんかが、聞いちゃいけない事だったんじゃないだろうか。
「私はね、泉ちゃんだから話したんだよ」
霞む視界で捉えたおばあちゃんの顔は目を細め優しく微笑んでいて、私が今悩んでいる事を吹き飛ばす。
「私……だから?」
「そう。泉ちゃんだからだよ」
「どういう…事?おばあちゃん?」
私の問い掛けにフフッと笑って、
「ばあさんっていうのは何でも知っているものさ」
そう言葉を放つ目の前のおばあちゃんは、もうそれ以上何も答えてくれないんだろう。
私だから話した…か。
特に何も説明も無いけれど、駄菓子屋のおばあちゃんがそう言うのだから、私が聞いても良かったんだと思わせられる。
泣き続ける私へ白いハンカチを差し出してくれるおばあちゃんの手は骨ばっていて皺だらけ。
それが無性に温かく感じた。