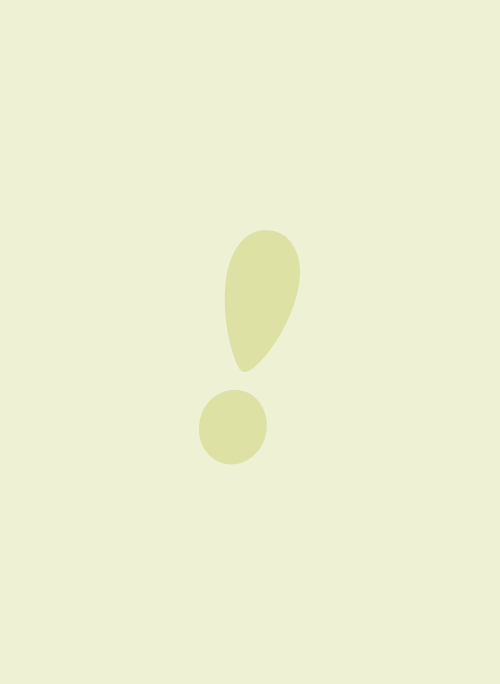「わしの母は三歳の時に死んだ。位は低いが桐壷の更衣という。
わしは何のことかよくわからなかったが父の桐壷帝は見る影も
なく落ち込んでいたようじゃ。あまりの落ち込みように周りは必死で
生き写しの姫君を探した。それが藤壺、御君の母じゃ」
冷泉院は身を乗り出して聞き入っています。今日こそ事の真相が知れる。
院がごくりと唾をのむ音が聞こえてきそうです。お市もおくどで手を止め、
入り口戸で背を向けて立っている惟光もじっと聞き耳を立てています。
「美しかった。わしより五歳年上で周りからは母桐壷にそっくりといわれ
十二でわしが元服し葵上を迎えてももう心は藤壺だったなあ。そりゃそう
じゃろう、継母とはいえ宮中で姉弟のように育ったからじゃ。人恋初めじゃ」
「初恋?」
「ああ、強烈な初恋じゃ。わしが十八、宮が二十三もう身体はとまりゃせん。
王命婦をかき口説いてついに手びいてもらった。しかし胸のときめきが大き
すぎて何が何だか覚えていない。二度目は三条邸に下がっておられた時この時
の事はよく覚えている。一瞬一瞬が夢の様じゃった。この時に君が宿ったんじゃ」
老いたる源氏はここでようやく我に返って酒をそそぎます。
冷泉院は息づまる思いだったのかここで大きく深呼吸をします。
お市も賄をはじめ惟光も息を抜いて首を動かします。
「しばらくして宮ご懐妊のうわさが広がった。そりゃひやひやもんよ。
まさか?宮も同じ心地じゃったろう。宮中ではことさら会わぬようにした。
しかしまぬがれぬ、紅葉賀の試楽は宮のために舞った、思いっきり宮の前で」
「今でも語り草になっております」
「しかし年が明けても子は生まれぬ。とにかく宮の安産を、必死で祈った。
おそらく宮中も世間の民もみな祈っていたと思うあの時は。二か月遅れで
やっと生まれた玉のような男君。それが御君じゃというわけよ」
「そのことは女房達からよく聞きました。遅れているのは物の怪の仕業とかで
大掛かりな加持祈祷が連日あちこちで行われていたとか」
「そうよ、君はわしの弟。わしは母方の身分が低く皇太子にはなれぬが君は
次の次の帝になれる身、父桐壷帝はことのほか喜ばれた。わしもうれしかった」
冷泉院は笑みを浮かべて源氏を見つめます。年は老いても気品は高く、見えぬ
開いたまなざしもやわらかで声はそれこそ昔の儘で艶(つや)があります。
わしは何のことかよくわからなかったが父の桐壷帝は見る影も
なく落ち込んでいたようじゃ。あまりの落ち込みように周りは必死で
生き写しの姫君を探した。それが藤壺、御君の母じゃ」
冷泉院は身を乗り出して聞き入っています。今日こそ事の真相が知れる。
院がごくりと唾をのむ音が聞こえてきそうです。お市もおくどで手を止め、
入り口戸で背を向けて立っている惟光もじっと聞き耳を立てています。
「美しかった。わしより五歳年上で周りからは母桐壷にそっくりといわれ
十二でわしが元服し葵上を迎えてももう心は藤壺だったなあ。そりゃそう
じゃろう、継母とはいえ宮中で姉弟のように育ったからじゃ。人恋初めじゃ」
「初恋?」
「ああ、強烈な初恋じゃ。わしが十八、宮が二十三もう身体はとまりゃせん。
王命婦をかき口説いてついに手びいてもらった。しかし胸のときめきが大き
すぎて何が何だか覚えていない。二度目は三条邸に下がっておられた時この時
の事はよく覚えている。一瞬一瞬が夢の様じゃった。この時に君が宿ったんじゃ」
老いたる源氏はここでようやく我に返って酒をそそぎます。
冷泉院は息づまる思いだったのかここで大きく深呼吸をします。
お市も賄をはじめ惟光も息を抜いて首を動かします。
「しばらくして宮ご懐妊のうわさが広がった。そりゃひやひやもんよ。
まさか?宮も同じ心地じゃったろう。宮中ではことさら会わぬようにした。
しかしまぬがれぬ、紅葉賀の試楽は宮のために舞った、思いっきり宮の前で」
「今でも語り草になっております」
「しかし年が明けても子は生まれぬ。とにかく宮の安産を、必死で祈った。
おそらく宮中も世間の民もみな祈っていたと思うあの時は。二か月遅れで
やっと生まれた玉のような男君。それが御君じゃというわけよ」
「そのことは女房達からよく聞きました。遅れているのは物の怪の仕業とかで
大掛かりな加持祈祷が連日あちこちで行われていたとか」
「そうよ、君はわしの弟。わしは母方の身分が低く皇太子にはなれぬが君は
次の次の帝になれる身、父桐壷帝はことのほか喜ばれた。わしもうれしかった」
冷泉院は笑みを浮かべて源氏を見つめます。年は老いても気品は高く、見えぬ
開いたまなざしもやわらかで声はそれこそ昔の儘で艶(つや)があります。