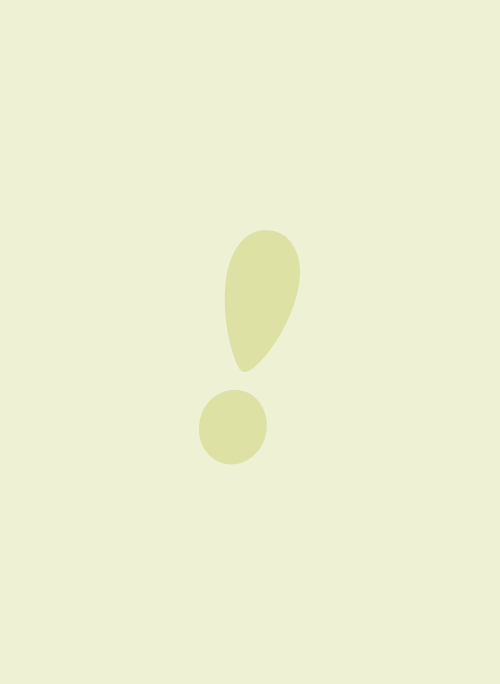「だれにもまねのできないお父様の唯一の取り柄ですね」
「そう言うな。唯一ということはなかろう?」
微笑みながら中宮は老いたる源氏を困らせます。
「だけどほんとはお父様の養女にしていただいて心の底から
感謝いたしております」
「そうそう、そう言えばさらに美しさが増すというものよ」
老いたる源氏はやっと一息ついて膳に手を出そうとします。
そこに松茸のいい香りがします。
「いい匂いじゃなあ」
お市も惟光も源氏も中宮もみんな鼻をくんくんとさせています。
「今日は一つだけ父上に聞きたいことがございます」
中宮は松茸の切り身にたっぷりと酢を染ませて源氏の口に運びます。
「(もぐもぐ)ひとつだけ?」
「ええ、ひとつだけ」
「・・・・・」
「母とはどういう付き合いだったのでしょうか?」
「何も聞いておらんのか?」
「いとしいお方というばかりで、どこがいいのかどうしてそうなったのかは
一度も聞いたことがございません」
「若き頃、六条の御息所は我ら若者のあこがれの的じゃった。東宮亡き後
つまり、ほんとは皇后になられたお方。今の六条院の秋の邸宅はすべて
御息所のお屋敷やった。そこに当時の若者は競って集いあった。楽曲、
歌詠み、舟遊び。ついにそこで御息所はこのわしに目を止められたのよ」
「源氏殿の若き頃は玉のようないい男。そう申しておりました」
「ところがわしは一番年下で妻の葵上もお前は知ってか藤壺も五歳上。
御息所は何と七つ上。何かと引け目もあったようじゃ。一番の実力者で
教養豊か誇りも高かったから、恨まれたら逃げようがない」
「野々宮で?」
「そう、夕顔と葵上の怪死はどうも御息所の怨霊のようじゃった。
そう告白なされた。いとおしいお方じゃったよ」
「愛しておられた?」
「もちろん。世が世であれば結ばれていたやもしれぬ」
老いたる源氏はおよよと涙を流します。
中宮はにじり寄って源氏の涙をぬぐいます。
「そう言うな。唯一ということはなかろう?」
微笑みながら中宮は老いたる源氏を困らせます。
「だけどほんとはお父様の養女にしていただいて心の底から
感謝いたしております」
「そうそう、そう言えばさらに美しさが増すというものよ」
老いたる源氏はやっと一息ついて膳に手を出そうとします。
そこに松茸のいい香りがします。
「いい匂いじゃなあ」
お市も惟光も源氏も中宮もみんな鼻をくんくんとさせています。
「今日は一つだけ父上に聞きたいことがございます」
中宮は松茸の切り身にたっぷりと酢を染ませて源氏の口に運びます。
「(もぐもぐ)ひとつだけ?」
「ええ、ひとつだけ」
「・・・・・」
「母とはどういう付き合いだったのでしょうか?」
「何も聞いておらんのか?」
「いとしいお方というばかりで、どこがいいのかどうしてそうなったのかは
一度も聞いたことがございません」
「若き頃、六条の御息所は我ら若者のあこがれの的じゃった。東宮亡き後
つまり、ほんとは皇后になられたお方。今の六条院の秋の邸宅はすべて
御息所のお屋敷やった。そこに当時の若者は競って集いあった。楽曲、
歌詠み、舟遊び。ついにそこで御息所はこのわしに目を止められたのよ」
「源氏殿の若き頃は玉のようないい男。そう申しておりました」
「ところがわしは一番年下で妻の葵上もお前は知ってか藤壺も五歳上。
御息所は何と七つ上。何かと引け目もあったようじゃ。一番の実力者で
教養豊か誇りも高かったから、恨まれたら逃げようがない」
「野々宮で?」
「そう、夕顔と葵上の怪死はどうも御息所の怨霊のようじゃった。
そう告白なされた。いとおしいお方じゃったよ」
「愛しておられた?」
「もちろん。世が世であれば結ばれていたやもしれぬ」
老いたる源氏はおよよと涙を流します。
中宮はにじり寄って源氏の涙をぬぐいます。