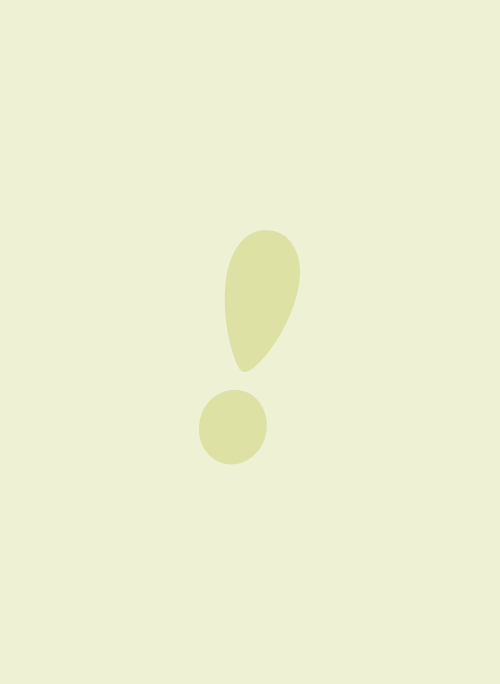「ふむ、うまい酒じゃ」
そこに焼きなすが運ばれてきます。
お市の方と目を合わせて微笑む明石の中宮。
添えてある味噌を和えながら中宮は優しくなすをほぐします。
盃を膳に置いて老いたる源氏は大きく口を開けます。
「はい、お上手。大好きなおなすをどうぞ」
「あちち」
「あらごめんあそばせ」
中宮はなすを戻しフーフーと吹いています。
「今度は大丈夫ですよ」
「ふむふむ」
源氏はおいしそうになすを食む。
「おじいさまはなぜ探すなとおっしゃったんでしょうかしら?」
「もぐもぐ、それには深い訳があるんじゃ」
「訳?」
「そうじゃ。わしにはよくわかる」
「今日は詳しく教えてください父上」
源氏は再び大きく口を開けます。
中宮は笑いながら焼きなすを運びます。
お市も惟光も笑っています。
「全ては入道殿の信心のあかしじゃ」
「住吉大明神?」
「そうじゃ、もともと気の荒い一本気のお方じゃった。
京におられてわしの遠戚でもあられる。ところがあの気性
じゃから都人からは疎まれて信心に走った」
「荒い気性を何とかせねばと思われて?」
「そうじゃと思うが、本来の気性などなかなか治るものではない」
「そう思います。お父上様も」
「なにをいう、親をからかうものではない」
「おほほほほ」
笑う中宮いとをかし。
「ところがじゃ、信仰心のあまりの厚さに気性は変わらぬが
その出方が変わった」
「と申しますと?」
これからが本題じゃというように源氏は手元の湯呑をさっと
手にして白湯を飲まれました。まるで目が見えるよう。
そこに焼きなすが運ばれてきます。
お市の方と目を合わせて微笑む明石の中宮。
添えてある味噌を和えながら中宮は優しくなすをほぐします。
盃を膳に置いて老いたる源氏は大きく口を開けます。
「はい、お上手。大好きなおなすをどうぞ」
「あちち」
「あらごめんあそばせ」
中宮はなすを戻しフーフーと吹いています。
「今度は大丈夫ですよ」
「ふむふむ」
源氏はおいしそうになすを食む。
「おじいさまはなぜ探すなとおっしゃったんでしょうかしら?」
「もぐもぐ、それには深い訳があるんじゃ」
「訳?」
「そうじゃ。わしにはよくわかる」
「今日は詳しく教えてください父上」
源氏は再び大きく口を開けます。
中宮は笑いながら焼きなすを運びます。
お市も惟光も笑っています。
「全ては入道殿の信心のあかしじゃ」
「住吉大明神?」
「そうじゃ、もともと気の荒い一本気のお方じゃった。
京におられてわしの遠戚でもあられる。ところがあの気性
じゃから都人からは疎まれて信心に走った」
「荒い気性を何とかせねばと思われて?」
「そうじゃと思うが、本来の気性などなかなか治るものではない」
「そう思います。お父上様も」
「なにをいう、親をからかうものではない」
「おほほほほ」
笑う中宮いとをかし。
「ところがじゃ、信仰心のあまりの厚さに気性は変わらぬが
その出方が変わった」
「と申しますと?」
これからが本題じゃというように源氏は手元の湯呑をさっと
手にして白湯を飲まれました。まるで目が見えるよう。