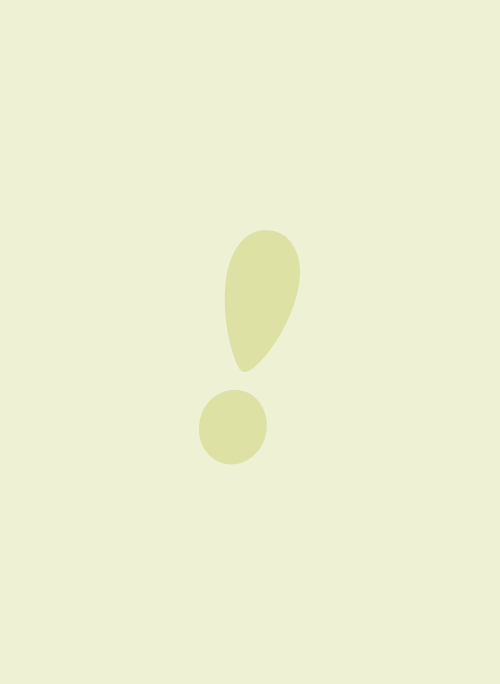「どうぞあまり冷えてはおりませぬが」
しわがれ声に源氏は思わず顔をそむけます。
甘えた声で玉鬘が源氏に語り掛けます。
「今日は折り入って聞きたいことがございます」
玉鬘は瓜の切り身を手に取って源氏の手指に添え
口に運びます。
「なんじゃな?何なりと申せ」
「はい私の母のことでございます」
「ふむ。母上のことは誰からも聞いておらんのじゃな」
「花散る母から亡くなったと聞きました。ずっと行方知らず
ということでしたから」
「そうか、夕顔の女御と言ってとてもきれいなお方じゃった」
「夕顔?」
「そうじゃ、わしが勝手につけた名じゃ」
「?」
「わしが十七の頃じゃ。焼きもちやきの年増の御息所にもう
ほとほとうんざりしてた頃じゃ。ばあやを訪ねて五条に寄った」
「十七?」
「そうじゃ。妻葵上、中宮藤壺、空蝉、六条の御息所。年増が多い」
「何という多情な」
「そんなもんよその頃は。ばあやがなかなか出てこない。そのとき
隣の壁に夕顔が咲いておったんじゃ。見とれておると女児が歌を添
えていい香りの扇を持ってきた」
「その主の方が?」
「そうお前の母君じゃ。この扇に乗せて夕顔を蔦ごと持って帰れと
いうわけよ。いじらしいではないかこんな小さなあばら家に住みながら」
「あばら家とは失礼な、私の母上がかわいそうにございます」
「いや、すまんすまん。それまでは殿上人ばかりで、ほんとのいい女
というものはこの中品の女御に逸品が隠れておると先輩が言うもので
少なからずそういうものかと興味はあったから」
「言い訳は見苦しいですよ父上殿」
しわがれ声に源氏は思わず顔をそむけます。
甘えた声で玉鬘が源氏に語り掛けます。
「今日は折り入って聞きたいことがございます」
玉鬘は瓜の切り身を手に取って源氏の手指に添え
口に運びます。
「なんじゃな?何なりと申せ」
「はい私の母のことでございます」
「ふむ。母上のことは誰からも聞いておらんのじゃな」
「花散る母から亡くなったと聞きました。ずっと行方知らず
ということでしたから」
「そうか、夕顔の女御と言ってとてもきれいなお方じゃった」
「夕顔?」
「そうじゃ、わしが勝手につけた名じゃ」
「?」
「わしが十七の頃じゃ。焼きもちやきの年増の御息所にもう
ほとほとうんざりしてた頃じゃ。ばあやを訪ねて五条に寄った」
「十七?」
「そうじゃ。妻葵上、中宮藤壺、空蝉、六条の御息所。年増が多い」
「何という多情な」
「そんなもんよその頃は。ばあやがなかなか出てこない。そのとき
隣の壁に夕顔が咲いておったんじゃ。見とれておると女児が歌を添
えていい香りの扇を持ってきた」
「その主の方が?」
「そうお前の母君じゃ。この扇に乗せて夕顔を蔦ごと持って帰れと
いうわけよ。いじらしいではないかこんな小さなあばら家に住みながら」
「あばら家とは失礼な、私の母上がかわいそうにございます」
「いや、すまんすまん。それまでは殿上人ばかりで、ほんとのいい女
というものはこの中品の女御に逸品が隠れておると先輩が言うもので
少なからずそういうものかと興味はあったから」
「言い訳は見苦しいですよ父上殿」